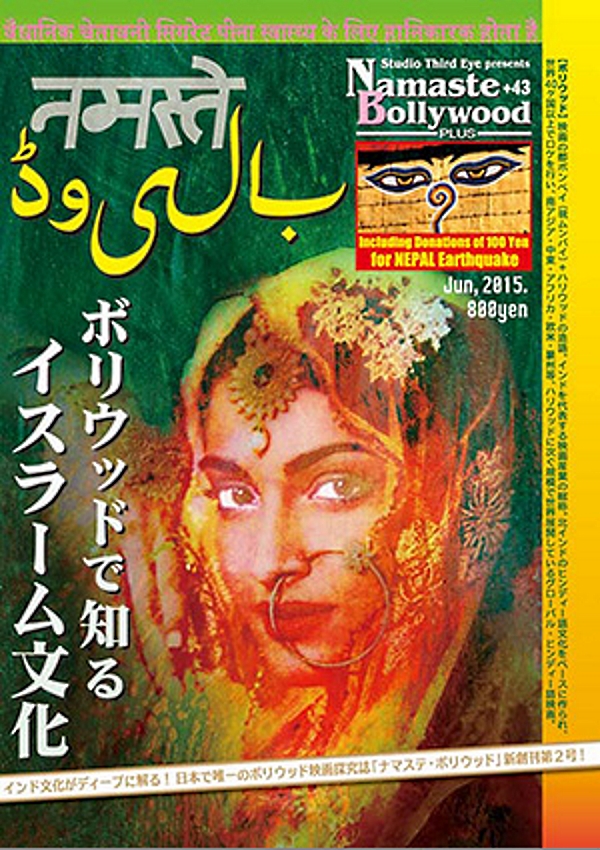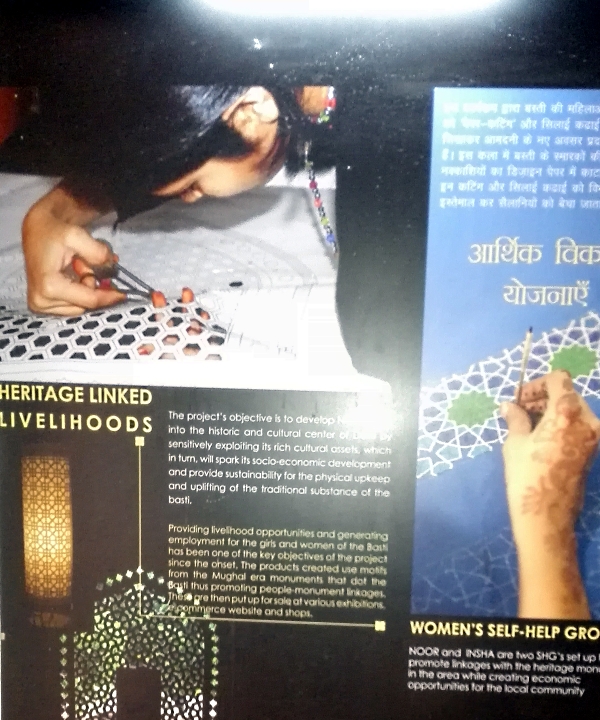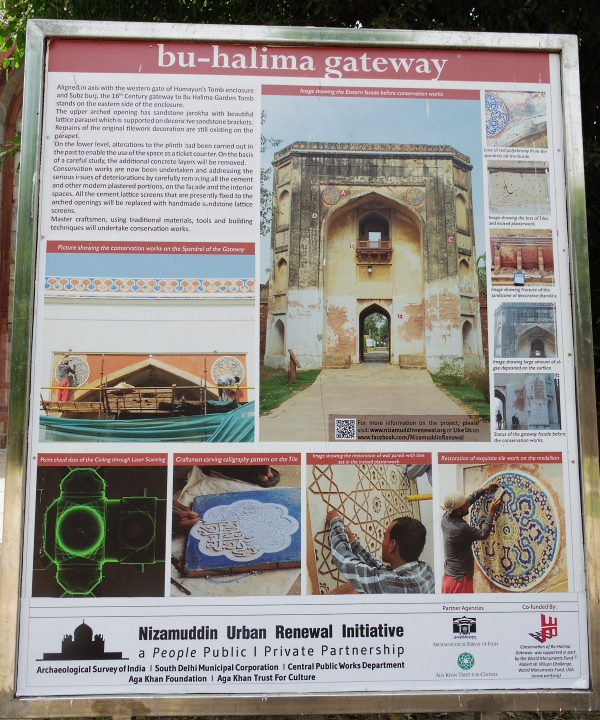隣国バングラデシュから経済的な理由からインドへ不法な移住を図る人々の流れは絶えず、常に政治問題となっている。
北海道の7割増程度の土地に約1億8千万人の人々が暮らすという人口があまりに稠密すぎるバングラデシュから雇用機会とより高い賃金を求めて、同じベンガル人が暮らす西ベンガル州、おなじくベンガル人たちが多く暮らす近隣州に出ようというのは自然なことでもあるだろう。もちろん彼らが移住する先はこれらに留まらず、インド各地の主要な商業地域や工業地域にも及ぶ。
そもそも同国が東パキスタンとして1947年にインドと分離して独立(その後1971年にパキスタンから独立して現在のバングラデシュが成立)したことが、悲劇と誤算の始まりであり、経済面・人口面での不均衡の根本でもある。
しかしながら、国家の成立には往々にしてその時代の流れに沿った必然と不条理が混じり合うものであり、その枠内で国家意識が形成されていくとともに、国民としての一体感も醸成されていくものだ。
そうした中でも、国境の向こうで異なる国籍が与えられることになった家族や親族に対して、こちら側の者はある種の憐憫の情を抱いたりすることもあれば、羨望の念を持つことも少なくない。同様に、宗教をベースとした分離の場合、ボーダーの向こう側にマイノリティとして残された、こちら側と同じ信仰を持つ者たちに対する「同胞」としての感覚には、社会で一定のシンパシーを共有することになることが少なくない。
ムスリムが大多数を占めるパキスタンにおけるヒンドゥー教徒たちの境遇については、インドでしばしば報じられるところであり、そこにも「国籍」の違いとは別次元の一体感があり、不幸にして異なる国籍を与えられることとなった「同胞」とでも言うような感情がベースにある。
さりとて、イスラームという宗教を旗印に、ムスリム主体の国家の建設を目指した東西パキスタンに対して、宗教的にニュートラルな「世俗国家」を標榜してきたインドとの決して相容れるところのない部分は、例えばカシミール地方の領有に関する両国の主張が平行線であるところにも現れる。
パキスタンと隣接する地域で、ムスリムがマジョリティであることが自国領であることが当然とすることがパキスタンの考えの根底にある。かたや宗教に拠らない世俗国家としてのインドにとっては、イスラーム教徒が多くを占めるからといってこれを隣国のものとするわけにはいかないのは当然のこととなる。現在、両国ともカシミール全域についてそれぞれ自国領であることを主張しているが、イギリスからの独立直後に勃発した第一次印パ戦争ならびに1965年の第二次印パ戦争の停戦ラインが実効支配線として、事実上の国境として機能することにより現在に至っている。
パキスタン建国に際して、多くのムスリムたちが当時の西パキスタンならびに東パキスタンへ流出するとともに、それらの地域からヒンドゥー教徒たちがインドに難民として逃れることになった。しかしそうした動きにもかかわらずインドを捨ててこれらの地域に移住することなく、あるいは経済的に移住することがならず、そのままインドに残ったムスリムたちも大勢いたわけだが、独立後はそうした人々が内政面での不安材料となることを避けるためもあり、インド政府は彼らの歓心を買うために様々な努力をする必要があったことは否定できない。ちょうど、欧州にて共産主義のソビエト連邦と隣接する地域で、高い福祉や社会保障制度が発達することとなったことと似ている部分がないでもない。
それが「世俗主義」を標榜しつつも、独立以降長年に渡って、少数派であるムスリムに譲歩する政策を継続せざるを得なかった理由でもあり、その世俗主義自体の矛盾と綻びであったとも言える。マイノリティとはいえ、規模にしてみるとの世界最大級のイスラーム教徒人口を抱えていることもあり、現実を見据えた上での選択であったはずだ。
しかしながら、このあたりが圧倒的なマジョリティを占めるヒンドゥーたちから成る社会の中での不満を醸成することになったのも事実で、宗教別に定められている民法について1980年代末あたりから、「統一民法」の制定を求める声が高まっていくこととなる。これがやがて90年代にはいわゆる「サフラン勢力」の核となるBJPに対する支持数の急速な伸張へと繋がっていく。
その後、国民会議派を中心とするイスラーム勢力や左派勢力を含む統一進歩同盟(UPA : United Progressive Alliance)とBJPがリードする保守から中道あたりの政党が集結した国民民主同盟(NDA : National Democratic Alliance)が一進一退の駆け引きを続けている。
さて、このほどインドの北東地域では、隣国バングラデシュからの不法移民について、バングラデシュから来たヒンドゥー教徒に対して市民権を与えるべきだと唱えるBJPに対して、国民会議派はヒンドゥー、クリスチャン、仏教徒(要は非ムスリム)の移民に対して市民権付与による保護を訴えるという形で、信仰を根拠とする論争が起きている。
こうした主張はインドの独立以来の国是である世俗主義に対する挑戦であるとともに、とりわけ国民会議派については、大きな方向転換のひとつの兆しであるのかもしれないようにも思える。
同時に、インドにおけるこうした動きについて、隣国バングラデシュ国内に与えるインパクトも少なくないかもしれない。同国内人口の一割近くを占めるヒンドゥー教徒たちの取り込みと捉えることも可能であるとともに、コミュナルな対立が発生した場合に、「インドによる差し金」を示唆する口実にもなろうし、敵性国民として排斥する動きに出ることもあり得ないことではないだろう。
宗教をラインとする国家形成を経てきた国と、世俗主義を国是として歴史を刻んできた国の間で、それなりのバランスが保たれてきた中で、後者が前者と近いスタンスを取ることになることについて非常に危ういものを感じる。
インド東北部におけるこうした動きが現実のものとなるようなことがあれば、やがてインドとバングラデシュの間での国際的な問題に発展する可能性を秘めていることから、今後の進展には注目していきたい。
BJP & Congress Raring to Provide Citizenship to Hindu-B’deshi Migrants (Northeast Today)