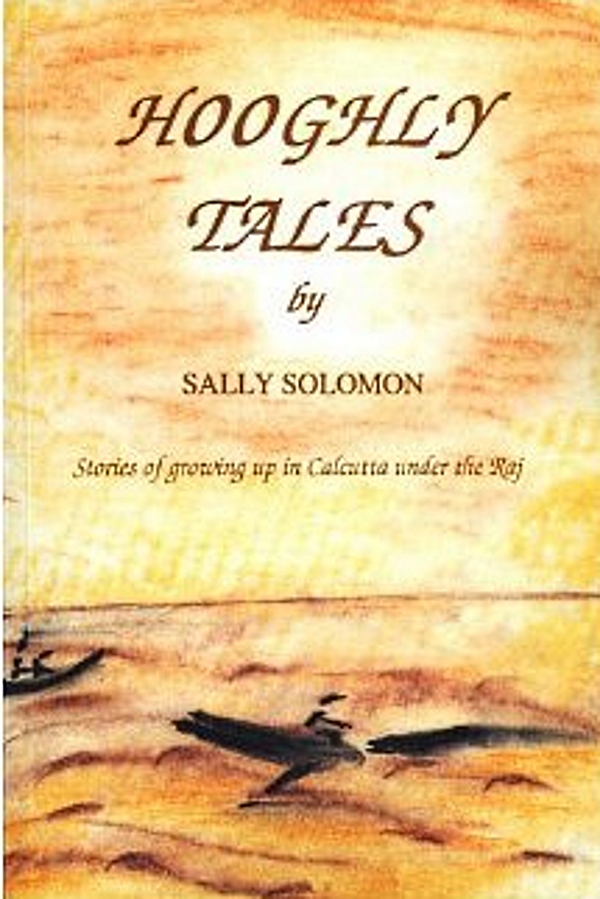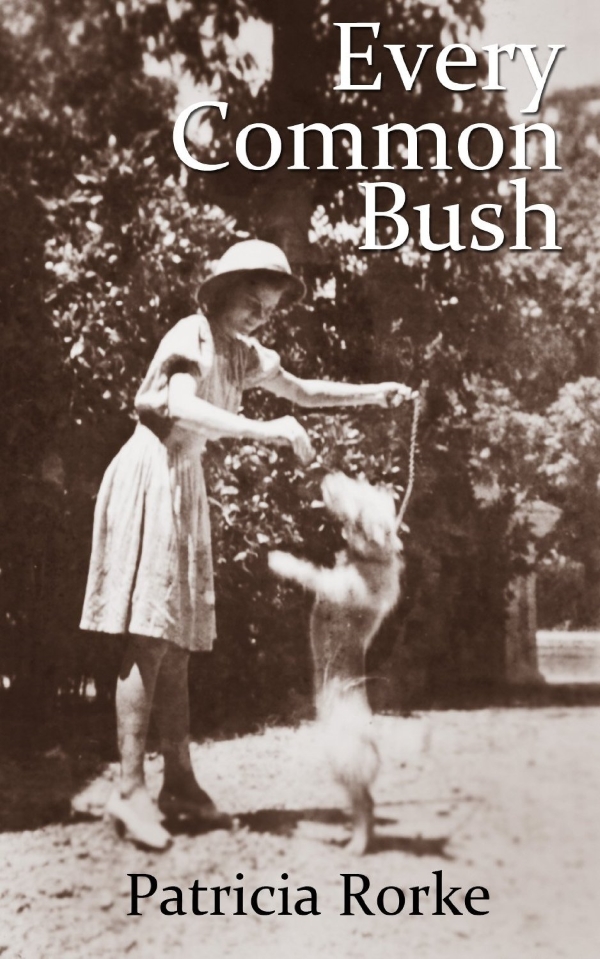かつて「10 SUDDER STREET」で取り上げたように、タゴール家の持家のひとつがここにあった。同家から出た詩聖ラビンドラナート・タゴールがしばらく起居したこともあるというがあったと聞く。そんなサダル・ストリートは、今のような安宿街という趣とはまったく異なる閑静な住宅地であったのだろう。
大きな商業地域を抱えるチョウロンギー通り界隈に隣接しているが、ごく近くにインド博物館、Asiatic Society、サウスパークストリート墓地のような植民地期の白人墓地があるとともに、由緒ある教会もある。
また、「サダル・ストリート変遷」で紹介してみたように、19世紀あたりから、ユダヤ人たちも多く居住する時期もあった。著者であり、主人公でもあるSally Solomonという女性が、この作品内で描いた自分自身の子供時代から新婚時代までにかけての物語は、彼女ら家族が居住していたエスプラネード北側のBentinck Street、そして引っ越した先でSudder StreetとMarquis Streetの間に挟まれたTottee Laneで展開していく。
彼女の先祖はシリアのアレッポから移住したShalom Aaron Cohen。カルカッタのユダヤ人社会では伝説的な偉人だが、彼女の時代にはごくありふれたロワー・ミドルクラスの家庭のひとつとなっている。
先祖が日常的に着用していたアラブ式の装いや家庭内で使用していたアラビア語は、彼女の世代にとってはとうの昔にエキゾチックな存在となっており、これらは洋装と英語に置き換わっている。これは17世紀初頭から19世紀にかけて、中東地域からインドに移住した、いわゆる「バグダディー・ジュー」と呼ばれる人々に共通した現象で、インドに定着するとともに生活様式が洋風化していったのは、偶然の所作ではなく、商業の民の彼らの稼ぎ口が当時インドを支配していた白人社会にあったからである。
英領時代のカルカッタの街のコスモポリタンぶり、市井の人たちの暮らしぶりを知るための良い手がかりになるとともに、カルカッタを旅行で訪れた人にとってもなかなか興味深いものとなるのではないかと思う。20世紀前半のサダル・ストリート界隈での暮らしや出来事、ごく近くに立地するニューマーケットの様子などが活写されており、カルカッタで現存する最古の洋菓子店あるいは様式ベーカリーとして知られる「ナフーム」も出てくる。
サダル・ストリート界隈に、今なお多く残る昔はそれなりに立派であったと思われる屋敷や建物(たいていは内部が細分化されて貸し出されていたり、転用されていたりするが)のたたずまいから、そうした過去に思いを巡らせてみるのはそう難しいことではない。
Hooghly Tales – Stories of growing up in Calcutta under the Raj (English Edition) [Kindle版]
著者 : Sally Solomon
ASIN: B00EYTNNMK