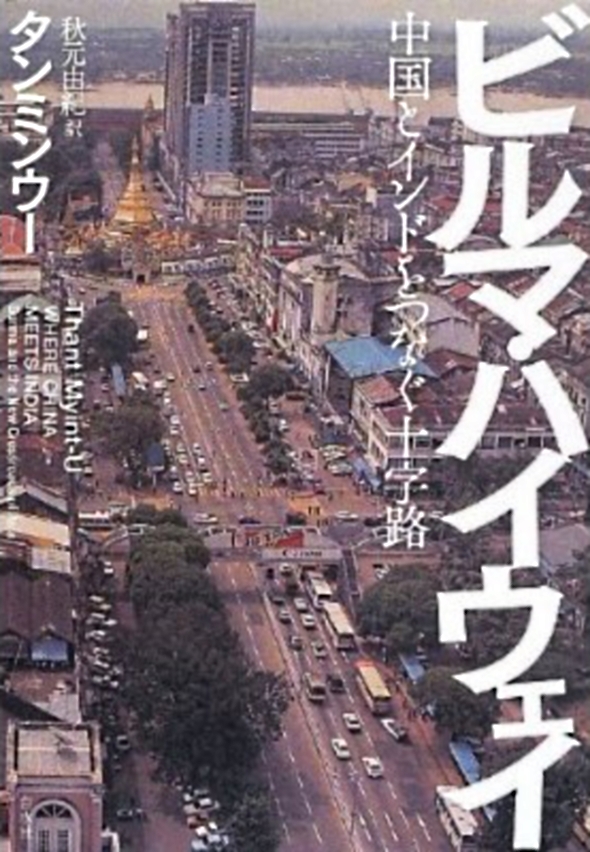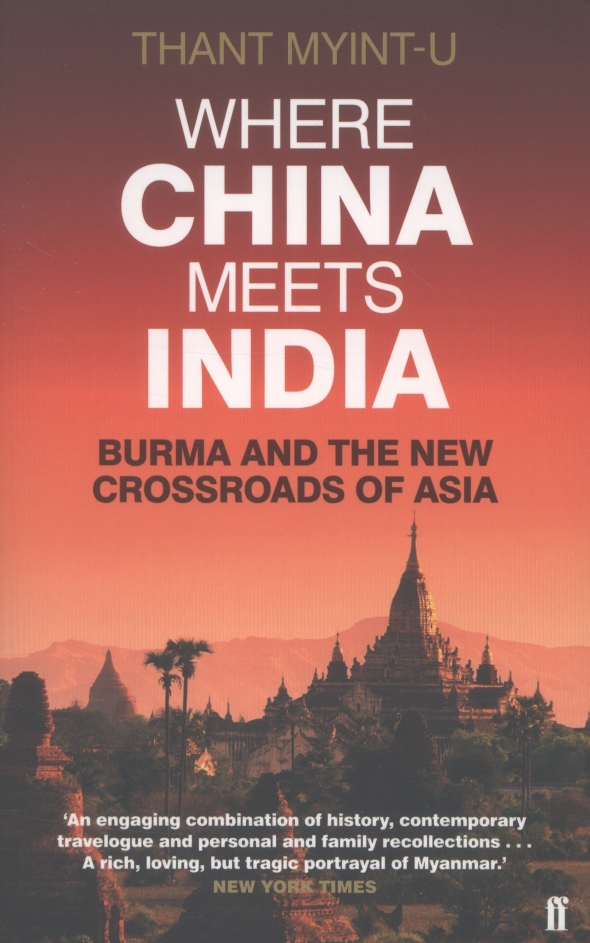コールカーターで、ある若い日本人男性と出会った。
インドの隣のバーングラーデーシュに4か月滞在して、グラーミーン・バンクでインターンをしていたのだという。これを終えて、数日間コールカーターに滞在してから大学に戻るとのこと。彼は、現在MBAを取得するためにマレーシアの大学に在学中である。
マレーシアの留学生政策についてはよく知らないのだが、同級生の半分くらいが国外から留学しに来ている人たちだという。
今や留学生誘致は、世界的に大きな産業となっていることはご存知のとおりだが、誘致する側としては英語で学ぶ環境は有利に働くことは間違いなく、留学する側にしてみても英語で学べるがゆえに、ハードルが著しく低くなるという利点があることは言うまでもない。
同様のことが、ターゲットとなる層となる自国語が公用語として使われている地域が広い、フランスやスペインなどにも言える。これらに対して、国外に「日本語圏」というものを持たない日本においてはこの部分が大きく異なる。
出生率が著しく高く、世帯ごとの可処分所得も潤沢な中東の湾岸地域にある産油諸国においては、急激な人口増加に対する危機感、そして石油依存の体質から脱却すべく、自前の人材育成に乗り出している国が多く、とりわけ欧米諸国はこうした地域からの留学生誘致に力を入れている。昨年、UAEのアブダビ首長国で開かれた教育フェアにおいては、日本も官民挙げて力を注いだようだが、来場者たちは日本留学関係のエリアはほぼ素通りであったことが一部のメディアで伝えられていた。
投資環境が良好なUAEにおいては、Dubai International Academic Cityに各国の大学が進出して現地キャンパスを開いているが、それらの大学はほぼ英語圏に限られるといってよいだろう。やはりコトバの壁というものは大きいが、こういうところにもインドは堂々と進出することができるのは、やはりこの地域との歴史的な繋がりと、英語力の証といえるかもしれない。
日本政府は中曽根内閣時代以来、留学生誘致に力を入れているものの、現状以上に質と規模を拡大していくのは容易ではなく、「留学生30万人計画」などというものは、音頭を取っている文部科学省自身も実現不可能であると思っているのではないかと思う。仮に本気であるとすれば、正気を疑いたくなる。
もともと日本にやってくる留学生の大半は日本の周辺国であり、経済的な繋がりも深い国々ばかりであり、その他の「圏外」からやってくる例は非常に少ない。また、日本にやってくるにしては「珍しい国」からの留学生については、日本政府が国費学生として丸抱えで招聘している例が多いことについて留意が必要である。そうした国々からは「タダで学ぶことができる」というインセンティブがなければ、恐らく日本にまでやってくることはまずないからである。
身の丈を越えた大きな数を求めるのではなく、質を高めるほうに転換したほうが良いのではないかと思うが、ひょっとすると、少子高齢化が進む中で、外国から高学歴な移民を受け入れて、労働人口の拡充に寄与しようという目的もあるのかもしれないが、実際のところは、学齢期の人々が漸減して、冬の時代を迎えている国内の大学の生き残りのための政策なのではないだろうか。
こればかりはどうにもならないが、もし日本が「英語圏」であったならば、様々な国々からの留学生の招致は現状よりももっと容易であったに違いない。