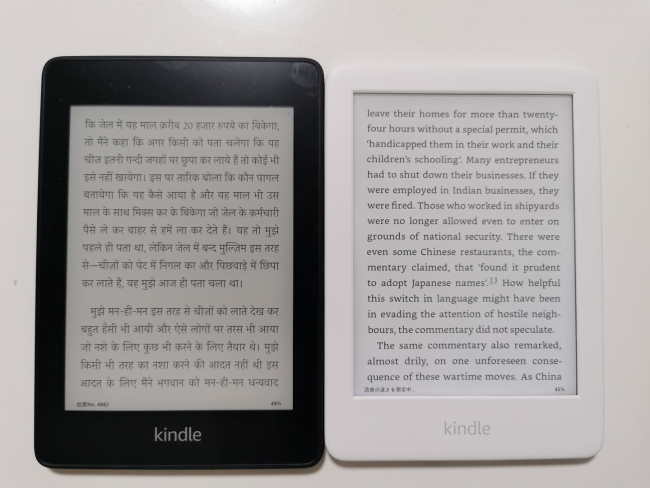ウッタラーカンドはひどい荒天による洪水や地滑りなどで大変なことになっている。メディア各社がへ報じているところだがAajtakのようなヒンディー語メディアとともにIndia Todayの英語ニュースも24時間オンエアーされているのでご参考願いたい。
それにしてもヒンディー語メディアではインド北部各地のさまざまなニュース、とりわけ「ヒンディーベルト」は当然としても、その周辺地域のベンガル、グジャラート、そしてマハーラーシュトラ関係の出来事も報じられるいっぽう、南インドに関しては、大物政治家が突然亡くなったとか、大災害が起きたとか、よほど大きなことが起きない限り、ほとんど出てこない。ケーララ、タミルナードゥなどはまるで外国のようだ。
大きな国なので、言語圏が生活圏であり、興味関心の圏内であることがよくわかる。それがゆえに、各地方語の番組がそれぞれの地域では圧倒的な支持を得るのだろう。Zee TVのベンガル語のエンターテインメント番組は隣国バングラデシュでもよく視聴されているようで、人々の支持も高いようだ。同時にベンガル語によるZee News番組もなんとなく目にしているはずなので、インドの事情についても相当詳しいはずだ。たぶん西ベンガル州の人たちはバングラデシュで起きていることについてはあまり関心はないだろう。
バングラデシュからは休暇時期にカルカッタやメガーラヤ州などに家族や仲間と出かけたりする人は多いし、カルカッタで先進医療を受けるために定期的に出てきている人も知っている。そういうのもかなり多いらしい。やはりそのあたりでも、国は違っても同じベンガル語世界ということで、ひとつの「地元圏感覚」のようなものがあるようだ。