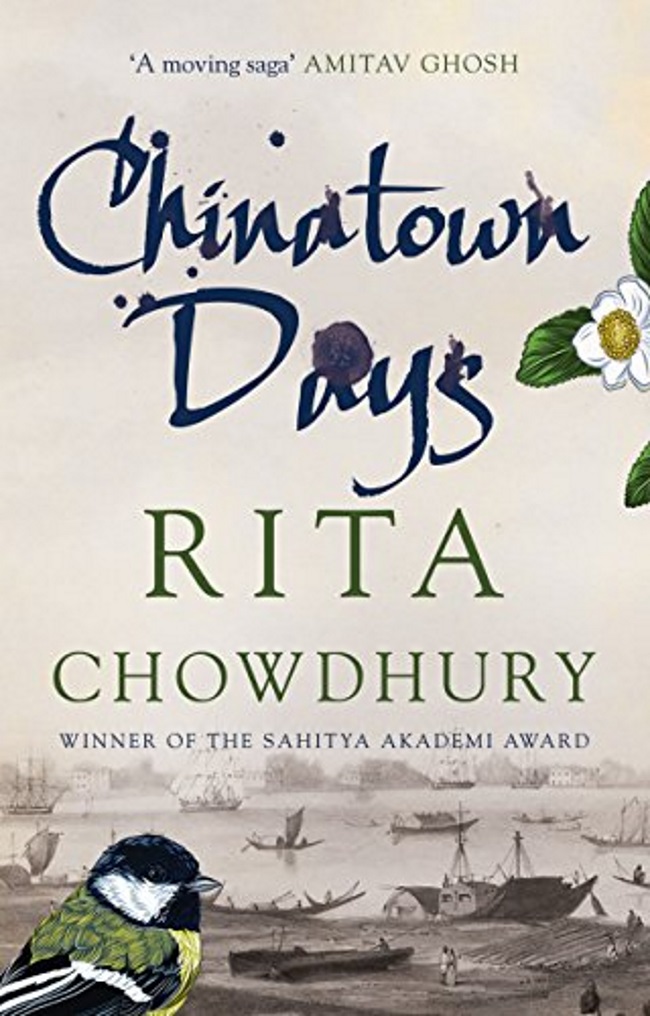アッサムの女性作家、リーター・チョードリーによる大作。
清朝支配下の19世紀、南中国の寒村から奴隷として町の商人のところに売られていき、そこで奴隷ながらも主の信用を得て、それなりの金銭的充足と自由を得ることとなった少年。だが、彼はさらにここから別の人身売買シンジケートにより、カルカッタへ運ばれ、そこから開業間もないアッサムの茶園に行くこととなる。
時代は下り、その茶園近くのマークームの町や周辺で事業を起こした中国移民の子孫たち。
アッサムのすっかり根付き、「中国系アッサム人」として地域社会の中の一部として定着していた。
中印戦争開戦。最初は特に影響を受けることのなかった華人コミュニティだが、インドの敗色濃くなっていくにつれて、反中国感情の高まりとともに、中国系住民への感情も急速に悪化していく。
中国との敵対関係がエスカレートしていくとともに、国内政治でも共産主義勢力を「親中かつ反インド」であるとして攻撃するだけではなく、民族的なルーツを中国に持つ人々への風当たりも強くなってくる。
やがて中国系市民の拘束の命令が中央政府から発せられ、華人が集住していたカルカッタはもちろんのこと、ところどころに華人コミュニティが散在していたアッサム(当時は現在のメガーラヤもアッサムの一部)においても一斉に彼らを逮捕して地域内の刑務所へ収容してしまう。驚いたことに、チベットからダライラマとともに亡命してきたチベット難民の中にも、このあおりで逮捕・拘束された人たちが少なくなかったらしい。
その後、華人たちは、まとめてラージャスターン州のデーオーリーキャンプへと列車で移送される。(デーオーリーキャンプは、奇しくも第二次大戦期にマラヤ半島などに住んでいた日本人たちが敵性外国人として植民地当局に検挙されて移送された先でもある。)
インド政府は、世代を継いでアッサムに暮らし、インドを祖国とする中国系市民を敵視するいっぽう、引き揚げ船を仕立てて彼らを迎えるというオファーをする中国に対して、これ幸いと彼らの身柄を引き渡してしまう。インド生まれの華人たちにとって中国は未知の国。おりしも時は文革の渦中で、引き揚げてきた彼らはインドによるスパイという嫌疑もかけられて大変な苦難を重ねることとなる。
中国に送られることなく、アッサムに帰還することができた華人たちにとっても、日々は決して楽なものではなかった。苦労して得た工場、店、家屋などは、「敵性資産」として、競売にかけられており、彼らの父祖がそうであったように、再び裸一貫でスタートしなくてはならなかったからだ。
文革の嵐が収まりかけたあたりから、中国に送られたアッサム華人たちの中で、当時英領だった香港を目指すのがひとつの流れとなっていった。
そして現在、結婚したばかりの華人妻と生き別れになったアッサム人男性が、かつてマークームに暮らした華人住民たちの小さな集まりが開かれる香港を訪問して49年振りに再開。
雄大な時間軸の中で展開していくスケールの大きなドラマ。こうしたインド系の人々の歴史を交えた長編作品を得意とする大作家アミターブ・ゴーシュの作品を彷彿させる。
もともとマークーム(মাকুম)と題して2010年にアッサム語で発表された当作品だが、好評を得て英語版も出版されることとなったが、翻訳版という形ではなく、新たな記述等を加えて最初から書き下ろすことになったため、英語版の出版まで何年もかかったと聞いている。
タイトル:Chinatown Days
著者:Rita Choudhury
出版社:Amazon Services International, Inc.
ASIN: B0786T8XKX
※紙媒体ではなく、アマゾンのKindle版を入手。