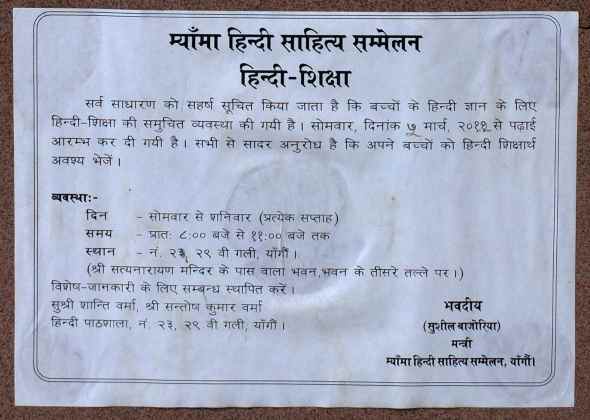1975年に公開されたラメーシュ・スィッピー監督による映画SHOLAYといえば、インド映画史上最大のヒット作のひとつ。今も燦然と輝く金字塔的な存在だ。
若き日のアミターブ・バッチャン、ダルメーンドラが出演し、この映画の制作を通して、前者とジャヤー・バッチャン、後者とヘーマー・マーリニーというビッグなカップルが二組も誕生した。
ダルメーンドラについては、当時すでに妻子持ちであったのだが、最初の結婚を解消することなく、ヘーマー・マーリニーを娶るという離れ業?を遂げている。おそらく家庭内では大変な騒動になっていたのではないだろうか。
ダルメーンドラと同じく俳優のサニー・デーオールとボービー・デーオールは最初の結婚で出来た息子たち。女優として活動しているイーシャー・デーオールは、彼らの異母妹にあたる。
アミターブ・バッチャンとダルメーンドラという、当時の若きヒーローたちの存在に加えて、SHOLAYを歴史的な大作の地位にまで押し上げたのは、二人が演じる主役との対立軸に、悪役の中でも迫力に抜きんでた名優アムジャド・カーンがいたからだろう。彼が演じた役柄「ガッバル・スィン」は、名前そのものが悪漢、盗賊の代名詞のようになったほどだ。
SHOLAYのリメークとして、近年はラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督のAAGが話題になったが、1991年にはパロディ作品でRamgarh Ke Sholayというコミカルなもの(低予算な映画だが面白かった)もあった。隣国パーキスターンでも、似たような映画が制作されていたようだし、インド国内でも、地方映画でこれに触発された作品があったのではないかと思う。
今年8月には、本物のSHOLAYが3D化されて公開予定。封切りは、8月15日。インドの独立記念日である。老若男女、誰もがよく知っている映画ではあるが、再度大きなヒットを期待したい。
Gabbar Singh set to return on screen, this time in 3D (India Today)