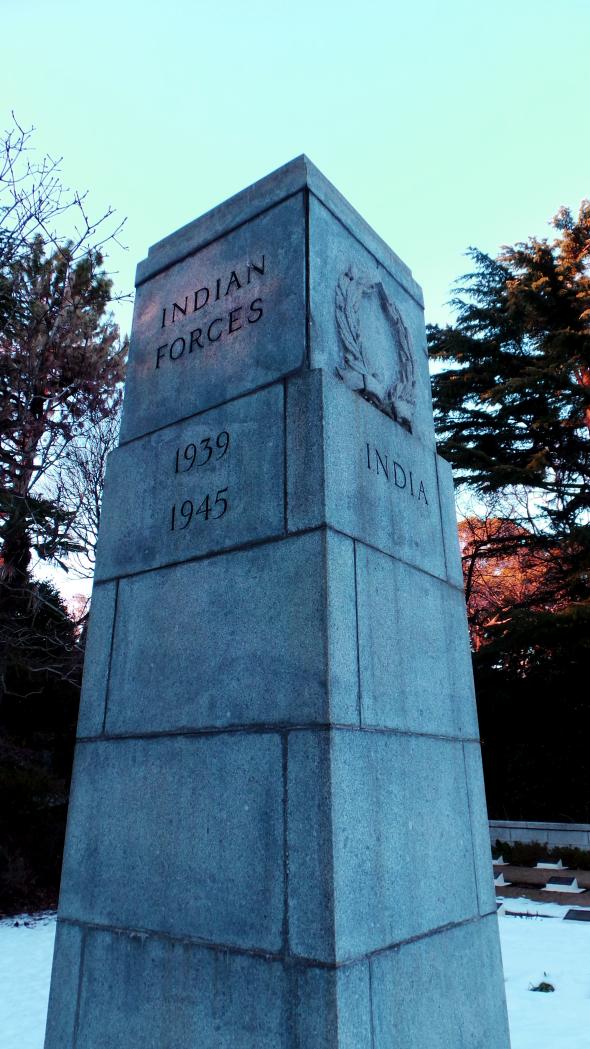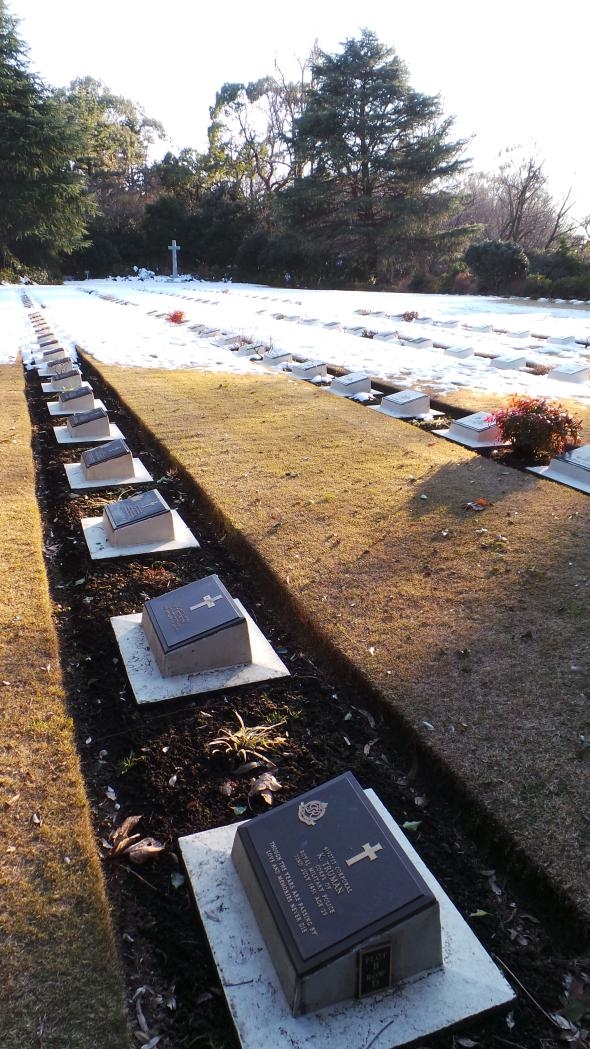ミャンマーで、1962年に起きた軍部によるクーデター以降、約半世紀ぶりに民間の新聞が復活しているというニュースが流れたのは、ごく先日のことだ。
ミャンマー、民間日刊紙が半世紀ぶりに復活 (asahi.com)
この民間の新聞の中で、おそらくほとんどがビルマ語紙で、ひょっとしたら英字紙も含まれているのかもしれない。旧英領といっても、英語の通用度はインドと比較のしようもないほど低いミャンマーには、それなりの理由がある。
イギリスによる支配の歴史がインドに較べるとかなり短いこと、そして独立後のインドにおいて英語が果たしてきた大きな役割とは裏腹に、支配的な立場にあるビルマ族による「国粋化」により、日常の商取引や教育の場から英語が駆逐されたミャンマーとでは、英語の位置付けそのものが大きく異なる。インドにおいて、英語は(たとえそれを理解しない人が過半数を占めているとしても)インドの言葉の中でも重要な地位を占めているが、現在のミャンマーにおいては、英語は外国語にしか過ぎない。
英字紙はともかく、おそらく1962年のクーデター以前には、ヤンゴンその他の都市部では広く流通していた中国系住民のための華語紙、インド系住民を対象としたウルドゥー紙その他の外来の言語によるメディアの復活はありそうにはないようだ。
ミャンマーでは、新聞や雑誌等に対する事前検閲は廃止されたものの、発行後の事後検閲は継続している。管理に手間のかかる外国語によるメディアについてはなかなか許可が出にくいものであろうと想像される。また、1962年以前は都市部人口にかなり高い割合を占めていた中華系、インド系の人々が軍政の始まりとともに、大挙して国外に流失してしまったという事情もある。
話者人口の規模が縮小するとともに、世代交代が進むにつれて、自然と父祖の母語を理解する人々は減り、理解度という面においても水準は下がっていくのは当然のことだ。
ヤンゴンのあるヒンドゥー寺院では、地元のインド系住民の若年層を対象にした「ヒンディー語教室」が開かれている。そこで教えている男性に話を聞いたことがあるのだが、話者人口や世代交代だけではなく、インド系の言語によるメディアが廃止されたことによる言語面でのインパクトはかなり大きかったようだと語ってくれたことを思い出す。
「だって、あなた、読み書きする機会が減れば、語彙も乏しくなるでしょう。言葉が乏しくなれば不便になって、あまり使わなくなってしまいますよ。するとどんどん先細りになっていく。喋った先から消えて行ってしまう話し言葉だけじゃなくて、やっぱりきちんとした文章を日常的に読むということは大切ですから・・・」
20世紀初頭のヤンゴンでは、住民の半数以上がインド系の人々が占めていた時期もあり、非インド系の人々の間にもヒンディー/ウルドゥーが通じるというのがごく当たり前といった状況であったようだ。
ヤンゴンで、今のインド系住民の間で、インド系の言語による新聞が復活することはないだろう。それでも、ダウンタウンのインド人地区でモスクの中や周辺では、ウルドゥー語による会話が聞こえてくることはしばしばあるし、ヒンドゥー寺院に出入りする人々の会話にしばしばヒンディーによるやりとりが含まれることはよくあるようだ。
やはり言葉というものには、単に意思疎通の手段としての道具という以上に、民族のアイデンティティとしての意味合いも大きい。インドから移民して数世代経過している人々の間では、地元ビルマ語が母語になっているとはいえ、宗教施設での説法や人々の会話の中にそうした父祖の言葉による会話が挿入されることが多いのは当然のことなのだろう。
そんな環境の中で、曲がりなりにもヒンディー/ウルドゥーを理解するということに対する、インド系の人々の反応のポジティヴさには驚かされる。インドではずいぶん粗末に扱われている印象を拭えない言葉に対する人々の愛着には心動かされずにはいられない。
ミャンマーで、ヒンディーやウルドゥーの新聞や雑誌が復活することはないにしても、コストのかからないウェブ上でのニュースサイトが出てくることは、有り得ないことではないように思う。
報道や表現の自由度の拡大や経済発展へと向かう中、これにより本国とは遠く離れた環境下で細々と続いてきたインド系言語環境が利するところはあるのか、今のところはまだよく判らない。