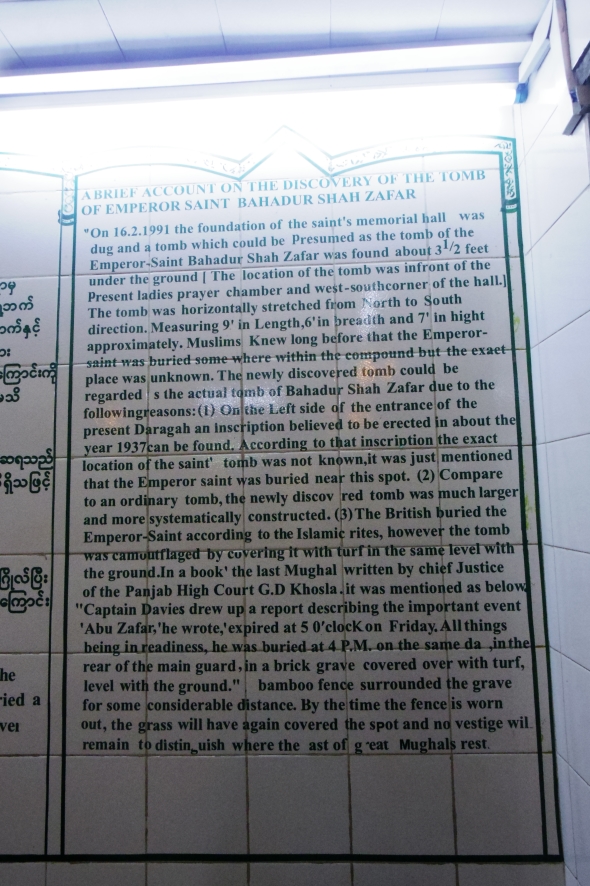この町で少々気になったことがある。ヤカイン州といえばロヒンギャー問題で海外にもよく知られているところだ。ロヒンギャーとは、ベンガル系のチッタゴン方言に近い言葉を母語とするムスリム集団のことだが、すでにこの国に数世代に渡って生活しているにもかかわらず、「ベンガル人の不法移民」「外国人」とされており、この国で市民権を与えられていない宙に浮いた存在である。
近年は、ムスリムに対する暴動が発生して、モスクやムスリムの家屋に対する破壊行為が起きたこと、多数の死傷者が出るとともに、避難民を数多く発生させたこともメディアで伝えられていたのを目にした人も多いだろう。
ミャンマーの中ではとりわけイギリスによる植民地史の中で早い時期からインド系の移民の波にさらされた土地であること、港町として南アジアとの往来も盛んであったことから、インド系の人々の姿が非常に多いであろうことを予想していたのだが、意外にも港湾エリアを中心とする繁華街ではインド系の人々、ムスリムの人々の姿が非常に少ない。
繁華街の目抜き通り(Main Rd.)には、ジャマーマスジッドという名で、立派なムガル風建築のモスクがあり、おそらくこのあたりには相当数のムスリムが住んでいたのではないかと思われるが、周囲のマーケットはそのような雰囲気ではない。モスクそのものも現在は使われていないようで、入口につながる小道にはバリケードがあり、武装した治安要員が警備に当たっており、足を踏み入れるまでもなく、その前に立ち止まるだけで追い払われてしまう。
ヤンゴンから飛行機で到着した際の空港から市内への道筋にも、小ぶりながらも由緒ありそうな凝った建築のモスクがいくつかあったのだが、どれもそうした制服の男たちが入口を塞いでいた。
市内中心部でも繁華街の目抜き通り(Main Rd.)から西に進んだエリアに行くと、ところどころでインド系の人々を目にした。そんな中に、いくつかのヒンドゥー寺院があった。おそらく最も大きなものが、マハーデーヴ・バーリーという、名前からしていかにもといったシヴァ寺院だ。
入口の鉄扉を開けて中に入ると、若い男性が「何か用か?」といった不審そうな面持ちで出てきたが、インド系の人々のお寺に関心があること、ぜひ神殿で拝ませて頂きたいという来意を伝えると、快く迎えてくれた。
お堂の中は簡素で、祭壇にはシヴァの絵と小さなリンガムが祀られているというシンプルなもの。だがその反対側の壁にはシヴァの連れ合いであるドゥルガーの立派な神像があり、本尊は実は後者なのではないかと思われるくらいにアンバランスである。ドゥルガーやカーリーへの信仰の厚いベンガル系の信者から寄進されたものではないかと思う。
ミトゥン・チャクラボルティーという、ヒンディー語映画のベテラン俳優みたいな名前のこの男性はこのお寺のプージャーリー。快活な感じのする男性で、ヒンディー語もなかなか上手い。名前の示すとおりのベンガル系で、20代後半で昨年結婚したばかりだが、来月初めての子供が生まれる予定であるとのことで、境内には身重の奥さんもいたが、彼女はヒンディーを話すことはできないようであった。
現在、母親とお嫁さんとの3人暮らしであるそうだ。父親は20年ほど前にカルカッタに行ったきり、消息を絶っているとのこと。「父が先代のプージャーリーで、私がこうして継ぐまでしばらく空いているんです。私が幼いときに仕事を求めてカルカッタに行ったのですが、それっきりどうしているのかも判りません。もちろん私たちはベンガル人ですが、父はカルカッタに何かツテがあったのかどうかは判りません。そんな具合であったので、母は大変苦労したようです。」
特に身の上話を尋ねたわけではないのだが、いろいろと聞かせてくれるのはインド系の人らしいところかもしれない。しばらく世間話をした後、「少々お待ちいただけますか。」と言い残してどこかに姿を消した彼は、サフラン色のローブを纏って現れて、私のためにプージャーをしてくれた。
彼の家族は曽祖父の代にベンガルから移民してきたというが、今でもベンガル語とヒンディー語は使えるということから、この地のインド系のコミュニティの絆はもちろんのこと、人口規模も決して小さなものではないことが窺える。
そこからごく近いところに、ダシャー・プージャー・バーリーというヒンドゥー寺院もあり、ここもまたプージャーリーの男性に挨拶すると、非常に愛想よく迎え入れてくれた。こちらはカーリーとドゥルガーを祀った寺であり、プージャーリーはさきほどのマハーデーヴ・バーリーのプージャーリーと同じ苗字を持つベンガル系のブラフマンの50代男性だが、親戚ではないそうだが、年代が上であるだけに、さきほどの男性よりもヒンディーが流暢で、彼らのコミュニティに関する知識も豊かなようである。
彼によると、この町に暮らすヒンドゥーの人々はおよそ3,000人程度。インド系という括りで言えば、ムスリムがマジョリティで彼らは少数派だそうだ。かつてはもっと多くのヒンドゥー(およびインド系ムスリム)が暮らしていたそうだが、1962年のネ・ウィン将軍によるクーデター以降、多くは国外に移住したとのことだ。
近年においては、この地における反ムスリムの動きが、彼らヒンドゥーの立場をも悪くしているという。「このあたりでは、インド系といえばムスリムのほうが多いでしょう。ロヒンギャーの問題もあるし、私らヒンドゥーも同じように見られてしまう部分がある。とりわけムスリムに対する攻撃が始まってからは、私らも必要なとき以外はなるべく外に出ないようにしています。この地域に暮らすということはリスクと不便があまりに多い。」とのこと。あれほどインド本国では圧倒的な重みを持つインド文化も、この地にあってはその輝きほとんどなく、まるで隠れキリシタンのような趣さえある。
「私の祖父がインドからやってきました。ここのヒンドゥーの間ではベンガル人が多いですが、U.P.やビハールからの移民もいれば、マールワーリーもいるし、グジャラーティーもいます。でも私らの間では正直なところ、先祖がやってきた地域の区別はあまりないんです。結局、同じヒンドゥーでしょう?」
この界隈には、他にゴーランガー・マハー・プージャー・バーリー、ハリ・マンディル、ラーダー・クリシュナー・マンディルといったヒンドゥー寺院がある。
翌日にはこの地域のインド系の人の結婚式があるので、ぜひ出席しないかと誘われた。ぜひともよろしくお願いしますと言いたいところであったが、タイトなスケジュールでのミャンマー訪問で、その日にはすでに移動する予定であったので、後ろ髪を引かれる思いながらも辞退せざるを得なかった。寺院を出て、しばらく進んだ先では着飾ったヒンドゥー女性たちが乗合自動車から降りてどこかに向かうところであったので、この婚礼と関連するものが行われていたのではないかと思う。
寺の外でも、インド系の人々は総じてフレンドリーな印象を受けたが、この「インド系タウンシップ」を徘徊するのはなかなか面倒なことでもあった。というのは、辻のそこここに警察のバリケードがあり、POLICEと大書きした車両が行き交う中で、そうした地域に足を向けようとすると、往々にして「こちらに立ち入るな」と追い返されたり、職務質問を受けたりするからだ。
中には非常にガードが堅い路地もあり、一体その先には何があるのかと興味をそそられるものの、路地の反対側から進入することを目指しても、迂回路を探してみても入ることができなかったりする。
ときに多少の英語ができる警官もおり、「ロヒンギャーたちがいる地域であるから危険なので入らないこと。」とのこと。ロヒンギャーの人々が危険であるのかどうかはともかく、このように常に監視の対象になっているということ、それが州都であることを思えば、その他の地域では一体どんな扱いをされているのかと思う。
こうした中で、ヒンドゥーたちが監視の対象になっているのか、保護の対象になっているのかわからないが、やはりインド系の人々全体がロヒンギャーと同義に扱われているかのような印象を受けるとともに、こうしたインド系が住むエリアそのものが警備の対象となっているようにも感じられた。
英領期に、ここに移住してきたインド系の人々の多くは、当時のヒンドゥスターンの新天地として入植してきたはずだが、結局こうしたやってきた大地はいつの間にかヒンドゥスターンの一部ではなくなり、彼らの父祖の故地もひとつのインドからインドとバングラデシュに分かれてしまい、コミュニティとしては大きなものであったインド系の人々自体がいつの間にかマイノリティとなり、しかも監視の対象にさえなってしまったことになる。
かつてイギリス領であったこと、隣接しているインド亜大陸からの移民が多いことから、しばしばインドの北東部にいるかのような気にさせられることもあるミャンマーの中でも、地理的に最もインド世界に近い場所にある地域だ。
インドの北東部でモンゴロイド系の住民がマジョリティを占めるエリアを訪れると、「インドの中にあってインドでない」といった印象を受けるが、それでもインド共和国という政治システムの中の一地方であるがゆえに、インドという存在は至高のものであるとともに、圧倒的な存在感をもってその地に君臨している印象を受けるものだ。しかし、その法的・軍事的な強制力が及ぶ圏外であるここでは、インドという国が非常に遠く感じられるとともに、インド系の住民なり文化なりが非常に無力なものに感じられる。
もしインドの北東部が本土から分離するようなことがあったりすると、まさにこのような感じになるのではないかと思ったりもする。
〈完〉