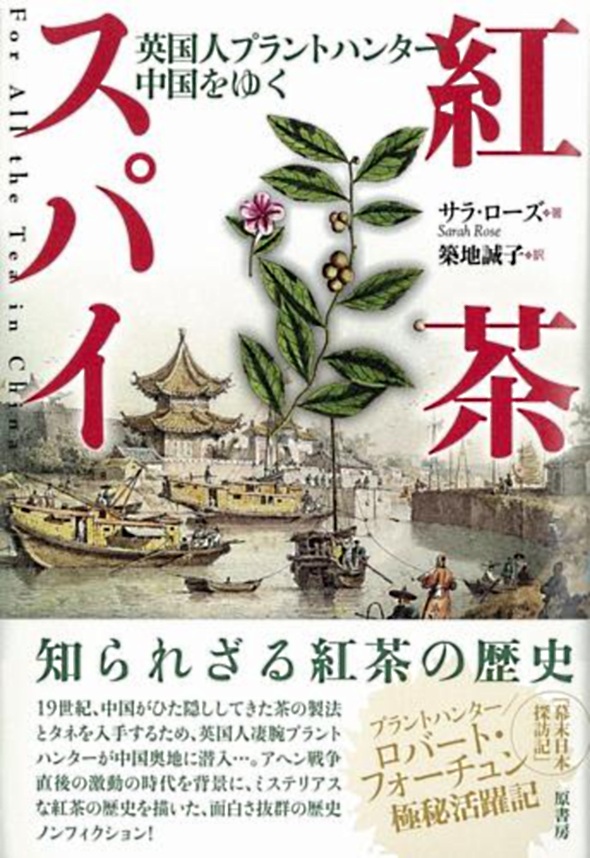手元に1990年の2月に撮影したレーの町並みの写真が2枚ある。そしてもう2枚は2012年の夏に撮ったもの。季節はもちろんのこと、レンズの画角やアングルは少し違うのだが、どちらもレーの町を見降ろす王宮脇からの眺めである。王宮は、1990年当時は廃墟といった状態で、内部はあちこち崩落していたため公開されていなかった。撮影したネガは紛失しており、すっかり退色してしまったポジをスキャンしたものだ。
レーの町 1990年
レーの町 2012年 レーの町の東端 1990年 レーの町の東端 2012年
レーの王宮入口 1990年 レーの王宮入口 2012年 レーの町の中心を成すメイン・バーザール界隈の大きな建物や政府機関等を除けば、大半の家屋は伝統的なラダック式の日干しレンガを積み上げた構造のものが大半であった。宿もそのような家屋に手を入れたようなものが多かったように記憶している。
レーのメイン・バーザール 1990年 レーのメイン・バーザール 2012年 レーの市内も主だった通りを除けば、大半は未舗装であったため、やたらと埃っぽかった記憶がある。他にもいろいろ撮っておけば良かったと思うのだが、フィルム時代であったため、低予算のバックパッカーにとっては、コスト面から一枚一枚がなかなか貴重であったため、今のように枚数を気にせずに撮りまくるようなことはできなかった。加えて、愛用していたニコンの機械式のカメラが故障したため、撮影数が少なかったということもある。
当時のティクセの寺院の画像もある。かなり荒廃した感じに写っているが、その頃は実際そういう具合であった。僧侶たちの多くが携帯電話を所持していたり、その中の若い人たちの中にはスマートフォンを手にしていたりするような時代が来るとは想像もできなかった。
ティクセ 1990年 ティクセ 2012年 今回のラダック訪問で、20年もの歳月が過ぎているので当然のことではあるが、レーや周辺の町並みの整備が進んだこと、主だった寺院その他の建築物が非常にいい状態にあることが印象的であった。やはりインドという国の経済が継続的に右肩上がりで推移していること、観光業もまた順調に振興していること等々の効果もあるのだろう。加えて、1990年当時には、外国人にとって完全に地域が、ILPを取得することにより訪問可能になっていることについて驚かされるとともに、大変嬉しく思った。電気を使えるのは午後7時から午後11時までというのは相変わらずであるし、夏季以外は陸路が閉ざされるという状況は変えようもないのだが。
電気はともかく、まさに夏季以外の厳しい気候やアクセスの面での不都合があるがゆえに、外部からの人口流入も限られていることも、ラダックらしさが保たれているひとつの要因に違いない。とりわけ北東インドのアッサム州やトリプラー州のように、隣接するベンガル州はもとより、ヒンディー・ベルト地帯からの移住者が多い地域と比較すると、その差は歴然としている。経済的な理由により、ラダック地域内での人口の移動は相当あるのかもしれないが。
地理・気候的に厳しい条件があるがゆえに、今後もラダックらしさが失われることはないのではないかと思われる。それとは表裏一体ということにもなるが、ラダックの今後については、「インドの中のJ&K州のラダック地域」としての位置付けではなく、ラダック独自の特別な扱いが必要ではないかと思うのである。それは、以前から要求のある州に格上げという行政区分上の事柄で片付くものではないように思う。
外部から訪れる人々があってこそ成り立つ観光業を除き、いまだにこれといった産業があるわけではない。しかしながら戦略的な要衝にあるため軍施設は多いので、これに関連した雇用やビジネスのチャンスは少なくない。だが電力は圧倒的に不足しているため、これを必要とする産業の育成は難しく、人口密度も少ないためマーケットとしての魅力も薄い。それでいながらも、限られた条件の中で日々やりくりしながら過ごしていく余裕はあるというところが興味深い。他者に従属しない気高さが感じられる。
蛇足ながら、個人的にはラダックでのヒンディーの通用度の高さには大変驚かされた。ヒンディー・ベルトとは、これほど地理的に離れた地域であり、民族的にも文化的にも大きな乖離があるにもかかわらず、農村のご婦人たちもごく当たり前に喋ることができる。J&K州の公用語がウルドゥーであるということもあるにしても、言語的にも文化的にも全く異質なコトバをこれほど広範囲に受容しているということは、ラダックの人々の柔軟さによるものであるとともに、中国を目の前にするインド最果ての地という地理条件によるものであろう。
インドにあって、インドではないとも言えるラダックについては、あまり多くを知らないのだが、極めて独自性の高いこの地域で、将来に渡って持続可能な発展とは、どのような形のものなのだろうか。