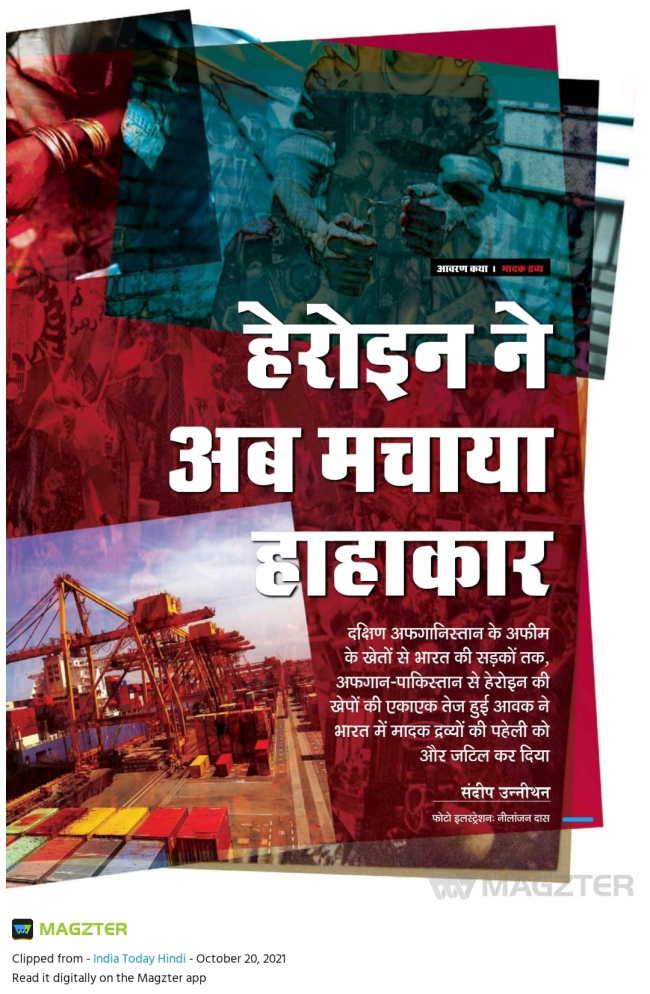ドラゴンフルーツ。こちらは白玉(中身が真っ赤な「赤玉」もある)だが、安定したあっさり、さっぱり感が心地よい。美味しいかと言えば、味わいはあんまりないように思うが、爽快感があり、食べていて気持ちが良い。濃厚な味わいと陶酔感を呼ぶドリアンの対極にあるように思う。これらが同時に店先に並ぶベトナムは、フルーツ環境としては、ライチーとマンゴーがマーケットにふんだんに供給される雨季入り前の酷暑期のインドに匹敵する幸福感があるに違いない。
ドリアンといえば、インドでもたしか南西沿岸地域で輸出用作物として栽培が始まるといえ報道を目にしたのはかなり前のこと。その後どうなったのだろう。ゴアでは野生種が自生しているというが、インドでは食べ物と認識されてこなかったのでマーケットに並ぶことはなかった。
また、スリランカでも山間部にはドリアンが自生だか栽培されているのか知らないが、沿道でイガイガの実を売る姿をチラホラ見かけたことはあるが、町のバーザールでは発見できなかった。南アジアもドリアンが生育できる環境のところがあるが、食文化の中にドリアンが占める位置はない。
しかしながらタイでもシンガポールでも現地在住のインド系の人たちがドリアンを楽しむ姿があるので、何かきっかけがあれば、定着していく余地はあるかもしれない。
今はカシミールやヒマーチャルの特産品となっているリンゴにしてみても、地場の固有種ではなく、外来で定着した果物。ドリアンは特有の香りと陶酔感があり、味わいの中に明らかに洋酒が仕込んであると思われる部分、そして卵黄を使っているとしか思えないコクがある。
これらについて、ヒンドゥーの人たちの中で厳格な人たちが「ピュアル・ヴェジ」と認めるかどうか。そもそも私自身は、この目でドリアン畑を見たことがないので、ドリアンは人工物に違いないという確信めいたものがある。
熟練のパティシエが卵黄、砂糖、ブランデーなどを使って丹念に創り上げていくのだ。ツナギに何を使っているのかは秘伝で、果実を口にしたときのムラのある繊維感とこれまた微妙な歯触りを出すには長年の経験が必要。だからドリアンは当たり外れが大きいのだ。
よって、ドリアンは言うまでもなく、「ノン・ヴェジ」だと信じている。