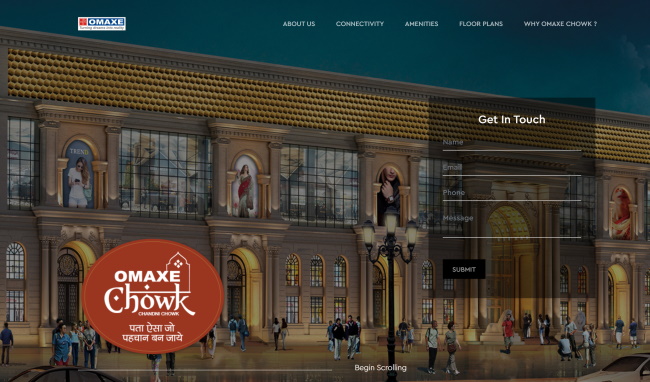インターネットが普及し始めた1990年代半ば、世界中でサイバーカフェなる「ネット屋」が続々オープン。どこも大いに賑わっていた。
それまでは、旅先で家族や友人と連絡を取り合うとすれば、郵便が主要な手段であった。どこの国でも大きな街の中央郵便局では「局留め」で封書、ハガキ、荷物などを期限付きで預かってくれていた(今でも制度上はあるかと思う)ので、そうしたところでは親しい人から手紙を受け取って笑顔の人、期待していた便りがなくて残念そうな人等々、さまざまだった。
電話という手段もあったが、いかんせん国際電話というものは目が飛び出るほど高かったので緊急の場合のみの手段であった。電話局で長時間待たされるものでもあった。そもそもこちらからはかけられるが、自前の番号を持っていないこちらに家族や友人がかけることはできない。
「コレクトコール」の制度を利用して、定期的に自身の安全を家族に伝えている若いドイツの女性に会ったことがある。数年前に欧州を一人旅していた兄が事件に巻き込まれて死亡するという不幸があり、両親は成人したばかりの子がひとりで旅行することを大変心配しており、毎週末にに欠かさず無事を知らせるという約束で旅行に出るとができたのだそうだ。両親の元にコレクトコールを依頼し、オペレーターが両親のどちらかに「娘さんがコレクトコールをかけたいと依頼しているが受けるか?」と質問して、両親は断ることになっているのだと言っていた。どうしても話をする必要がある場合はどうするのかと尋ねると、「緊急の際に名乗る名前が決めてある」とのこと。いつもの名前でかければ自分が無事であるという了解になっているのだというから、実に賢い「コレクトコールの利用方法」だと感心した。
手紙を出してもこちらから向こうまで届くのにかかる時間、故郷からこちらまで届くまでの時間は、国や地域にもよるが短くて数日、長くて半月あるいはそれ以上かかることもあり、ハガキなどでは伝えられる内容も限られていた。
ネットの時代入ってからは、連絡にかかる時間がゼロとなり、向こうがすぐに見て返信してくれれば、ものの数分で「元気そうでなりより」という連絡が入ってくるのだから、郵便でやりとりしていた時代とは比較にならない一足飛びの進歩だった。インターネットが普及し始めたばかりの低速な回線であっても、それはたいへんな驚きであったことは言うまでもない。
低速な回線といえば、その頃のインドの田舎ではネット屋が少なく、接続はとても遅かった。宿からわざわざオートリクシャーでネット屋まで行き、そこでウェブメールで自分のアカウントをなんとか開き、届いているメールに簡単な返信を書いて送信するだけで、軽く1時間かかってしまうようなことはザラであった。ログインするにも、受信するにも、送信するにも、じっと待っている必要があったのだ。
それでも当時は「たいへん便利な時代になった!」と感じていた。インドから日本その他どこにでも連絡をすることができるからだ。それだけではなく郵便のように「これから向かう先の中央郵便局」の局留めで送ってもらうわけではなく、目の前で開いている自分のメールアカウントで相手とメッセージをやりとりできるという双方向性は画期的だった。
やがてブロードバンドが浸透してくるころになると、あまたあるネット屋はいずれも「高速回線」を売りにするようになり、ネット屋で家族や友人たちとビデオチャットに興じている様子はよく見かけるようになった。
ネット屋が重宝されていたのはこのあたりまでだろうか。それまでは「有料サービス」であったホテル等でのWIFI接続は次々に無料化されていき、街中のカフェなどでも無料のWIFIサービスを提供するところが増えていき、有料のネット接続そのものを提供するネット屋は次第にジリ貧になっていく。
ネット屋の時代の終焉が決定的となったのは、スマートフォンの普及だ。初代iPhoneの登場した頃には端末もデータ通信料も高額であったが、アンドロイドOS搭載のスマートフォンの登場とともに利用者が急増していくにつれて端末価格も通信料も低廉化していく。
この流れの中で、誰もが掌の中にネット環境を持ち歩くようになっていったため、ネット屋はすっかり存在意義と顧客を失い、バーザールから姿を消していった。
 廃業したネット屋(バンコクにて)
廃業したネット屋(バンコクにて)
今から思えば何が仕込んであるかわかったものではない端末で、よくもまあ大切なIDとパスワードを入力してメールのチェックなどしていたものだと思うが、それも自前の端末とネット環境を持ち歩くことができる今だからこそ言えることだ。
こうしたものを求めるユーザーが爆発的に増加していくことを受けて、各国でデータ通信の分野で新規参入が相次ぎ、熾烈な競争を繰り広げた結果、旅行者のような一時滞在者でも安価に利用できるプリペイドプランが各国で普及した。インドもまたその中のひとつであることは言うまでもない。
今の時代、早朝でまだ暗い宿のベッドの中でメールをチェックして必要があれば返信し、階下に降りて開店したばかりの隣の食堂でトーストをかじりながら、長距離バスを予約し、続いてUBERを呼んでバススタンドまで行ってもらうというようなことが可能なのだから、ずいぶん便利になったものだと思う。バスが深夜近くになって目的地に到着するので泊るところが不安であれば、座席で揺られながら予約サイトでバススタンド近くの宿を確保できてしまう。
長期旅行者たちの旅のスタイルにも大きな変化を生んだ。ネット以前は仲良くなった相手と別れるときは文字どおり「今生の別れ」みたいなもので、住所と実家の電話番号を交換して「また機会があれば会おう」なんて言っていたが、ネット時代に入るとメルアド交換でいつでも簡単に連絡できるようになった。
そしてスマホとSNSの普及した後は、「佐藤君は今日プリーに着いた」とか「ジャニスは明日イギリスに帰国するみたい」といったことがオンタイムで共有されるようになったし、SNSの通話機能でごく当たり前に会話する先は自国であったり、旅先で会ってすでに他国に移動している相手だったりする。
そんな具合なので、旅行先で待ち合わせて再会というのもごく当たり前のものとなっている。ネット以前も旅先で再開というシーンはしばしばあったとはいえ、それらは偶然の産物であり、予定しての行動ではなかったため、本質的に異なるものであった。
デジタルの時代になってからは、どんなサービスや利便さも、すぐに陳腐化してしまうので、現在の「たいへん便利な時代」も5年後、10年後から見ると、「あの頃はあんなに面倒くさかった」とか「まだこんなことをしていた」と思い出すことだろう。
もっともその「進歩」を見る前に、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが収束を見ないことには、そうした旅行の景色は見えてこないわけだが。