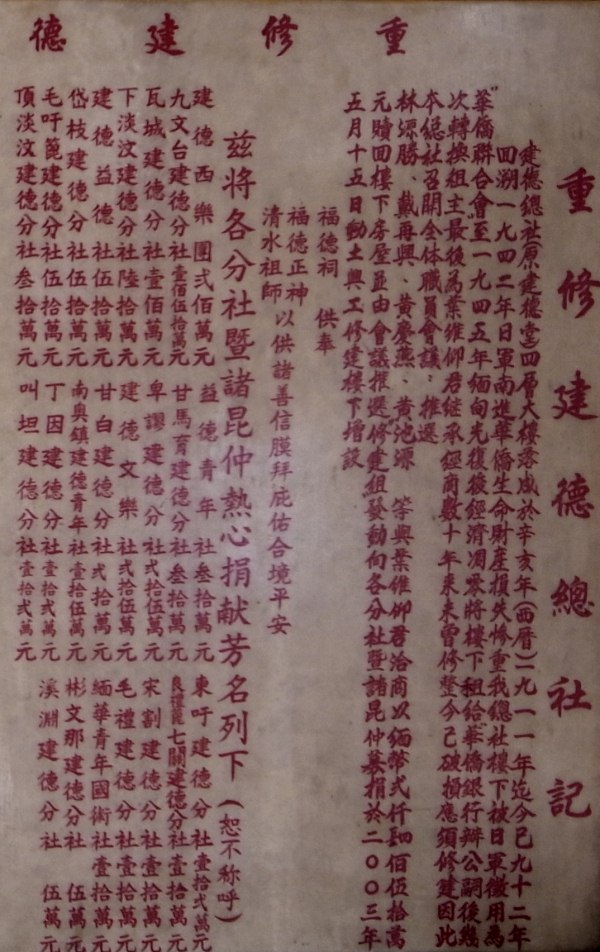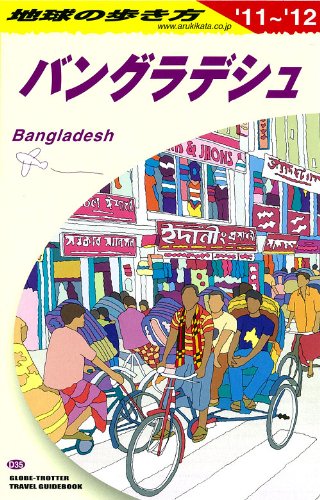
日本の出版社から出ているバーングラーデーシュのガイドブックといえば、旅行人の『ウルトラガイド バングラデシュ』くらいかと思っていたが、昨年10月に地球の歩き方から『バングラデシュ』が出ていることに今さらながら気がついた。
近年、日本からアパレル産業を中心に企業の進出が盛んになってきているとともに、同国首都ダーカーに旅行代理店H.I.S.が支店をオープンさせるなど、観光の分野でも一部で注目を集めるようになってきているようだ。
すぐ隣に偉大なインドがあるため、観光地としてクロースアップされる機会が少なく、存在すら霞んでしまう観のある同国だが、なかなかどうして見どころは豊富である。
もちろんここがインドの一部であれば訪れる人は今よりも多かったことだろう。またインドとの間のアクセスは空路・陸路ともに本数は多く、両国の人々以外の第三国の人間である私たちが越えることのできる国境も複数あるため、行き来は決して不便というわけではない。
だがインドのヴィザに近年導入された『2ケ月ルール』のため、インド東部に来たところで『ふと思い立ってバーングラーデーシュに行く』ことが難しくなってしまっている。インド入国前のヴィザ申請の時点で、隣国への出入国を決めておかなくてはならなくなったからだ。
だからといって西ベンガル、アッサムその他インド東部まで来て、この実り豊かな麗しの大地を訪れないというのはもったいない話だ。
インドでも西ベンガル州で親日家、知日家と出会う機会は少なくないが、ことバーングラーデーシュにおいては、日本のバブル時代に出稼ぎに行った経験のある人々が多いこと、日本のODAその他の積極的な援助活動のためもあってか、日本という国に対して好感を抱いてくれている人たちがとても多いようだ。
それはともかく、歴史的にも地理的にも、『インド東部』の一角を成してきた『ベンガル地方』の東部地域だ。南側に開けた海岸線を除き、西・北・東の三方を東インド各州に囲まれ、本来ならばこれらのエリアとの往来の要衝であったはずでもある。
またこの国の将来的な発展のためには、圧倒的に巨大な隣国インドとの活発な交流が欠かせない。同時にインドにとっても、人口1億5千万超という巨大な市場は魅力的だし、この国の背後にあるインド北東諸州の安定的な発展のためには、ベンガル東部を占めるこの国との良好な関係が不可欠である。もちろん今でも両国間の人やモノの行き来は盛んであるのだが、それぞれの国内事情もあり、決して相思相愛の仲というわけではない。
イスラームやヒンドゥーの様々なテラコッタ建築、仏蹟、少数民族の居住地域、マングローブ等々、数々の魅力的な観光資源を有しながらも、知名度が低く訪れる人も多くない現況は、『インド世界』にありながらも『インド国内ではない』 がゆえのことだ。
日本語のガイドブックが出たからといって、訪問者が急増するとは思えないものの、やはり何かのきっかけにはなるはず。今後、必ずや様々な方面で『バーングラーデーシュのファン』が少しずつ増えてくるように思われる。