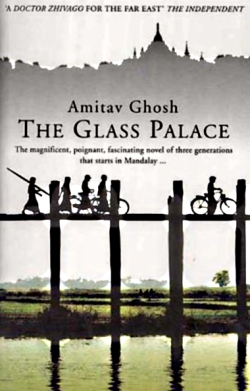活字中毒・・・というわけでもないが、いつも手元に何かしら読み物がないと落ち着かない。小説でもノンフィクションでもいいのだが。加えて日々の出来事に目を通さないと何だかスッキリしない。日常の暮らしの中でも旅行先でも目覚めてから一番にすることといえば、新聞を広げながら朝食を取ること。
朝起きてすぐに手に入らなければ、近くのマーケットに散歩がてら出かけて新聞売りを見つける。あるいは早い時間帯から鉄道、バスその他で移動する際には、駅やバススタンドで、まず最初に買うのはスナック類ではなく新聞だ。
全国規模のメディアで広大なインドの政治、社会、経済等の様々なニュースを目にするとともに、ローカルな新聞も押さえておきたい。広域紙には出ない地元の出来事がいろいろ掲載されているので、数日間読み続けると今そこで話題になっているらしいことについておおよそ検討がつくようになってくる。
往々にして退屈な記事が多いことも事実だが、例えばモンスーン期に激しい雨が降り続いているときにヒマーラヤ地方を旅行する際、あるいは付近で洪水その他の天変地異が起きている場合など、参考になることはとても多い。
また政治関係も同様だ。アッサム等の北東州を訪れた際には、ULFA (United Liberation Front of Asom)やNNC(Naga National Council)をはじめとする各地の分離活動を行う組織にかかわる記事をいろいろ目にすることができて興味深いものがあった。北東州関係については、コールカーターあたりであっても、地理的に北東州に近いこともあり、そのあたりに関するニュースはその他の地域よりも格段に豊富だ。
南インド、とりわけタミルナードゥやケーララあたりでは、新聞をはじめとするヒンディーによる印刷物はほとんど見当たらないものの、都市圏以外でも英字紙が豊富なのはありがたい。だいぶ前のことになるが、2005年12月のスマトラ沖地震による津波災害の際にちょうど南インドの沿岸部にいたため、いろいろ参考になった。
各地でメディアの活動が盛んであることは言うまでもないが、報道の自由度が高く周辺各国とは大きな開きがある。人々の『知る権利』が尊重されているからこそ『読むに値する新聞』が豊富であることはありがたい。
もちろん新聞といっても様々なので、報道の質についてはいろいろあり、それは報じる側、読み手側の双方のスタンス、加えてこう言っては大変失礼かと思うが、それらの質の問題もあることは否定できないのだが。もちろんそれこれは読み手自身がメディアを選択すればいい。
報道の自由は必ずしも手放しで称賛できるものとは限らず、報道機関とて大きな資本によるいわば『営利事業』であるがゆえに、ニュースの『売り手』の事情が紙面に現れることがあってもおかしくない。また近年の民間放送局による視聴率を意識してのセンセーショナルな報道(興味本位の犯罪特集番組、ヤラセや捏造ニュース)や視聴者からの携帯電話のSMSによる人気投票的なマーケティング手法等、ちょっと良識を疑いたくなる面も否定できない。
これを玉石混淆とまで言うつもりはないが、そうした様々なソースから流れるニュースを人々が個々の意志と良識で取捨選択できる状況は健全であると私は思う。
ともかく新聞をはじめとするメディアにより、人々は国、地域や社会の動きを知り、自身の頭でそれを理解する。私たち外国人も同様にそれにあずかることができる。これはとても大切なことだ。ミャンマーや中国のようにメディアやネット環境にも大きな制約のある国々と比べるのは極端に過ぎるかもしれないが、インドという世界最大の民主主義システムの根幹にあるのは、活発で自由度がとても高い報道の存在であるといって間違いないだろう。
政府により、報道に関する制約が厳格な国々以外に、現地のアンダーワールドな部分からの圧力により、メディア自身が事前に『自己検閲』をしてしまう国もある。たとえばメキシコのように政府と拮抗する勢力である麻薬カルテルによる報復への恐れから、これらの組織に関する分野は報じられないようになっているようだ。既存のメディアでは伝えられない『空白地帯』を一人の匿名の大学生(・・・ということになっている)によるBLOG DEL NARCOというブログが情報を流しているという状況は決して肯定できるものではないだろう。
ブログ運営者のもとに、多数の発信者たちから連日大量の情報が写真や動画とともに届けられ、これらを編集したり裏を取ったりすることなく、そのまま掲載しているとのことだ。血なまぐさい内容が大半で、凄惨な画像も含まれている。
すべてスペイン語で書かれているが、ブラウザにGoogleツールバーがインストールしてあれば、日本語に自動翻訳したものを読むことができる。いささかぎこちない和文となるものの、おおよその内容を掴むことはできるだろう。
もちろんインドを含めた各国のメディアにおいても、報道する側の身の安全という点から世の中に伝えることが難しい事柄は存在するであろうことは否定できないし、もちろん日本もその例外ではないのだが、こうした出所のよくわからないソースによる情報を日々綴ったブログが、本来それらを伝えるべき報道機関に取って代わってしまうという状況はとても危うい。
話はインドに戻る。
報道の本質にかかわる事柄ではないのだが、インドの外にある国々からしてみると、現地の各メディアによる各分野における英語によるニュース配信を大量に入手できることについても大きなメリットがある。とりわけインターネットが普及してからは、その感がさらに強まっている。
全国ニュースからかなりローカルなものまで、各地のメディアによる立ち位置の異なるソースから手に入れることができるという点で、とりわけ非英語圏の国々に比べて非常に『オープンソースな国』という印象を与えることだろう。
世にいう『グローバル化』とともにインターネットによる情報通信の普及と進化の過程の中で、これまで以上に英語が突出した存在感を示すようになっていることから『英語支配』の趨勢に対して主に非英語圏から危惧する声が上がっているが、インド自身はその英語による豊富な情報発信量から得ているメリットについては計り知れないものがあると思われる。
もちろん英語による情報のみでインドという国を理解できるとは思えないし、カバーされる範囲にも限界がある。それでも英語という広く普遍性を持つ言語によるソースが非常に豊富であるという点から、私たち外国人にとっても非常に利するものは大きいといえるだろう。報道の自由度の高さと合わせて、インドのメディアは自国内のみならず国外に対しても、非常に公益性が高いとも言えるのではないだろうか。