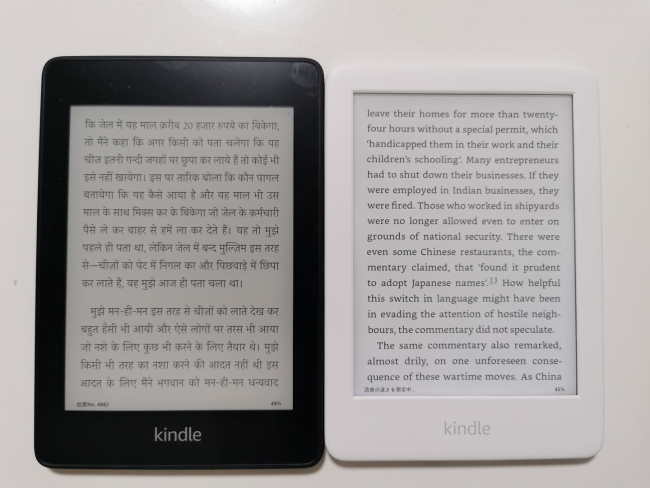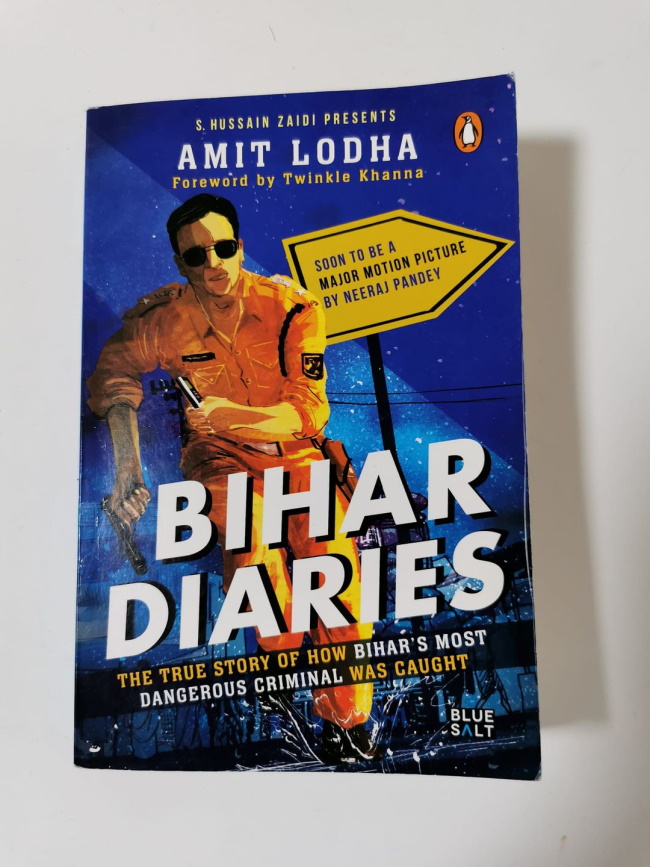これまで愛用していたタブレットが、とても鈍くなり、突然アプリが落ちたり、画面はフリーズしていないのに、操作ができなくなったり、指紋認証あるいはPINでの画面ロック解除ができなくなったりと、ダメになってきた。そろそろ後継機必要と、いろいろ検討。
当初は似たようなタブレットを購入するつりだったが、タブレットの近くの売り場では、画面の見た目はAndroidとほぼ同じASUS製の10.5インチのChromebook (CM300DV)が展示されていた。
タブレットとPCの中間みたいな位置づけとのこと。アプリはGoogleストア、あるいはChromebookストアからアプリを入れる。感覚はAndroidのタブレットと変わらない。縦置きしても画面を反転できないモデルもあるので、購入時にこのあたりは要確認である。Android端末で利用できても、Chomebook端末では使えないアプリも一部あるようだが、そのあたりは目をつぶることにする。
それ以外に異なるのは、最初から当然の装備としてキーボードが付いていること。Androidのタブレットもそうした装備の用意がある機種もあるが、それらに出来の良くない日本語IMEを入れて使うのと異なり、Chromebookでは、普段使っているPCと同じ感じで使えるのが良い。オフィスソフトの代わりにGoogleのドキュメントを使えばいいし、タブレット兼簡易版PCという具合か。キーボードは外して持ち歩いてもいいし、付けたままでも薄いので邪魔というほどでもない。
旅行に持参する端末としても、なかなか良いように思う。