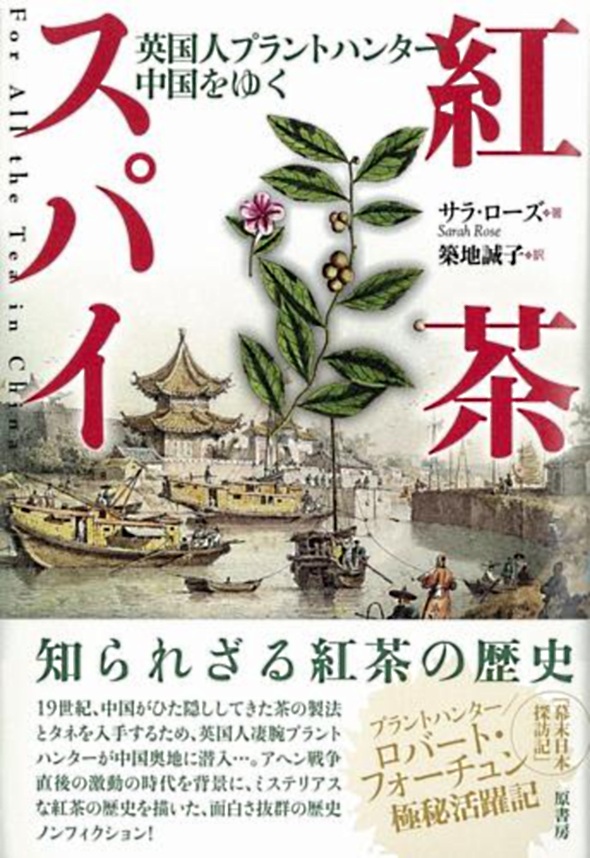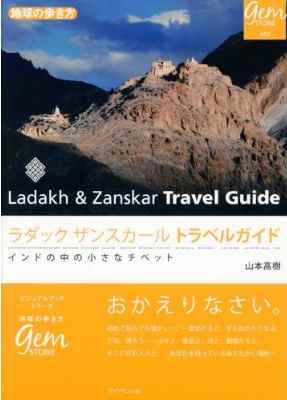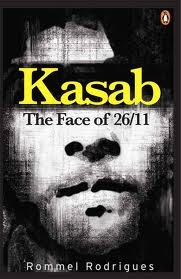中国からインドに茶の木と栽培法を伝えた功績で知られる植物学者ロバート・フォーチュンの試行錯誤を軸に描かれた、紅茶をめぐるノンフィクション作品。
イギリス東インド会社の依頼により3度中国に渡った彼だが、その中で2度目の中国行き(1948年~1951年)での任務は、当時の中国において門外不出であった茶の秘密を得ること。茶の木と栽培技術を密かにインドに移すことであった。
折しも、ウォードの箱の発明により、植物の長期間に及ぶ輸送が可能となっていたという背景がある。観賞用としてシダやラン、工業用の作物としてのゴムの木等々の苗の大陸間での移送が可能となり、当時海外植民地を持っていた列強国にとって、新たな富の創造を可能とするものであった。
インドに持ち込まれた茶の木は、当初U.P.のサハラーンプルの植物園で栽培されていたが、当時スィッキム王国から割譲されたばかりであったダージリンが、茶の生育には天恵といえる好適地であったことにより、質・両ともに本場中国を凌ぐ茶の生産の一大拠点として発展していくことになる。
1957年に発生したインド大反乱により、イギリス東インド会社がインドで得ていた特権は剥奪され、本国の君主が英領インド帝国の皇帝となることにより、それまで250年間もの間に亜大陸の貿易港の商館での取り引きから、この地域のほぼ全土を掌握するに至っていたこの「会社」による支配は終焉することになったが、その「会社」がこの地に残した最後の大きな遺産のひとつが茶の生産であった。
インドでの茶の栽培の進展は、それまでの茶葉の貿易事情に大きな変革をもたらし、茶をたしなむ習慣の大衆化を推し進めることにもなった。イギリスにおける磁器産業の発展も、まさにこうした茶器需要あってのことでもある。
フォーチュンは、日本との縁も少なからずあり、東インド会社とは無関係な仕事で1860年から1862年まで中国と日本に滞在している。植物学者として、またプラント・ハンターとしても当時第一級の知識と腕前を持つ人物であったが、同時にビジネスマンとしての才覚も人並み外れたものがあったようで、この時期の極東滞在で大きな財産を築いたとされる。
この本のページをめくりながら、休日の午後のひとときを過ごしてみると、手にしたカップの紅茶の味わいがことさら愛おしいものとなることだろう。
書名 : 紅茶スパイ
著者 : サラ・ローズ
訳者 : 築地誠子
出版社 : 原書房
ISBN-10 : 4562047577
ISBN-13 : 978-4562047574