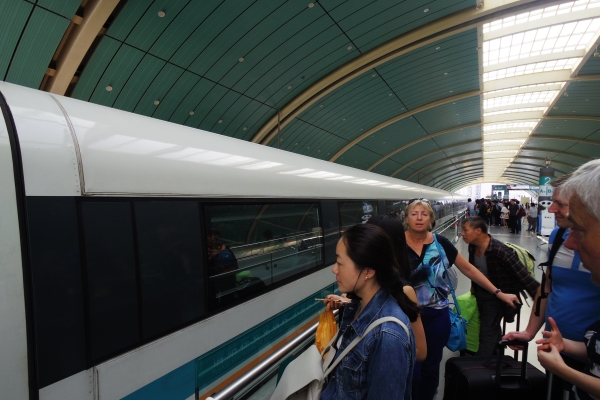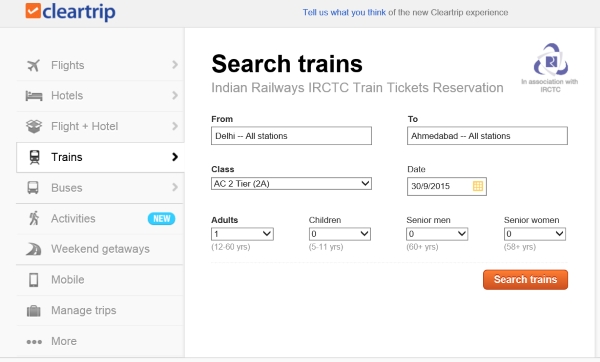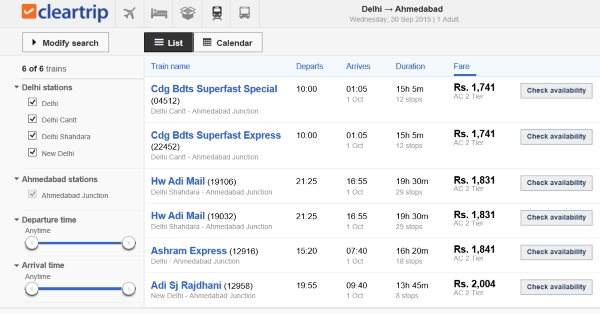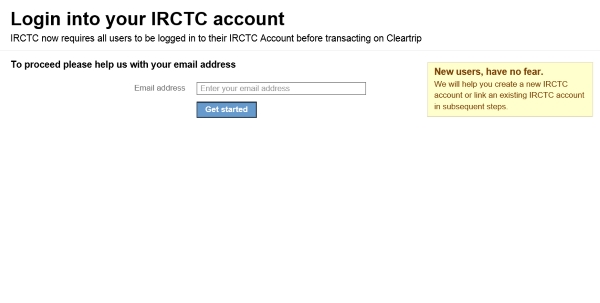宿から見て、鉄道駅がすぐ裏手なので、列車の汽笛がよく聞こえてきて風情がある。英領期には旧藩王国でも藩王国立の鉄道が敷設されたりなどしていた。開明的な君主が先端技術を導入したということもあろうが、これらの路線がイギリス当局により、藩王国の大きな負担により建設させたという部分も多いにあると思う。
こうした鉄道の多くはメーターゲージであり、各地にあった鉄道会社が独立後に統合されてインド国鉄となった後、ブロードゲージの幹線と軌道幅の相違から直接乗り入れできない不便を長いこと甘受してきたわけだが、同時に着々と全国路線のブロードゲージ化の事業は進行していき、近年はほぼ完成したといえる。ジャイサルメール、ビカネール、シェーカーワティーなどにもデリーからブロードゲージの直通列車が走るようになっている。シェーカーワティー地域においては、デリーからメーターゲージでジュンジュヌー経由でジャイプルに走っていたものだが、この路線も近年ブロードゲージ化された。ジュンジュヌーはまだメーターゲージのため、路線から外れることとなり、各駅停車の路線のみが残っている。
統合といえば国鉄だけではない。藩王国が割拠し、イギリスが間接統治を行なった旧ラージプータナ地域だが、インド独立後は行政組織も新生のインド共和国と統合させられることになったことから、旧藩王国により役人たちの明暗は分かれたのではないだろうか。有力な旧藩の役人たちはどんどん上のポストを占領して、そのラインで人事が進んでいく、あるいは冷や飯を食わされることになった旧藩の役人たちは不満たらたら・・・。そんな今の会社社会でもよくある悲喜こもごもが、ここでも展開されていったりしたのではなかろうか、と想像している。
〈続く〉