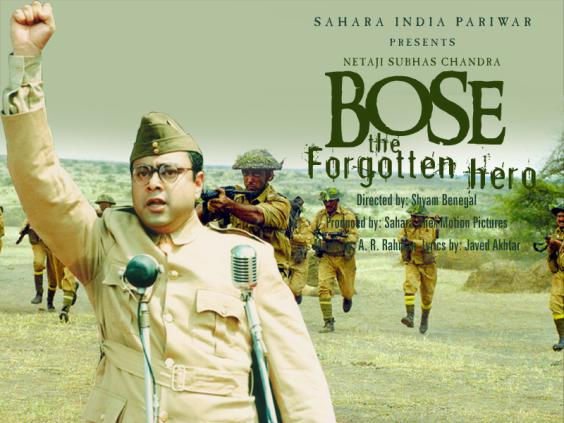デリーのラームリーラー・マイダーンにおいて、社会活動家アンナー・ハザーレーの断食が11日目に入っている。ジャンロークパール法案をめぐる一連の動きが予断を許さない状況になっている中、インド政治がらみながらもこれとは全く関係の無い事柄について触れるのはいささか気が引けるのだが、こちらも個人的にとても気になる人物である。

今月初めのことであったが、マハーラーシュトラ州のMNS (マハーラーシュトラ・ナウニルマーン・セーナー)の党首、ラージ・タークレーがグジャラート州首相のナレーンドラ・モーディーの招きにより9日間グジャラート州を訪れた際、メディアの取材に応じているが、その中でヒンディーによるインタヴューが放送されたこと自体が話題になっていた。
मोदी के गढ़ में हिंदी भाषी बने राज ठाकरे (AAJTAK)
元々、彼は極端な地元のマラーティー主義と、州外からやってきて就労する人たち、とりわけ北インドのヒンディー・ベルト地帯から来た人たちに対する排斥を主張し、暴力的な示威行動等も辞さない政党、シヴ・セーナーの幹部で、党創設者であるバール・タークレーの甥であり、バール・タークレーの息子で現在は党を率いているウッダヴ・タークレーのいとこである。シヴ・セーナーの中核にあった人物だ。
しかしバール・タークレーの高齢化とそれに伴う健康不安から、指導部の世代交代が行なわれる中での党内のお家騒動の中で、一時期州与党にあった時期にマハーラーシュトラ州首相まで務めたことがある大物ナーラーヤン・ラーネーが党を追われて国民会議派に加わるというサプライズな出来事があったが、その年末にはウッダヴ・タークレーとほぼ同格の立場にあったラージ・タークレー自身が同党と袂を分かつという大きな出来事があった。
翌年3月にラージ・タークレーは、シヴ・セーナー時代の取り巻きを引き連れて現在のMNSを結党している。党がシヴ・セーナーとその分家に当たるMNSに分かれたことにより、相対的にシヴ・セーナーの社会的影響力が減じることに繋がったようだ。
2003年7月下旬にムンバイー市内で起きた市バスの爆破テロに抗議して実施したムンバイー・バンドの際にはちょうどムンバイーに居合わせて、彼らの実行力(強制力)の凄まじさに驚かされたものだ。その模様については以下をご参照願いたい。
MUMBAI BANDH !! 大都会ムンバイーがフリーズした日 1
MUMBAI BANDH !! 大都会ムンバイーがフリーズした日 2
MUMBAI BANDH !! 大都会ムンバイーがフリーズした日 3
だがその3年後、2006年7月にムンバイーでシヴ・セーナーが再度試みたバンドは失敗に終わったのは、党が割れたことによる弱体化の表れだろう。その後彼らの地元であるインド最大の商都で、こうした規模のバンドは実行されていない。
ただし地域主義とともに反共産主義(地元ムンバイーの財界の支援を受けて、60年代後半から70年代にかけて共産党勢力と激しく対立し、共産党傘下の労働運動の影響力を弱体化させた経緯がある)を掲げて1966年に発足したシヴ・セーナーは、時代が下るとともに、マハーラーシュトラ州という地域を越えて大衆にアピールできるヒンドゥー至上主義に傾向してきた経緯がある。

中央政界やいくつかの他州の議会にも議席を持ち、国内各地に咆哮するトラのシンボルマークを掲げた支部が存在する。国外においても、彼らの支部というわけではないが、1999年にネパール・シヴ・セーナーという友党が発足している。
そんなことから、ときに彼らの地元のマハーラーシュトラ州の外で徹底したバンドを決行することもある。2006年7月下旬にはウッタラーカンドの州都デヘラドゥーンでもシヴ・セーナーによる『ラージダーニー・バンド』が決行された。
事の良し悪しはさておき、デヘラドゥーンの街の規模はムンバイーとは比較にならないほど小さいとはいえ、彼らのホームグラウンドから遠く離れたところにありながらも、見事な(・・・という言葉は適切ではないものの、パーフェクトなバンドであった)統率力で州都の機能を丸一日停止させていた。この日もたまたまその場に居合わせたため、『達人たちのバンド1』及び『達人たちのバンド2』と題した記事をアップしたことがある。
<続く>