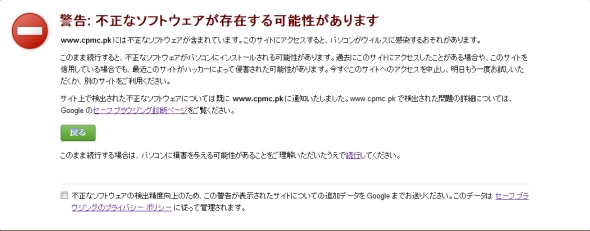バーングラーデーシュでのグラーミーン・バンクによる取り組みから世界的に注目されるようになったマイクロ・クレジット。通常、商業銀行から融資の利用ができず担保も持たない人々のグループに対する少額融資であり、返済についてはそのグループ全体が責任を負うという仕組みだ。経済的に困窮している層、とりわけ女性たちの経済・社会的地位向上のための役割が評価されている。
マイクロ・クレジットの代表格と言えるグラーミーン・バンクがアメリカに進出し、グラーミーン・アメリカを設立したのは2008年。当初はいろいろ不利な予想もあったが、現在までの4年間で着実に実績を上げているようだ。
滝川クリステル×ムハマド・ユヌス(ウェブゲーテ)
米国市民の間での経済格差について、よく「米国の黒人の寿命はスリランカと同程度である」ということが言われる。国民皆保険制度がなく、医療費が私たちから見れば法外なまでに高額なものとなりがちなことから、定収入のある勤め人でも大病を患った結果、自己破産という例はよくあるようだ。ましてや経済的に不利な境遇下にあるマイノリティの人たちともなれば、必要なときに充分な診療を受ける機会を逃してしまうということは決して想像に難くない。
だが、具体的な数字を提示することなく「スリランカ並み」という表現には、かなり恣意的なものを感じずにはいられない。このあたりの事情をあまり知らない人がそれを耳にすると、『とんでもなく短命』であるような印象を受けることを画策しているはずだからである。国連の統計によると、2005年から2010年の間のスリランカの平均寿命(74.25歳)は突出して高く、南アジア地域の平均の64.48歳を10歳近く上回る。ちなみにインド(64.19歳)は、ちょうどその平均値あたりにいる。
世界の平均寿命 (United Nations Population Division)
平均寿命73~74歳程度の国々はといえば、中東やアジアでは、サウジアラビア(73.13歳)、バハレーン(74.60歳)、タイ(73.56歳)、欧州ではルーマニア(73.16歳)、ハンガリー(73.64歳)、エストニア(73.91歳)あたりが挙げられる。日本では何故か長寿のイメージがあるブルガリア(72.71歳)、経済成長著しい中国(72.71歳)と比較しても、実はスリランカの数字はなかなか立派だ。豊かな産油国、東ヨーロッパと同水準なのだ。
予備知識無しで、「アメリカの黒人の寿命はスリランカ並みだ」と言われると、いささかショックを受けるかもしれないが、これを「金満の産油国並みだ」と言い換えたら、どんな印象を受けるだろうか。
国情の異なる国々の寿命を平たく慣らした世界平均(67.88歳)はあまり意味のないものかもしれない。だが、あらゆる面においてはるか前を邁進しているはずのアメリカ(77.97歳)の平均寿命が、自分たちの国との間のあまりに大きな経済格差のあるアメリカの平均寿命が、自分たちのそれとの差が3歳強しかないことについて、スリランカの人たちは不思議に思うだろう。
アメリカにおけるバーングラーデーシュ発のマイクロクレジットの成功、アメリカの黒人がとりわけ短命であるという一種の都市伝説の類など、先進国と途上国という色分けを取り払って社会を眺めてみると、世の中でいろいろ興味深いものが見えてきそうだ。