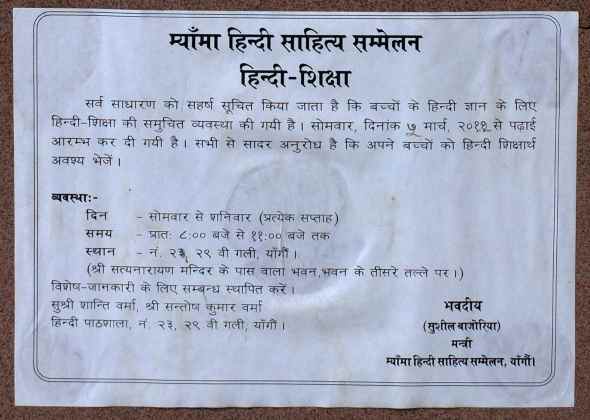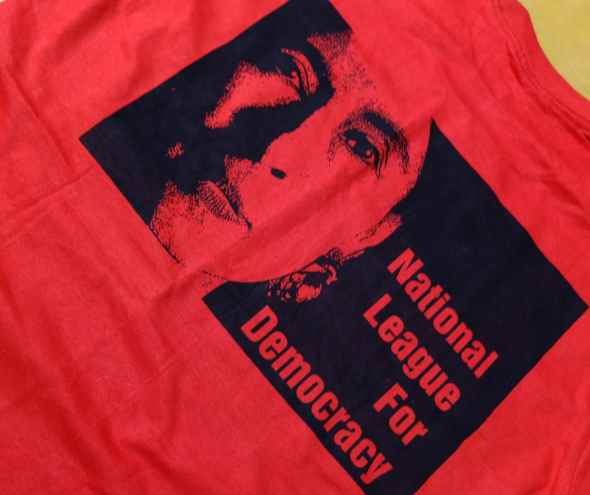先日述べたサティヤナーラーヤン寺と同じく29th Streetにジャイナ教寺院もある。こちらは信徒である年配のご兄弟が管理人をしている。一人はこの寺院を管理するトラストのプレジデント、もう一人はセクレタリーという形だが、同時にここのプージャーリーでもある
お二人の話によると、ヤンゴンにて最盛期にはジャイナ教徒の人口は5千人を数えたという。だが今残っているのは二家族だけで、彼らはそのうちの一つであるとのことだ。寺院はコロニアルな建物に入っており、地上階はトラストの事務所、セカンド・フロアーが寺となっている。ファースト・フロアーも昔は祭壇があったとのことだが、今では使われていない。
すでにほとんどのジャイナ教徒がこの国を去っているため、参拝客はほとんどいないそうだが、ときおりプージャーに参加するネパール人があり、いたく感激してくれるとのこと。しばらく事務所で話を聞いていたが、「さて、そろそろプージャーの時間ですよ!」と上階にある寺院へと招かれた。

長い白布を左肩から斜めがけに付けてもらい、神殿正面に立ち、真鍮のお盆に灯明を載せたもの(火の数が多いものと少ないものと二種類あり、プージャーの間の節目ごとにセクレタリー氏が取り替えてくれる)を抱えて時計回り動かす。セクレタリーの人が朗誦するマントラを耳にしながら、感激がこみ上げてくる。これまでインドの寺院ではプージャーを背後から見物したこことは幾多あっても、こうした形で主体的な形で参加させてもらったことはなかった。しかもジャイナ教寺院で!

事務所があるグラウンドフロアーとこの階との中間階、つまりファースト・フロアーもかつて寺であったが、今では使われることもなく、備品はすべて処分してしまったとのことだ。それでも奥の壁のニッチには、マハーヴィールの足跡のイメージがあった。
この地に残る信徒は二家族のみということからも、まさに風前の灯といった具合のようだ。ご兄弟には複数の子供たちがいるそうだが、特にこの寺に関わりを持ってはいないとのこと。「若い世代は物の考え方など違いますからねぇ・・・」と、少々諦めている様子。だがその割には、ずいぶん綺麗に保持されていることには驚いた。国外からの援助でもあるのだろうか。
「私どもの寺には150年の歴史があります」というご兄弟の言葉が本当であれば、第二次英緬戦争により、イギリスがヤンゴンを含む下ビルマを占領してから10年ほど後には、この寺院が建立されたことになる。多少の誇張が含まれているであろうことを差し引いても、19世紀末近くにはすでに存在していたことと思われる。この寺院は、ヤンゴンにおける「インド人史」の変遷を、つぶさに目の当りにしてきたことだろう。