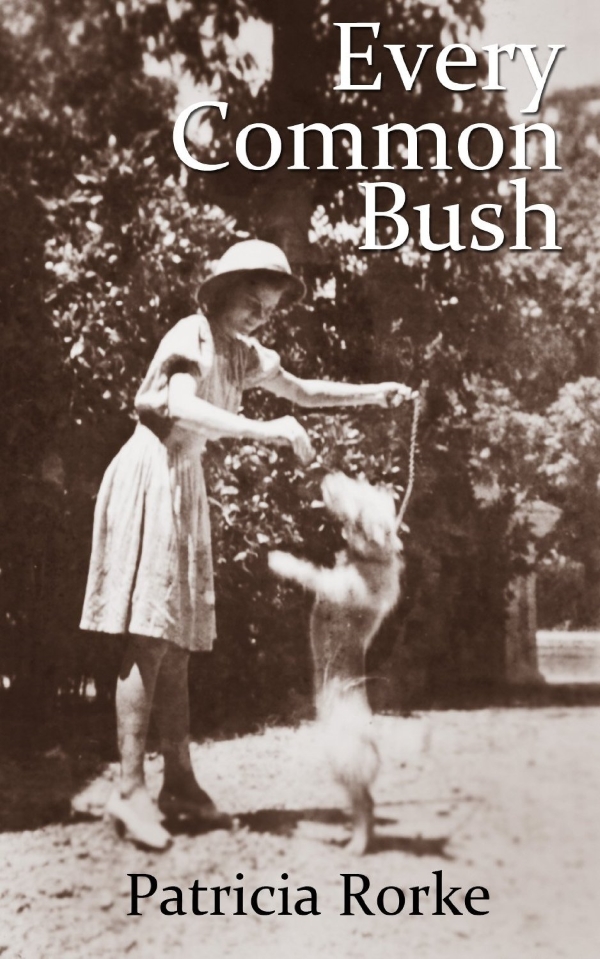著者である主人公の女性、パトリシア自身の英領ビルマでの生活の回顧録。彼女は1923年にラングーンで生まれて、日本軍の侵攻により1942年にインドに脱出するまで、ビルマで暮らしている。
彼女の先祖は、1840年代に軍人として赴任した初代(1857年のインド大反乱の際、アラーハーバードで死亡)とその妻、彼らに伴われて渡ってきた二代目となる子供たちがインドに根を下ろした。インドに暮らしてきた家族がビルマに移住したのは主人公の親の代であったようだ。主人公は本国から離れてアジアに移住した家系の五代目であり、植民地で暮らす最後の世代となる。
彼女の父親は自動車整備工。やがて企業して自らの自動車販売会社を持つようになり、順風満帆な生活を送るが、いつしか事業が不振に陥ってしまう。仕事に行き詰った結果、行政関係の仕事に就くが、独立運動とともに社会不安が高まる中、身の危険を感じて運輸関係の民間企業に転職。
第二次大戦開始による暗雲はアジアにも着実に影響を及ぼし、日本による真珠湾攻撃のニュースはビルマに暮らす主人公やその家族たちの生活にも暗い影を落とすようになる。
父は、勤務する運送会社がビルマから中国に至る「援蒋ルート」で軍需物資を運搬するという危険な業務に従事するようになるとともに、子供たちはビルマ中部のシャン高原にあるヒルステーション、メイミョーに疎開。
1942年、ラングーンに侵攻した日本軍はまもなくビルマ中部以北にも進撃を続ける中、まだ任務から離れることができない父親よりも一足早くインドに脱出。飛行機でチッタゴン、船でカルカッタ、そして鉄道でデヘラドゥーンへと向かい、主人公はしばらく看護婦として勤務することになる。
すでにビルマから外に出るフライトが無くなってしまった父親は、仲間たちとビルマからインド北東部を経て逃れる決断をしなくてはならなくなってしまう。
道中、命を落とす仲間たちも出る中、なんとかインドにたどり着くことができた父は家族と再会。家族はボンベイを経て、バンガロールに落ち着くこととなった。
作品の前半から中盤にかけては、主人公のどかな子供時代と家の中での出来事、彼ら家族を取り巻く人々の平穏な日常と在緬イギリス人たちや地元の人々の様子が描かれている。幼い子供だった主人公が成長していくとともに、植民地ビルマで暮らしていた様々な人たちとの付き合いも深まり、家や学校の外の社会に対する観察力が深まっていく。青春時代を迎えた主人公が、第二次世界大戦の戦況やビルマの独立運動の盛り上がりなどに対して、冷静に観察していた様子がうかがえる。
植民地在住のイギリス人とはいえ、ワーキングクラス出身で、5世代に渡ってインド・ビルマに在住。決して特権階級などではない主人公たちは、当時のラングーンの社会各層との繋がりは深く、そうした中で巧く世渡りをしていくたくましさを持っていたようだ。家庭内での英語以外に、ビルマ語やヒンドゥスターニー語(現在よりもインド系の人口が占める割合が高かった)をごく当たり前に使用する多言語・多文化環境にあったようだ。
バンガロールに落ち着いたあたりでストーリーは終わる。その後まもなくインドは独立を迎えることになるが、パトリシアとその家族たちはその後どうなったのだろうか、と少々気になるが、おそらく他の多くの英領インド在住のイギリス人たちがそうであったように、英国に「移住」あるいは第三国に転出し、その後は大過なく暮らしていたがゆえに、こうした本を出版することになったのだろう。
植民地末期の生活史として貴重な一冊であるが、amazonから手軽なkindle版が出ているので、多少なりとも関心があればご一読をお勧めしたい。