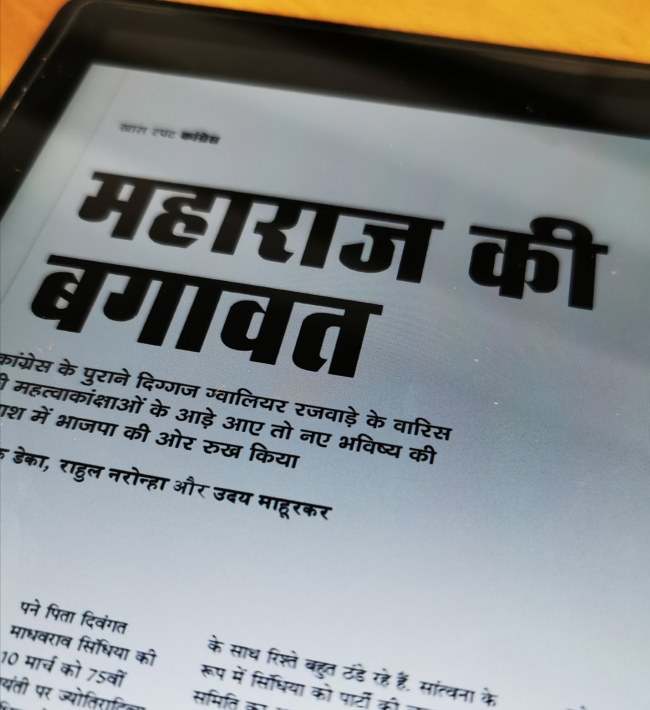1月14日からセイシェル共和国は「新型コロナワクチン接種済」の観光客を検疫等の制限なしで受け入れることを開始した最初の国となったそうだ。
One island welcomes all vaccinated travelers — but some may want to wait (CNBC)
現在は同様の措置をネパールも検討中とのことで、これと同様の措置により接種済の証明書を持つ人に対してはPCR検査も隔離もまったく求めず、アライバルビザの復活も併せて検討中であるという。
Nepal to allow unrestricted entry to vaccinated tourists (Kahmandu Post)
とりわけこれまで観光に依存してきた国にとっては、今回のコロナ禍により経済が「生きるか死ぬか」になっているところは多い。同様の検討を勧めているところは少なくないはずだ。
もちろんセイシェルがこのような措置を開始したといっても、観光客の送り出し国では帰国時に従前どおり「14日間の隔離」をそう易々と停止することも現状ではなさそうだ。加えて旅客機の国際間の定期便も激減している中で、セイシェルが期待しているとおりには事が運ばないように思われる。新型コロナウイルスについて、まだわかっていない部分も多く、始まったばかりの接種の効果も未知数の部分もある。
今後、その効果と集団免疫の達成状況、そして各国間の合意等を経ることによって、「海外旅行」の機会が私たちのもとに戻ってくることになるのだろう。まだしばらく時間がかかるのだろう。
個人的にはセイシェルには関心はないが、「早く接種してネパールを訪問したい」と思っている。しかしながら現状では、帰国時には2週間の隔離があるだけでなく、「自粛ムード」の中でたとえ航空券が手に入っても、行けるのか?という面も大きなハードルである。
やはりまだしばらく先のことにはなりそうだが、それでも各地で接種が始まっていたり、開始が予定されているワクチンが大変有効なもので、「接種さえすれば海外渡航も行動も制限なしで当然」というムードが醸成される、ごくごく近い未来に期待したい。