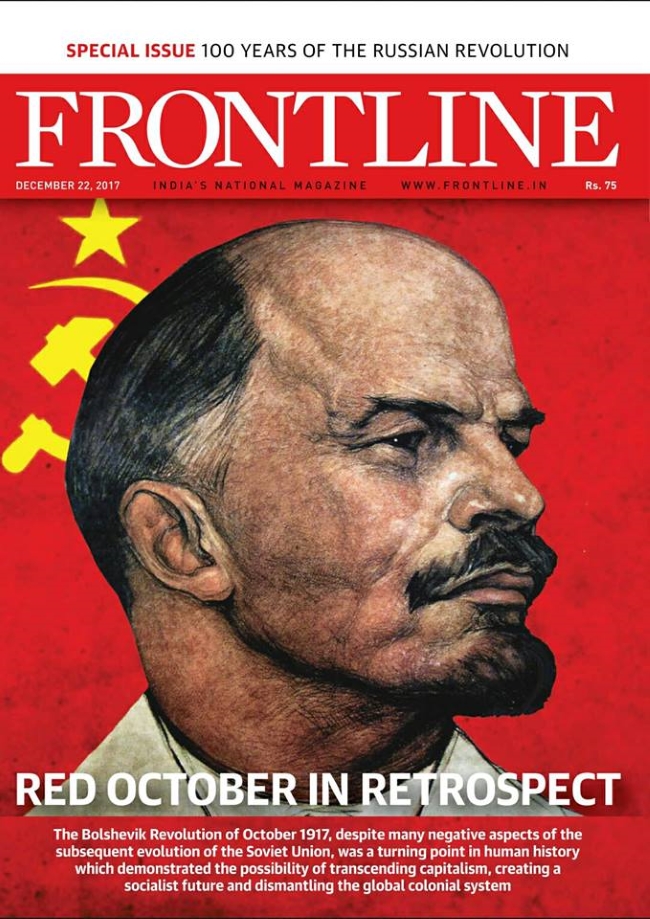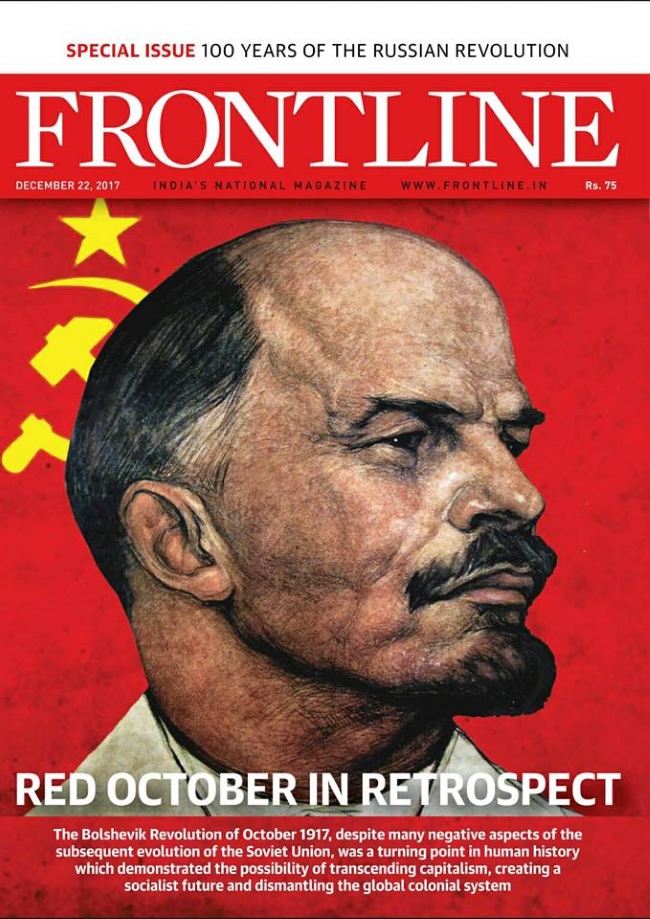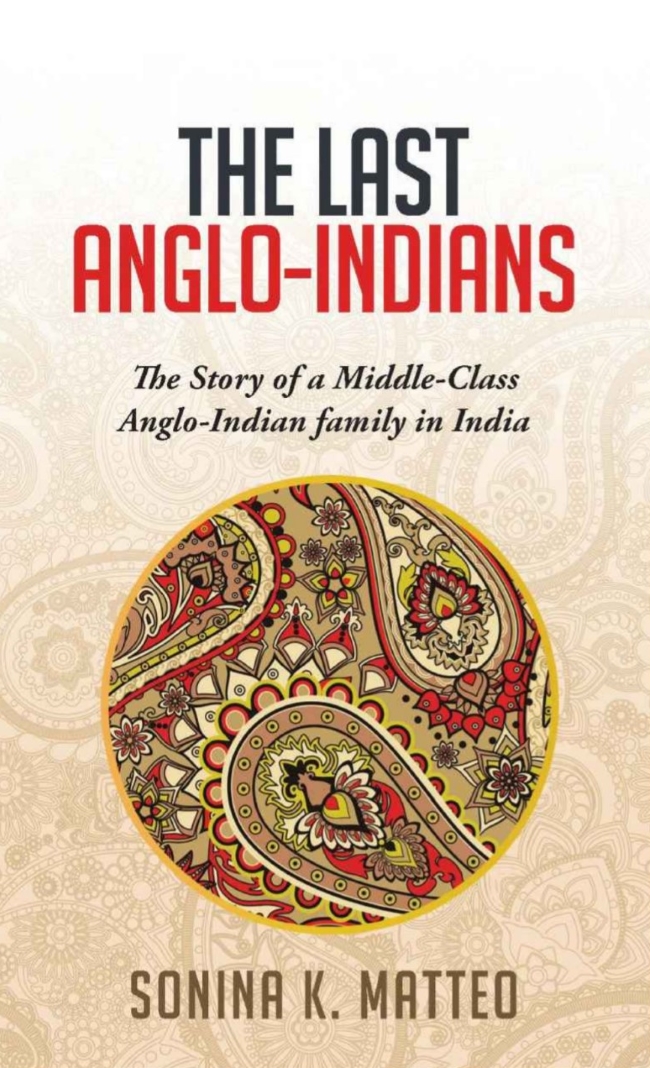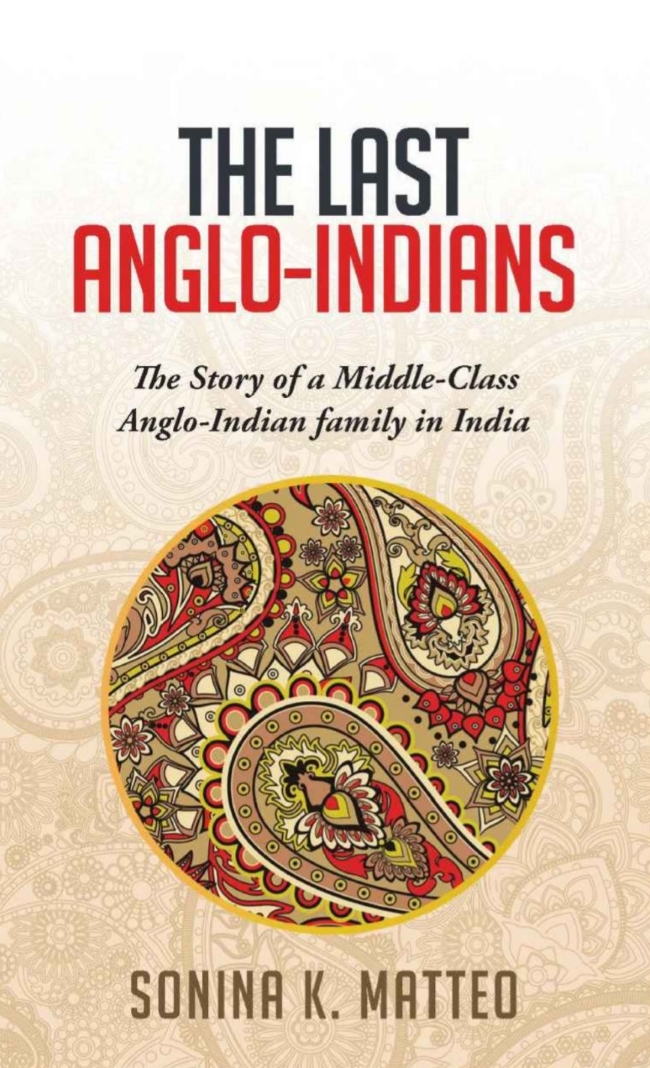1980年代にはゴールカー・ランド分離要求でテロが頻発して、事前にカルカッタなどで発行されたパーミット無しでは入域できない時期もあった。その後は穏やかになっていたものの、西ベンガル平地と分離してひとつの州を創ろうという動きは続いており、今後も同様であろう。やがて、ゴールカー・ランド州が成立する日が来るのではないかと私は考えている。
元々はチベット系のブーティヤー族(ブータン人とごく近い民族)が支配するスィッキム王国の一部であった現在のダージリン。英領インドに割譲されたことから、ヒルステーションとしての歴史が始まる。
スィッキムも同様だが、ダージリンでは英領期からネパールの様々な民族が移民として定着し、現在はマジョリティを成すようになった。これがゴールカー・ランド要求に繋がっていく原点。ゴールカー族が中心というわけではなく、様々な民族が集住している現状だが、ネパール系の象徴として、ゴールカーの名前が政治運動で使われているようだ。
先のゴールカー・ランド要求運動の果実として、1988年に自治組織としてのダージリン・ゴールカー丘陵評議会が成立。西ベンガル州の中では独特なエリアとなっているが、ゴールカー・ランド要求運動の目標は州の創設。闘いは静かに、しかし着々と続いていくこととなった。
現在、丘陵地区の政治を掌るのは、ゴールカー人民解放戦線(GJM)。ゴールカー・ランド州創設を唱える政治団体はいくつもある中で最大の政党。組織力と動員力を誇り、今回の無期限ゼネストは、その影響力の賜物といえる。
以前、ダージリンのチョーラースターで、GJMの青年部がオーガナイズする「ファッションショー」を見物したことがある。ステージで、ダージリンに暮らすネパール系の様々な民族の若者たちが、自らの民族の伝統衣装をまとって自己紹介したり、踊ったりするというもの。ネパール系といっても様々なエスニック・グループがある中での「多様性の中の統一と団結」をスマートにカッコ良く演出していた。ステージのセッティングも、カメラワーク(チョーラースターに入りきれない人たちのために、映像を流す大きなモニターが設置されていた)も、明らかにプロフェッショナルなスキルが感じられた。
最初、事情を知らずに、たまたまその場所に居合わせることになった私は、てっきりクリスマスのために企画された洒落たイベントかと思ったくらいだ。実は政治集会であるということを知って仰天した。
こうした催しを切り盛りしているのが、茶髪にピアス、手足にタトゥーを入れて、崩れた感じのお兄ちゃんから、いかにもエリート学生然とした若者、一見、政治なんかにこれっぽっちも興味の無さそうなモデル風の美女から、家族で経営するお店をやりくりするおばちゃん(お姉さん?)まで、実に様々な人たちが嬉々として参加していた。ネパール系社会の広範囲からの支持があるとともに、資金面でも強力な基盤があることが容易に感じられた。
政治集会で怒りを込めたメッセージを聴衆に伝えたり、デモで動員された群衆がスローガンを叫んだりするだけではなく、若者たちが自発的に楽しみながら参加する政治運動の潜在力というのは、相当なものだろう。
今回の一連の騒動は、そうしたエンターテインメント的なものとはまったく異なるが、地元社会を広範囲に巻き込んで涵養してきたパワーが、ここぞとばかりに発揮されているものであるとするならば、容易に鎮まるものではないことは、想像に難くない。
Violence returns to Darjeeling, Army deployed (THE ECONOMIC TIMES)