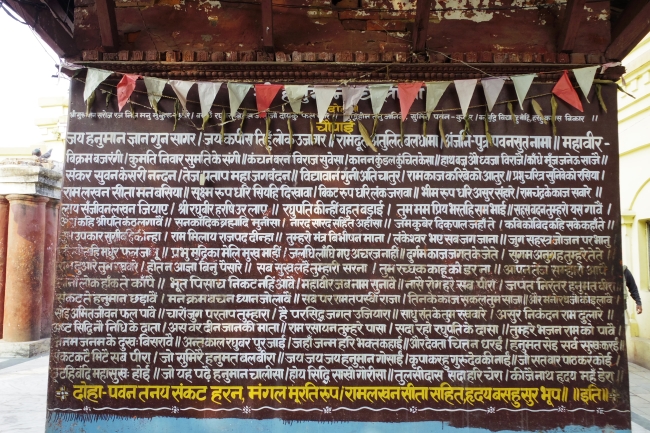マドガオンでの宿泊先で付いていた朝食。プーリーバージーなのだが、使われているのがココナツオイルであることに、なんだか不思議なエキゾ感を覚える。
町中とくに繁華街やその周囲では、元々のゴアの人たちは何割くらいなのか?と思う。観光客ではなく地元で働いている人たちのなかで、明らかにゴアンであるとは思えない人たちがとても多いようだからだ。聴覚的にも、地元に住んでいると思しき人たち同士のヒンディーによる会話も聞こえてきたりする。


インド各地からの移住は自由で、人口圧力の大きな州から大勢流入してくるのは当然のことだ。またビジネスを展開しようという人たちも沢山やってくる。現在、この州がBJP政権下となっている背景には、そうしたこともあるはずだ。
かなり南側に位置しているとはいえ、マラーティー語に近いコーンカーニー語のエリアなので、ヒンディー話者にとっては馴染みやすい言語環境(同様に地元でのヒンディー語受容度もすこぶる高い)であり文化圏であるため、北インドからを引き寄せやすい環境だ。
そんなこともあることから、話は飛ぶが、ポルトガル時代末期には、インド側のスパイや工作員の活動を防ぐことは困難であったらしい。革新志向のインテリ層の若者たちの中で、『祖国復帰』の活動のため地下に潜行したり、インド側の内通者として活動したりした者も一部あったようだ。
とはいえ、大方のポ領ゴアの世論はインドによる『返還要求』を脅威と捉えており、とりわけ受けた教育や社会的地位が高くなるほど、そうした傾向が強かったとのこと。
そんなポルトガル時代末期に、ゴアとパキスタンは蜜月時代にあったことがある。インド独立後にデリーから強硬な返還要求を拒み続けていたポルトガルは、インドによる経済封鎖を受けて、各方面に渡る様々な物資の入手をパキスタンに依存した。パキスタンにとってもインドと敵対するポ領ゴアは戦略上においても大きなポテンシャルを持つ『友好国』であり、食料、生活物資等々、多岐に渡る供給を支援していたようだ。
そんなポルトガル領ゴアとパキスタンの関係も1961年12月にインドが強行したゴア制圧の大規模な軍事作戦、『オペレーション・ヴィジャイ』により、粉砕されることとなる。
当時の貧しかったインドに呑み込まれることを恐れたことに加えて、よくも悪くもポルトガルによる同化志向の強い政策により、ゴア人として独自のアイデンティティとポルトガル本国との強い絆が涵養されてきた歴史が背景にあった。こうした面で、インドネシアと東ティモールとの間にあるものと、似たような土壌かあったとも言える。
復帰後のゴアは、中央政府による連邦直轄地となり、地元の社会・文化・政治環境等には配慮しつつも、16世紀から長く続いたポルトガル式統治のシステムと慣習をインド化することに力を注いだ。ポルトガル時代末期までの在地エリート層で、この時期に凋落してしまった例は少なくない。
ポルトガル語で教育を受けた官憲が英語教育で育った者に置き換えられただけでなく、インドが独立後に実施した土地の分配と同様に、ゴアでも大地主たちが所有していた農地等が分配されたことなどもある。ロンリープラネットのガイドブックで紹介されているBraganza家の屋敷の当主もそんな具合だったのではないかと思う。
ゴアがようやく『州』となったのは1987年のことだ。
インド復帰後のパワーゲームをうまく処理してゴアを上手にインドへ統合させたことになるが、ゴアで2012年にBJP政権が成立したことはエポックメイキングな出来事であり、ゴア問題解消に至るゴールであったと言える。かくしてゴアは普通のインドとなった。
さて、インドによる軍事侵攻に降伏してゴアを去ることになったポルトガル当局だが、1947年にインドを去ったイギリスと対照的なのは、ポルトガル籍を取得していた現地住民と一定ランク以上にあった政府職員への措置。
当時のポルトガルが保有していた海外領、とりわけモザンビークへの移住、再就職を積極的にサポートしたと聞く。もっともそれからまもなくモザンビークはポルトガル支配への闘争から内戦状態となり、インドから移住した官憲は当然攻撃の対象となる。そしてモザンビークは独立を迎える。期待した新天地での明るい未来は無かったことになる。
マドガオン駅は宿から徒歩すぐ。駅で大量に販売されていたが、ゴアのチッキーは、具材が豪華らしい。食べると歯の治療の詰め物が外れたりするのが悩ましい。

ニザームッディーン行きのラージダーニーに乗車。Wi-Fiが利用できて良いと思ったのだが、しばらくすると使えなくなった。携帯電話を入れて、SMSで送られてくるIDとパスワードを入れてログインするため、結局はインドのケータイが必要となる。しかし発車してしばらくすると使えなくなり、シグナルも来ていない。駅だけのサービスというわけではないと思うのだが?