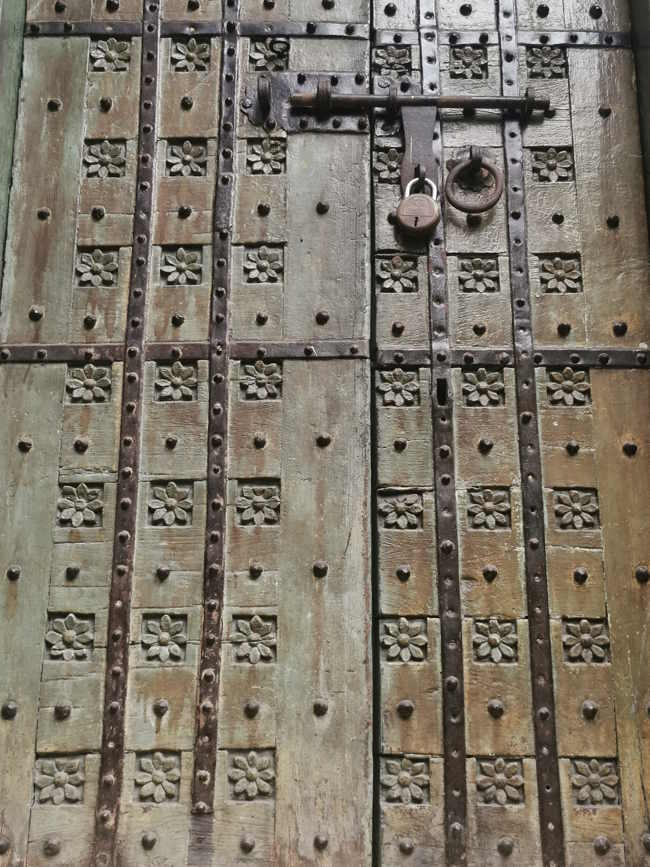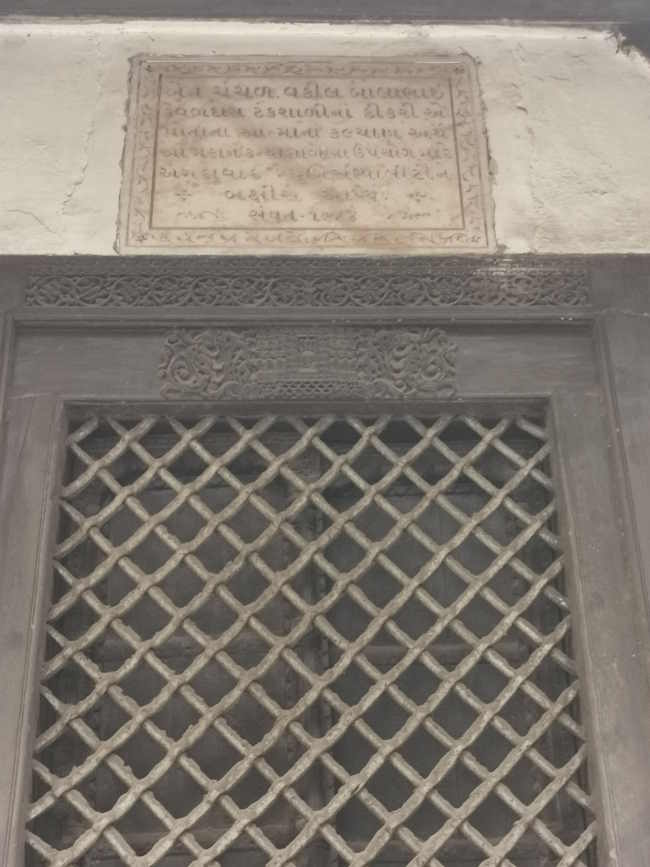来年5月に総選挙を迎えるインドでは、BJPが再び地名変更の動きを見せている。UP州のLUCKNOW(ラクナウ)をLAKHANPUR(ラカンプル)またはLAKSHMANPUR(ラクシュマンプル)にという案が浮上。いずれにしても取って付けたような名称ではなく、それなりにきちんとその土地に由緒あるものであるとはいえ、長らく「LUCKNOW」として知られてきた州都、旧アワド王国の都の名前をそのような形に変更してしまうというのは、ヒンドゥー至上主義右派によるイスラーム文化やイスラーム支配の歴史のあからさまな否定でもある。
Rename Lucknow as Lakshmanpur or Lakhanpur’: BJP MP urges Amit Shah(INDIA TV)
独立以来、インド各地で地名等の変更が行われてきたが、その目的は主に以下のようなものであった。
- 植民地時代式の綴りを現地の発音に即したものに改める。 (CAWNPORE→KANPUR、JEYPORE→JAIPUR、JUBBULPORE→JABALPUR等)2.
- 英語名称を現地語名称に揃える。 (BOMBAY→MUMBAI、CALCUTTA→KOLKATA、MADRAS→CHENNAI等)
同様に、各地のストリート名などが、植民地時代の行政官等に因んだ名前からインドの偉人や独立の志士などの名前に変更されている。インドに限らず植民地支配から脱した国々の多くでこのような名称変更は実施されていることはご存知のとおり。
しかしBJPが政権を握るようになってからは、それ以前は見られなかった新たな形での名称変更が続いている。
3.ムスリムの支配や影響を色濃く残す地名を「ヒンドゥー化」する。(ALLAHABAD→PRAYAGRAJ、OSMANABAD→DARASHIV、HOSHANGABAD→NARMADAPURAM等)
この③のタイプの改名については、コミュナルな背景の意思が働いているため①及び②とは異なり、注意が必要となる。
先述のとおり、2024年5月に総選挙が実施されることに先立ち、今後もこのような地名変更の提案が続くものと予想される。州都ラクナウのような伝統ある地名が③の形で改名されてしまうようなことが本当に起きるとは信じ難いものがあるが、グジャラートのAHMEDABAD(アーメダバード)についても、KARNAWATI(カルナワティ)に変更しようという動きもある。ひょっとすると首都DELHI(デリー)についても、INDRAPRASTHA(インドラプラスタ)に改称される未来が来るのではないかと冗談半分に言われているが、数年後にそういう日がやってきたとしても、あまり驚くに値しないのかもしれない。
頻繁に地名変更を提案したり、それを実施したりしているBJP政権だが、報道を注意深く見ていると、そのような方向に本格的に動き出したことが大きく報じられる前に、国会議員なり地方議会議員なりの「個人的な意見」という形で、しばしば観測気球のようなものが上がっていることに気が付く。
以下の記事は昨年末の報道だが、BJPの議員により「インドの国名を改めよう」という意見。
BJP MP who wants to rename India: ‘PM Modi trying to restore nation’s pride … I thought my question in Parliament will expedite his work’ (The Indian EXPRESS)
「INDIA」を「BHARAT(バーラト=ヒンドゥーの地)」あるいは「BHARATVARSH(バーラトワルシュ=バーラトの大地)」に変更しよういうものだ。
これについては、例えば英語で「JAPAN」と呼ばれてきたのを「NIHON」あるいは「NIPPON」に変えようというようなもの。外からの呼称を内での呼び方に揃えようというもの違和感は薄い。(インド国外でBHARATという名称をご存知ない方も少なくないかと思うので、もしかすると耳慣れない奇妙な呼称に感じるかもしれないが・・・。)
いっぽうでインド、INDIAの別称として「HINDUSTAN(ヒンドゥスターン)」もある。企業名でも「HINDUSTAN MOTORS」「HINDUSTAN PETROLEUM」等々、「HINDUSTAN」を冠したものは多く、日常会話でも自国のことを「ヒンドゥスターン」と普通に呼ぶので、なぜ「HINDUSTAN」にしないのか?と思う方もあるかもしれないが、BJPのようなサフラン右翼(サフラン色はヒンドゥーの神聖な色)にとって、やはり「BHARAT」あるいは「BHARATVARSH」こそが、あるべき母国の名称ということになる。
なぜならば「HINDUSTAN」という名前は、元々はペルシャ(及びペルシャ語圏)の人々から見たインドに対する呼称であって、インドの人々が自国をそう呼ぶようになったのは、ペルシャ語圏から入ってきたその名称が定着したからに他ならないからということが背景にある。