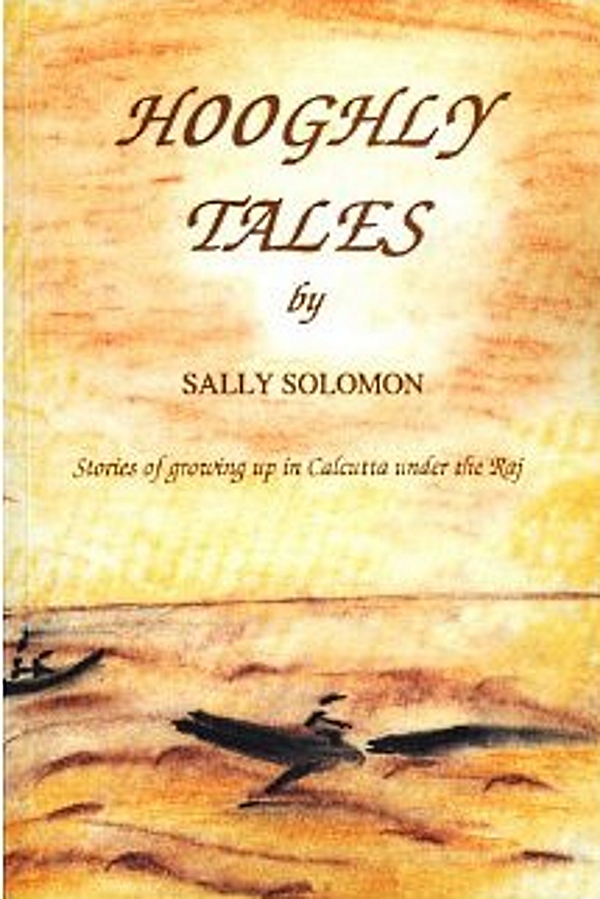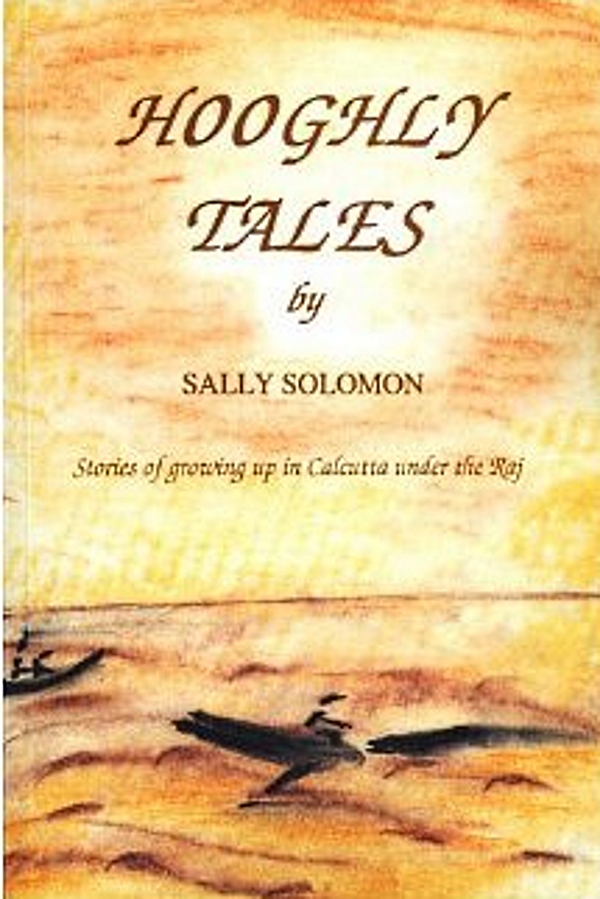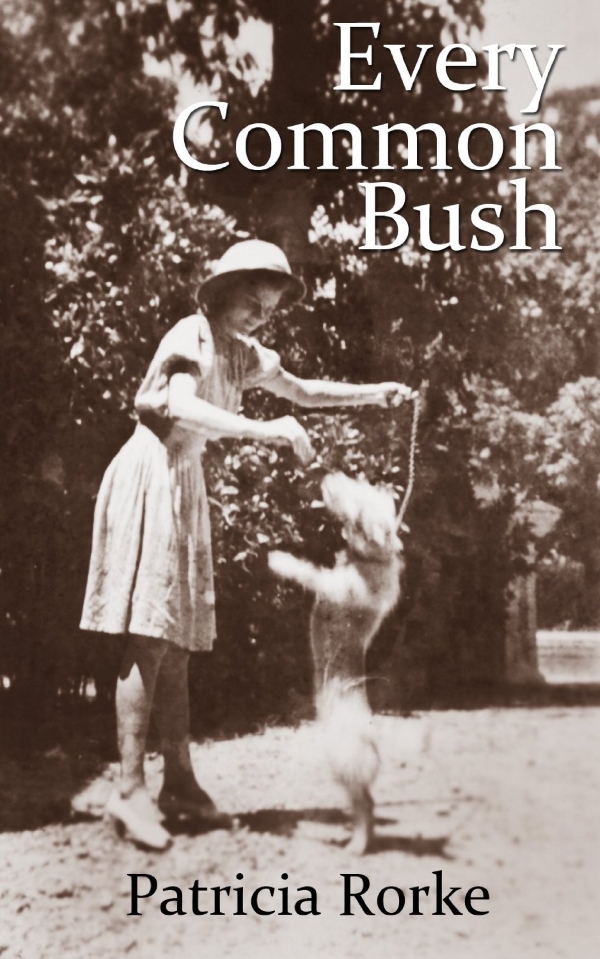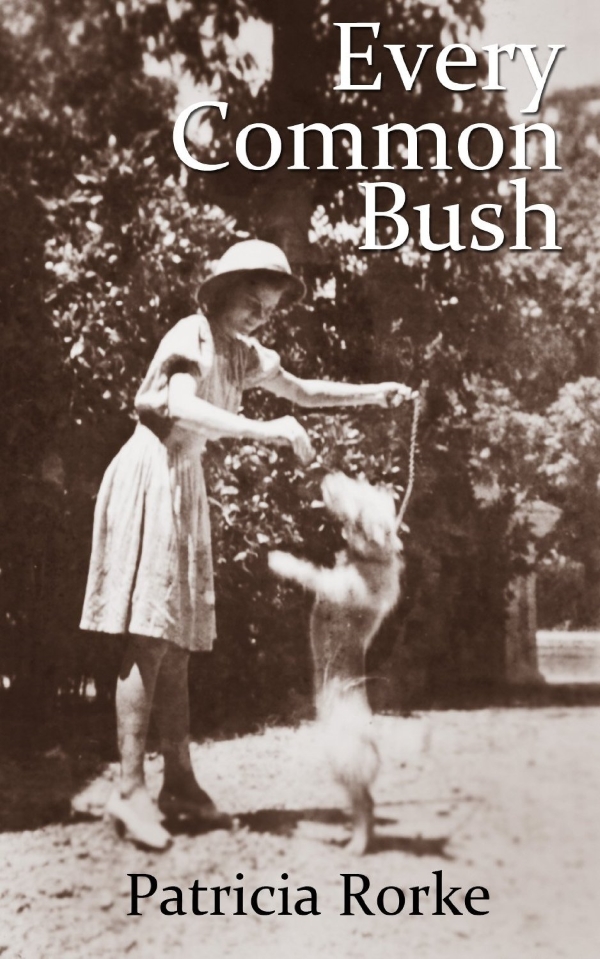サッカーのワールドカップのアジア二次予選の組み合わせが決定した。
日本、シリアなどと同組…サッカーW杯2次予選 (YOMIURI ONLINE)
非常に有利なグループ(日本・シリア・アフガニスタン・カンボジア・シンガポール)に入ったとメディアで取り上げられているが、そのとおりだろう。また、個人的には組み合わせはともかく、アフガニスタンと一緒のグループに入ったことについて興味深く感じている。
2011年にアジアカップ一次リーグでシリアと対戦して、2-1と日本が苦戦した相手シリアはともかく、まったくノーマークのアフガニスタンに注目したい。FIFAランキングのシリア126位と同じく、アフガニスタンの135位はどちらも苦しい国情のためもあり、国際試合の機会が希薄であることからくるもので、実力を反映したものとは言えない。
南アジアで開催された国際大会やアフガニスタン国内リーグなどをネット中継で観戦したことがあるが、南アジアサッカー連盟加盟の8か国(アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パーキスターン、バーングラーデーシュ、ブータン、モルジヴ)の中で、アフガニスタンは一線を画す存在だ。
南アジア選手権においては、2011年大会に大躍進を見せて準優勝、続く2013年大会では見事優勝している。この大会の決勝戦で対戦したのは、2011年大会と同じくインド代表であったが、2-0でこれを下した。ちなみにこのときのインド代表には、日本で生まれ育った日系インド人(父親がインド人、母親は日本人)のMFプレーヤー、和泉新(いずみあらた)選手が出場していた。アルビレックス新潟のサテライト(シンガポールのSリーグ加盟)でプレーしていた選手だが、日本のアマチュアチームを経て、インドのIリーグの名門イーストベンガルに加入後、同じくIリーグのマヒンドラ・ユナイテッドFC、そして現在はプネーFCでプレーしている。
さて、長年国内リーグを安定的に運営してきたインドをはじめとする国々が出場する大会で、これまでサッカーのインフラもなく、復興に向けてゆっくりと歩みを重ねつつある国の代表が制するというのは尋常ではないが、実はそれには訳がある。
アフガニスタン国内を横断するトップリーグ「ローシャン・アフガン・プレミアリーグ」は2012年に始まったばかり。それでいながら、報酬を得てプレーする「プロ」選手も少なくない。現状はよく判らないが、少なくとも発足当時、選手たちは年契約ではなく、試合ごとに「日払い」で報酬を受け取るというのが普通であったようだ。もちろん勝敗や個々の活躍ぶりによって受け取る額は変動したのだろう。
しかしながら、国内リーグの惨状とは裏腹に、海外のクラブにて活躍中で、母国の代表に招集される選手たちの存在と彼らのポテンシャルの傑出した高さがあるのがアフガニスタン代表の特異なところだ。代表選手たちの半数ほどは欧州を中心とする様々な国々のクラブでプレーしており、国外生まれの者も少なくない。
よって、スタメンで出てくる主力は海外仕込みの選手たちとなるであろうことから、日本が相手にする相手の大半は、本格的なサッカー環境とはほど遠いところで育った「アフガンの地場産の選手たち」ではなく、外国の2部や3部のクラブに所属とはいえ、紛れもない「本場仕込みのプレーヤーたち」であることを念頭に置く必要があり、他の南アジアサッカー連盟に加盟している国々の代表とは格が違うのは当然ということになる。
地域では突出しているとはいえ、日本代表が圧倒されるケースは想像しにくいが、「意外にいいサッカーをする!」と評価される可能性があるアフガニスタン代表だ。国内が安定して成長が見込めるようになると、今後さらに急伸していく可能性もある。
アジア二次予選では、ホーム&アウェイ方式で二試合ずつ、合計8試合行われることになるが、情勢が緊迫しているシリアもさることながら、果たして首都カーブル(「カブール」という表記がメディア等で見られるが、ペルシャ文字で「کابل」と綴るので、「カーブル」が適切)で今年9月8日に予定されているゲームが実現できるのか、第三国での開催となるのかについても注目したい。
安全確保が最優先であるのは当然だが、関係者たちの努力により、カーブルでのアフガニスタン代表のホームゲームが開催されるとなれば、アフガニスタンサッカー界にとって歴史的な快挙となるだけではなく、アフガニスタンのサッカーファン、とりわけ元気な子どもたちへの大きな贈り物にもなる。また、長く続いた内戦でズタズタになった国で、異なる民族の人々が声をひとつにして「私たちの代表」を応援できるということは素晴らしいことだ。
スポーツが平和のためにできることはいろいろある。勝ち負けだけではない「絆」や「共感」を持つことができることもまた、スポーツの国際大会の大きな意義のひとつだろう。アフガニスタンのサッカーファンにとっては、今や世界的な強豪国の一角となった日本を迎え撃つ「ワールドカップ予選試合」をホームで実現することは、日本がこの二次予選、そして最終予選を制して6度目の本大会に出場する以上に大きな意味のあることだ。勝敗はともかく、これを実現するということは、人々の心に届く、真に勇気ある国際平和貢献となることは言うまでもない。
はなはだ残念なことであるが、シリアにしても、アフガニスタンにしても、こうした大きなイベントは反政府勢力にとって格好のターゲットとなり得ることは間違いない。スポーツに政治を持ち込むことなく、誰もが心ひとつにして自国代表を力いっぱい声援できる環境を造ることは、思想や主義主張を越えて、FIFAや日本とアフガニスタンサッカー協会関係者たちはもちろんのこと、アフガニスタンの行政、治安当局や反政府勢力等々にかかわるすべて大人たちひとりひとりに課せられた責任でもあるとともに、私たち日本人もまた実現に向けて世論を後押ししていくべきだろう。
アフガニスタンで、後世に語り継がれる「伝説の試合」が現実のものとなることを期待したい。