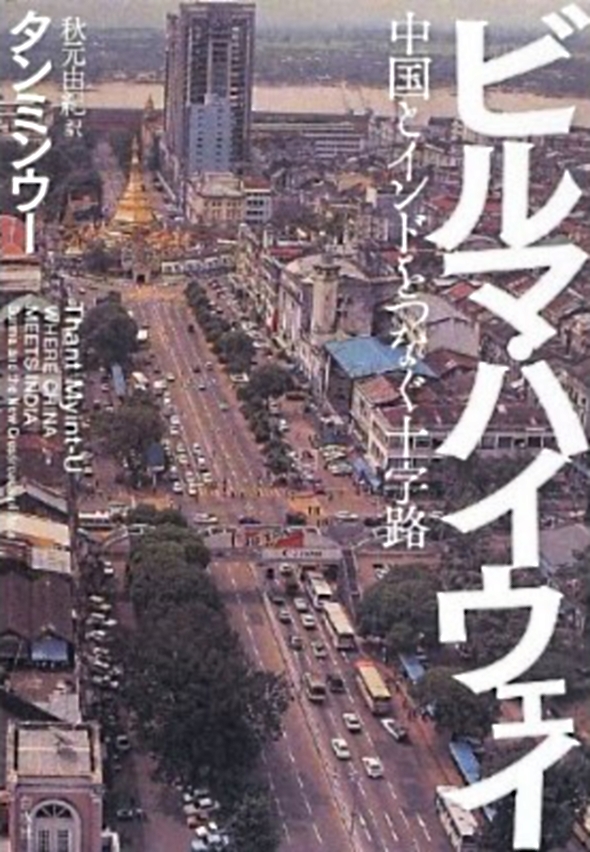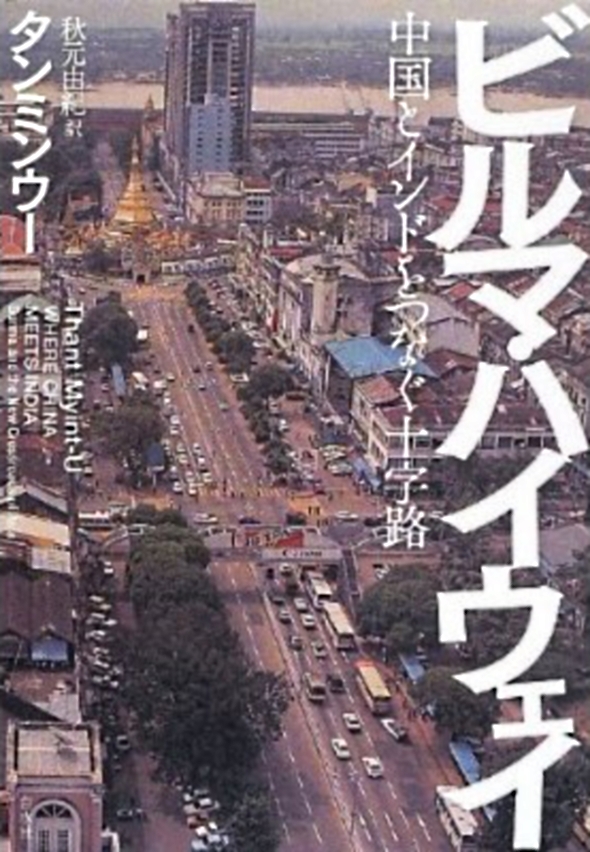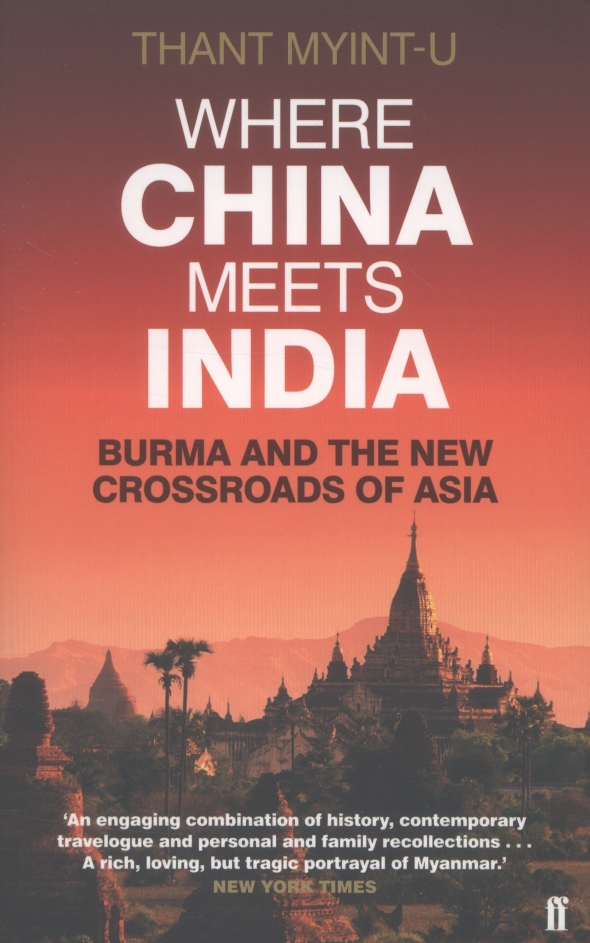近ごろ、首都圏でネパール人の姿を見かけることがとても多くなった、とりわけ若い人たちがよく目に付く・・・と感じている人は少なくないことだろう。
それもそのはず、ここ数年来、日本留学の入口となる日本語学校に入るために来日するネパール人が急増しているのである。
こちらの資料(一般財団法人日本語教育振興協会による「日本語教育機関実態調査」P5)をご参照願いたい。
ここに示されているのは、平成21年度から25年度までの日本語教育機関の学生数とその国別内訳だが、従前から日本への留学生出身国のベスト3といえば、中国、韓国、台湾の「御三家」であったのだが、すでに平成21年度において、それ以前は留学生の中ではマイノリティであったベトナム、ネパールが急伸しており、トップの三国に迫るところに来ている。
平成23年度に入ると、すでにベトナムは台湾からの留学生数を抜いて3位に食い込み、4位の台湾とほぼ同じレベルにまで達しているのがネパールだ。ベトナムとネパールは平成25年度には韓国を抜いて、それぞれ2位、3位となり、首位の中国からの留学生の規模には遠く及ばないものの、現在では御三家といえば、中国、ベトナム、ネパールとなっている。
留学生たちの実数で見ると、平成21年度にはベトナム847名、ネパール839名であったものが、4年後の平成25年度には前者が8,436名、後者が3,095名となっている。伸び率はそれぞれ9.96倍、3.69倍である。
その間に、元御三家の韓国は8,360名から2,386名、台湾は2,304名から1,425名へと、それぞれ元の数の0.29倍、0.62倍へと激減しているという背景もある。不動の首位の中国にしてみても、26,632名から18,250名へと、0.68倍という急激な減少がある。
留学生総数にしてみても、平成21年度の42,651名から平成24年度の29.235名という0.69倍という激しい落ち込みから平成25名は37,918名へと持ち直しているものの、それでも平成21年度と比較すると0.89倍という芳しくない数字である。
こういう具合になったことにはいくつかの要素があるので簡単に解説しておきたい。平成18年から19年にかけて、中国からの留学希望者に対する入国管理局や在外公館での審査が厳重となったため、多数の留学予定者対する在留資格認定証が不交付となったり、在外公館で査証が発行されなかったりという事態が多数発生し、日本語学校によっては中国からの入学予定者の半数前後が来日できず、留学をキャンセルというケースが生じた。
もともと零細な規模のものが多い日本語学校の世界では、送り出し数の多い国にパイプを持ち、そこから安定的に学生を供給してもらおうという傾向が強かったのだが、そうした中で、とりわけ中国への依存度が高かった学校の多くは、これを死活問題と捉え、他なる留学希望者送り出し国の開拓に乗り出さなくてはならなくなり、そうした学校にとってそれまでは視野に入っていなかった地域に精力的に働きかけることとなった。
その努力の結果、とりわけ新規来日学生の大規模な招致に繋がったのがベトナムとネパールであった。どちらも移民圧力の高い国であり、その当時までは日本における不法残留率も高くはなかったため、比較的順調に導入することができたといえるのだろう。
その後、来日数が安定的に増えてくるにつれて、すでに来日している者と自国との繋がり、日本語学校による更なる努力による留学需要の掘り起し、送り出し国側のそうした斡旋機関もそうした渡日熱の高まりにアテ込んで、これに加担したということもある。やはりそこは商売である。
異常が、ベトナムとネパールから来日して日本語学校に入る者が急増している背景についての簡単な説明であるが、いっぽうで今も御三家ながらも人数が大幅に減っている中国、元御三家から転落した韓国と台湾の落ち込み具合にはどのような理由があるのかについてもざっと述べておくことにしよう。
まず中国、韓国、台湾いずれについても共通して言えることは、自国経済の順調な成長ぶりと日本の長引く不況から、相対的に日本に対する魅力が薄れてきていることがある。これまで高く見上げていた対象が、相対的にその背丈が自分たちの居る場所から見て、さほど上のほうにあるように感じられなくなってくる。
日本語学校に入るということは、その中のマジョリティは大学や大学院への進学、そして日本での就職、将来的には日本のそのまま定住するという、移民のステップとして捉えている部分は決して少なくない。日本での留学の目的といえば、日本という国そのもの、日本の文化を学ぶというよりも、経済、金融、理工学、その他ハイテク分野といった、いわゆる「実学」を志向する割合が非常に高く、学業を終えた後での定着先としての日本についての期待があまり持てなくなってきているであろうことは、誰も否定できない。
とりわけ韓国については、グローバル市場における自国の一流企業の隆盛と、それに対する日本企業の地盤沈下を目の当たりにして、日本に対する興味・関心が急速に萎んでいくのは仕方のないことであったのだろう。
もちろん中国や台湾と日本の間にある尖閣諸島問題、韓国と日本の間の竹島問題その他の領土に関する論争、はてまた今なおくすぶり続けている歴史問題等々の政治的な事柄による日本に対する政治的なイメージの低下という面も無視できないものがあるにしても、やはり大半は私費で来日する留学生たちにとって、そうした思想的な要因よりも、実利的な要因が大きく作用するのは当然のことだ。
平成20年代に入るあたりから、上で述べた事柄を背景とする留学生数の頭打ち傾向があったのだが、これをさらに決定付けたのは平成23年の春に起きた東日本大震災、いわゆる3.11という大きな出来事であった。
「落ち目だった日本もこれで終わりだ」とまで言うわけではないが、地震、津波よりもむしろ原発事故による影響が大きかった。日本では大変センセーショナルながらも、極力抑えた調子で報道されていたのに対して、海外とりわけ近隣国での報道に抑制を期待できるわけもなく、日本に対する期待値は非常に低くなってしまった。
そうでなくても、これらの国々から人気の留学先としては、アメリカその他の欧米先進国がまず一番手にあり、二番手以降に日本という選択肢があったわけだが、その地位が大きく後退してしまっているのが現状である。
ベトナム、ネパールからの留学生の急増については、もともと需要の高くなかった地域であるだけに、勉学意欲の面でも経費支弁能力の面についても疑問符の付くケースが少なくなく、実際に来日してから雲隠れという事例も多いため、入国管理局による審査も非常に厳格そなものとなっていることは、元御三家の韓国と台湾とは大きく異なる。
総体的には、中国、韓国、台湾からの留学生の落ち込みを補うという点において、数の面からも質の部分からも決して充分なものとは言えないのが現状であるとともに、他にも様々な問題を抱えていることは否めない。
しかしながら、視点を変えれば、これらの国々と新たに緊密な関係を構築する良い機会であるということもあり、とりわけITの分野で地味ながらもそれなりに着実な成長を続けているベトナムから日本に留学する人が急増している中で、様々な問題はあれども、知日家が倍増していくという状況は将来的にプラスに作用することを期待したい。
ネパールについては、すでに日本で実業界その他で活躍している人たちがNRN(Non-Resident Nepalis)として様々な活動をしていることは一部で知られているが、とりわけ著名な存在として、今のネパールからの留学生たちよりもずいぶん早い時期に来日して学び、飲食業界での起業を手始めにネパールからインド、中東の産油国方面へのフライトを飛ばす航空会社を設立するまでに至るとともに、日本からネパールへの空の便の開設を企図しているB.B. Airwaysの代表のヴァッタ・ヴァバン氏が挙げられる。
様々な背景や動機により、日本を必要としてくれている若いネパール人たちの中から、将来の日本が必要とする人材が輩出し、新たな絆が築かれていくこともまた大いに期待したいものである。