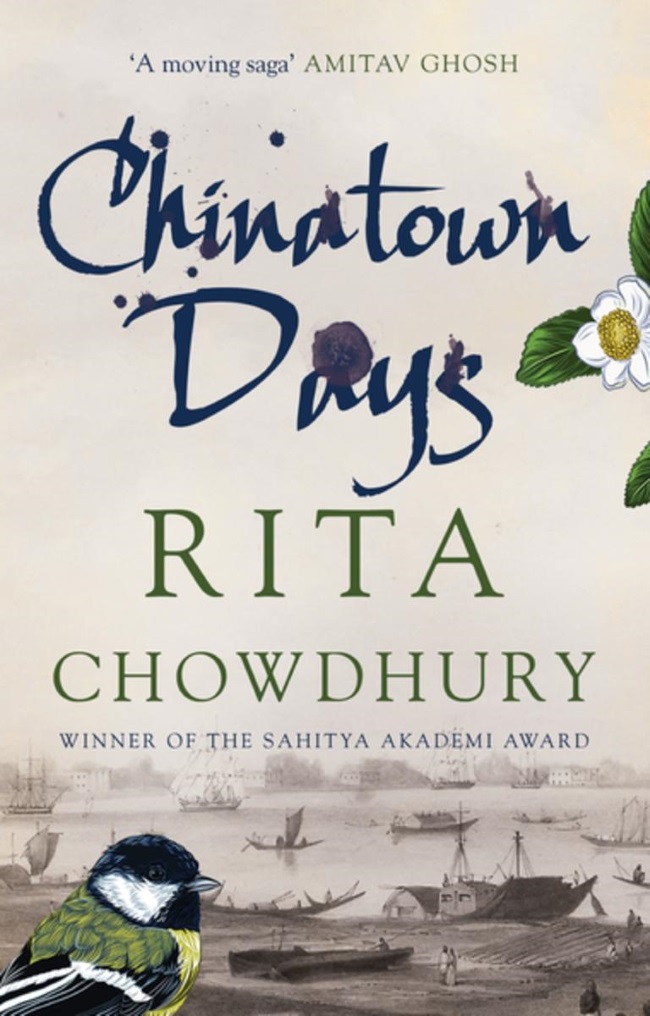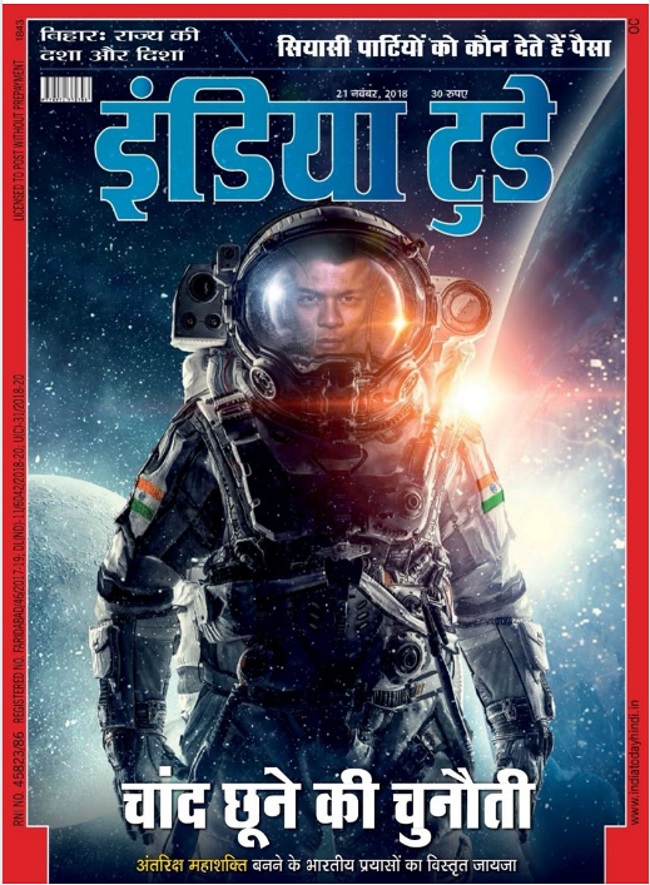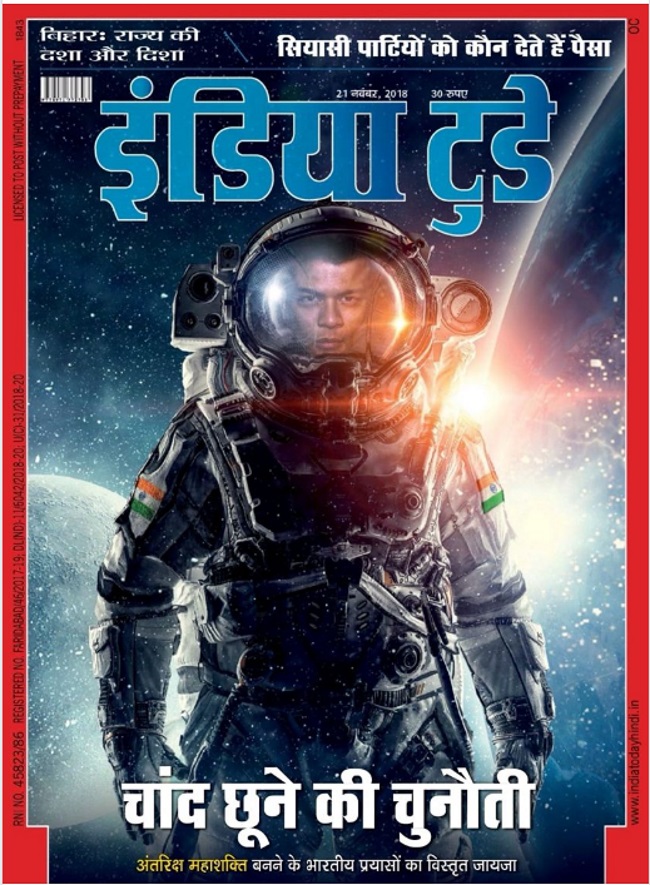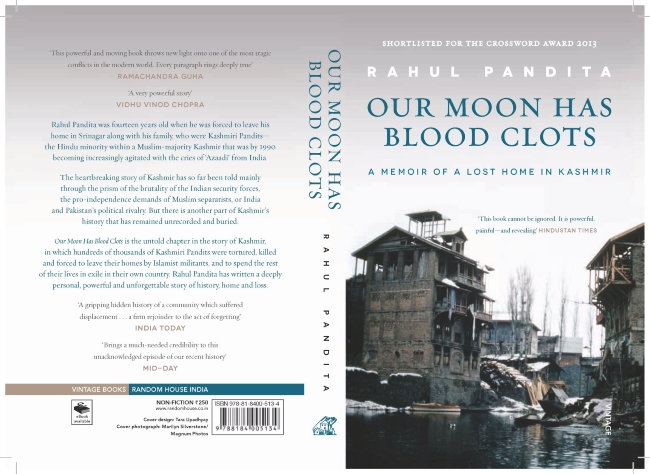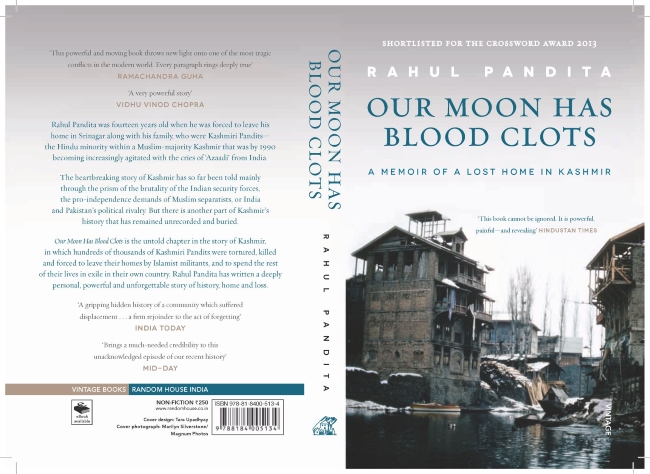昨日は2008年11月26日に発生したムンバイ同時多発テロから10周年であった。
この日の夜9時半頃に発生したムンバイCST(チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス)駅での銃乱射を皮切りに、コラバのレオポルド・カフェへの襲撃、タージマハル・ホテルとトライデント・ホテルでの立て籠もり、ユダヤ教施設のナリーマン・ハウス襲撃など、南ムンバイの複数箇所で時を同じくして複数のテロが実行された。
パキスタン水域から侵入し、インドの漁船を乗っ取ってムンバイに上陸した犯人たちは、犯行地点までは市内を流していたタクシーで移動したが、降車する際に車内に時限爆弾をセットしたため、これを知らなかったドライバーが向かった先でクルマが爆発を起こしている。
またムンバイCST駅で銃を乱射した際に被弾した人たちの多くが搬送された先のカーマ病院でも襲撃を加えるなど、非常に入念かつ冷酷な犯行であった。
2001年9月11日に起きたニューヨークでの同時多発テロの際もそうであったのだが、進行中の事件がテレビ等で中継されることをも計算に入れており、私たちは画面の前で進行している悪魔の仕業におののきながら釘づけとなった。
このとき私はAaj Tak、NDTV India等のニュース番組で成り行きを見つめていた。夜になっても、気にかかって寝ていることはできず、ほとんど徹夜で視聴していた。インドの大手メディアは電波だけではなく、インターネットでもニュース番組をリアルタイムで配信しており、私は日本でそれを見ていたのだ。
実行犯たちは携帯電話で、彼らをそこに送り込んだパキスタンのテロ組織幹部と連絡を取っていることが明らかになっていた。そんな中、テレビでインドの治安組織側の対応が放送されること、その時点でこの事件についてインド側が把握していることを逐一電波で流してしまうことは、敵に手の内を見せているようなものだという批判もあった。
犯人たちが立て籠もったタージマハル・ホテル、トライデント・ホテル、ナリーマン・ハウスでは、長いこと膠着状態が続き、制圧へ向けて動き出すには、デリーから投入された特殊部隊のコマンドーたちの現地到着を待たなければならなかった。
そしてついに彼らが現場に投入され、事態は急展開を見せた。事件発生から実に足掛け3日目の朝8時、最後の立て籠もり現場であったタージマハル・ホテルが制圧された。死亡者174名、負傷者300名以上という凄惨な事件がようやく幕切れとなった。
なお、この事件の実行犯10名のうち、事件当時21歳だったアジマル・カサーブは、この手の事件としては珍しく警察に捕縛された。(2012年11月に絞首刑)
後に事件の背後関係や実行犯たちの出自等の詳細がよくわかるようになったのは、犯人の1人が生け捕りになったためという部分も大きい。この若い実行犯男性を主人公にした映画The Attacks of 26/11 (2013年公開)は、そうした情報を下敷きして制作された作品だ。
こうしたことが二度と起きてはならないのだが、決してそうはいかないように思われるのは、やはりインド・パキスタン関係であり、商都ムンバイをターゲットとした場合のインパクトの大きさであり、いつ何時見知らぬ人が徘徊しても誰も気にさえ留めず人々の往来を管理することが困難な大都会の匿名性でもある。