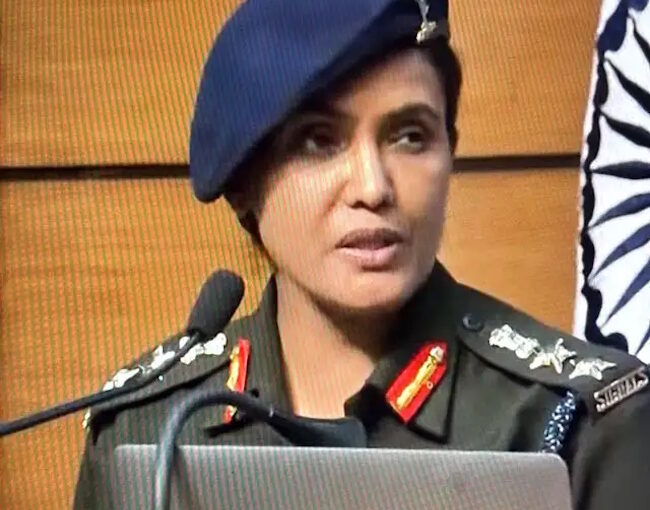やがて大きな転換期が訪れる。政治家としてのインディラーの跡取りと目されていたサンジャイが趣味の自家用機の墜落事故により急死。ラージーヴは「弟の代わり」に国民会議派でのキャリアをスタートさせることになる。
続いて1984年にインディラーがアムリトサルの黄金寺院占拠事件への対応として強硬手段の決行(Operation Blue Star」を命じたことから、首相公邸で勤務していた二人のスィク教徒護衛が彼女を射殺したのだ。パンジャーブでの騒乱ついては、混乱を起こしているのはパキスタンから支援を受けたスィク教徒過激派であったが、これに対して取締り、捜索、逮捕、尋問といった対応をしていたパンジャーブ警察も同様に主にスィク教徒を中心に構成されていたここと、同様に事が深刻となってからは軍も対応していたが、ここでもスィク教徒たちが重要なポジションを占めていたことから、「反スィク」の動きはなかった。だがここで、首相直々の護衛が敵方と通じていたことで、一気に反スィク暴動が発生することとなった。(それにしてもよくもまあ、首相の身近な人間をオルグできたものである。)
インディラーの死により、それまでは幹部候補生見習いのような立場であったラージーヴがインディラー亡き後の後継者として担ぎ出されておおかたの予想どおり、政治家としての能力は芳しくなく、政局が流動化していく。インディラーの死から7年後の1991年、ラージーヴは選挙戦の遊説先のタミルナードゥでLTTEの活動家女性による自爆テロで死亡してしまう。彼の首相在任時代にスリランカ内戦に干渉したことに対するLTTEによる「お礼参り」であった。政治に関わるとロクなことがないという、結婚前のソーニアーの予感が見事に的中したのであった。義母と夫を7年間の間に相次いで暗殺により奪われてしまったからだ。
その後、長らくソーニアーは政界入りを固辞し続けていたが、ついに追い込まれて受諾することとなったのが1999年。当初は「一応ガーンディー家というお飾り」と目されていたのだが、かつては「ちょっとおバカなお嬢さん」と評された彼女が並み居る幹部たちを掌握し、政権奪取後には首相職は固辞しつつもマンモモーハン・スィンというイエスマンを首相に付けて、常に背後に付き添い小声で指示するという「操り人形師」のような形で「実質の首相」としてインド中央政界を二期に渡って支配するまでになった。
そんなネルー/ガーンディー家の政治家としての草創期の記憶がたっぷりと保存されているこの屋敷を見学するのはたいへん興味深いことであった。たしか1988年からその翌年あたりに訪問していたはずなのだが、当時はそんなことに興味がなかったからかもしれないし、展示内容も異なっていたのかもしれない。今回訪問してみて良かったと思う。
アーナンド・バワンに展示されていたジャワーハルラール・ネルーが娘インディラーの結婚にあたり、招待者たちのために書いたという手紙。同じ内容でヒンディーとウルドゥーで書かれている。時期はインド独立前の1942年。近年改名される前までは「アラーハーバード(もしくはイラーハーバード)」と呼ばれていたこの街だけでなく、ヒンディーとウルドゥーはともに広く使われており、宗教を問わず書き言葉としてのウルドゥーは、知識層にとって当然の教養であったため、ヒンドゥーのネヘルーがウルドゥーで手紙をしたためても何の不思議もなかった。
もちろんそんなことはインドの人たちはよく知っているものの、私がこの手紙に見入っていると、インド人年配者たちのグループが「ほう、ウルドゥーでも手紙が書いてある」とささやいているのを目にした。そんな時代があったことを知ってはいても、ネルーがウルドゥーで書いた手紙を目の前にすると、ちょっと意外な感じがしたのだろう。