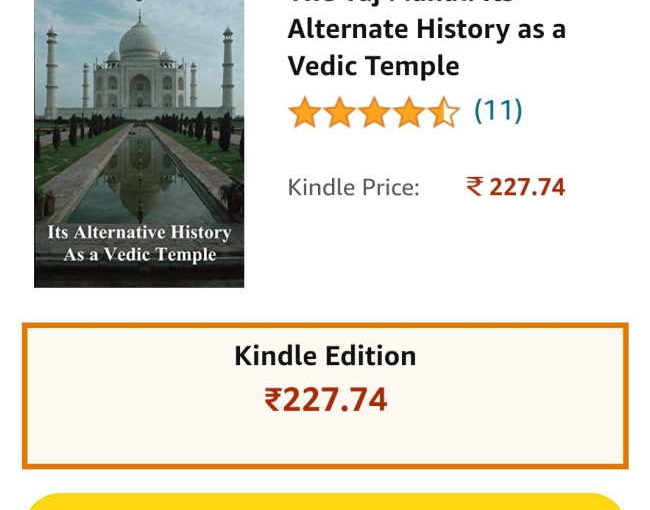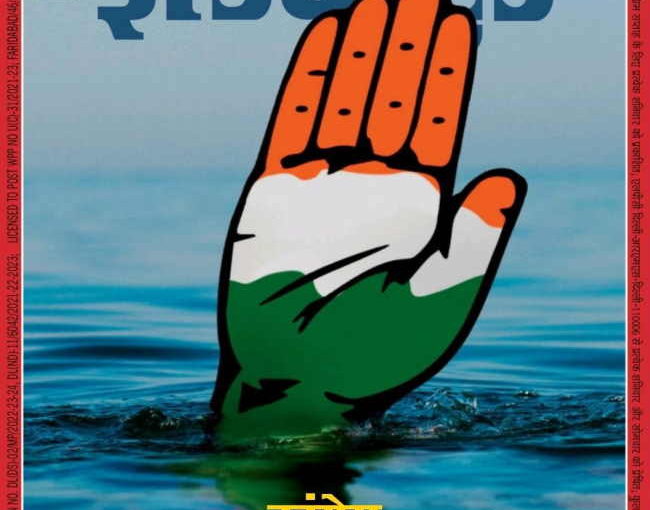5月29日に、パンジャービーのラッパー(パンジャーブ州議会議員でもある)のスィッドゥー・ムーセーワーラーがクルマで移動中に十数発の銃弾を撃ち込まれて殺害されるという凄惨な事件があった。関与が疑われているのは、パンジャーブ出身のギャング、ローレンス・ビシノーイーだが、現在デリーのティハール刑務所に収監中なのになぜか?と言えば、塀の中からスィッドゥーを脅迫していたローレンスは、彼の殺害を決めて、在カナダのパンジャービーギャング組織と連絡を取り、カナダからパンジャーブ現地の手下だか協力関係にある者たちがスパーリー(ヒットマン)として送り込まれたらしい。今どきのインドらしい国際間の連携とも言える。
こうしたリスクを抱えている有名人たちには、先の州議会選挙で国民会議派が負けて庶民党政権となるまでは、手厚い警護が付いていたのだが、政権交代後は「セレブを特別扱いしない」という庶民党の方針から警護体制の簡略化が実施されており、まさにそれを突いての犯行であったとされる。
それまでスィッドゥーは防弾処理を施された車両で複数のガードマンたちと往来していたとのことだが、この日は自家用車で、後続車両におそらくライフルを手にした護衛が付くのみであったといい、高性能銃器を手にしたプロの殺し屋による奇襲には対応できなかったようだ。
サルマーン・カーン自身も、ローレンスからずいぶん前から脅迫されてきたひとりで、身の安全が危惧されているため、この事件後は警護が大幅に強化されることになったと聞く。
インドの音楽関係者にしても映画人にしてもこの手の脅迫にかかる事案は昔から多く、かつてはグルシャン・クマールのような超大物さえも殺害されたことを記憶している人は多いだろう。