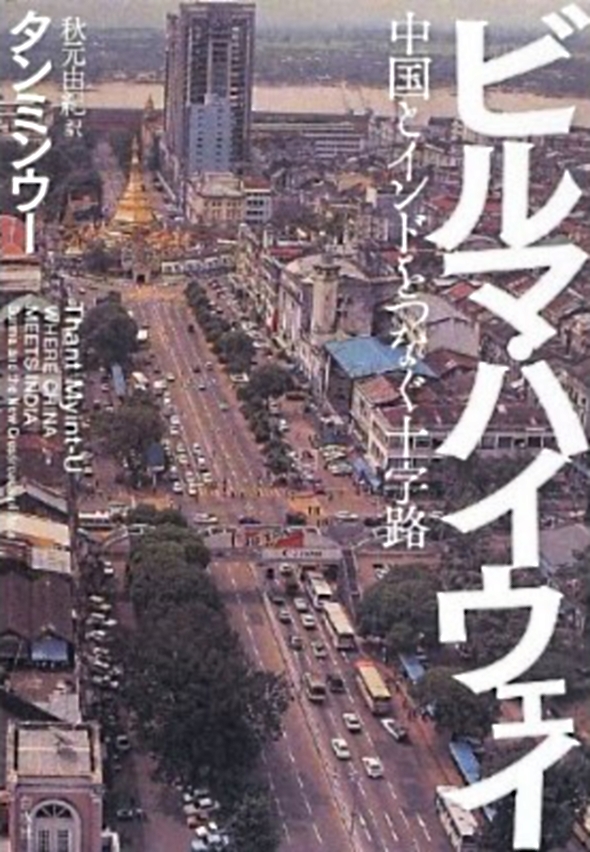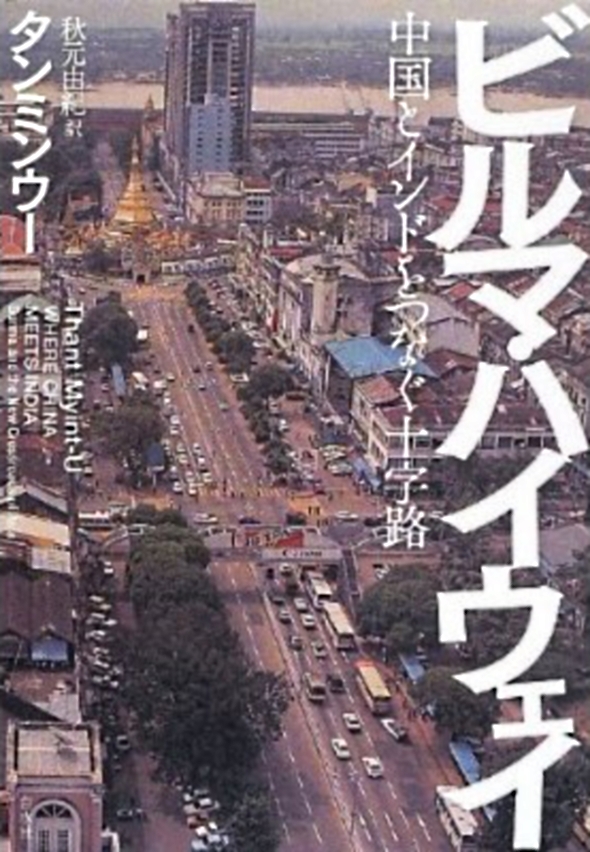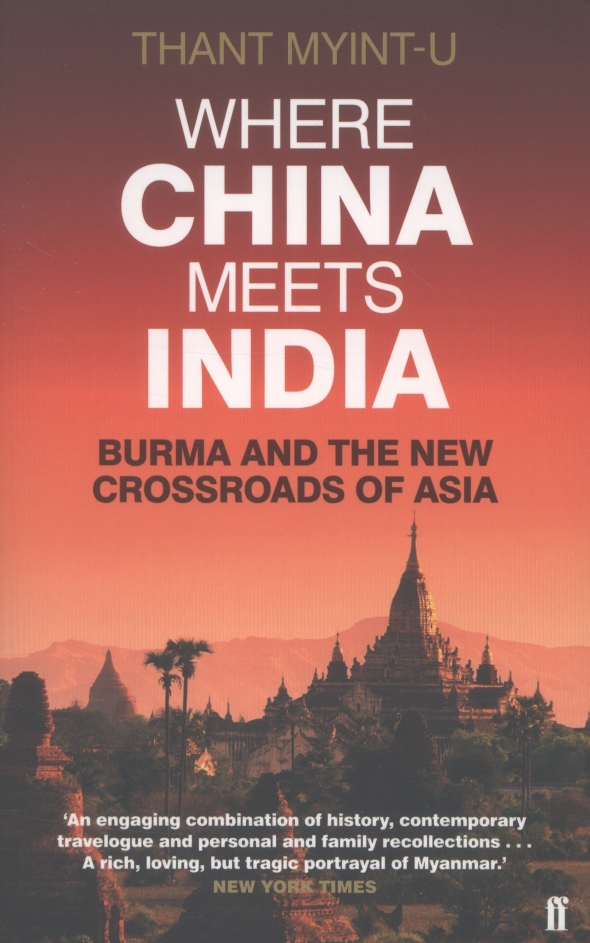昨年のクリスマスはナガランド州のモコクチュンで過ごした。
90%以上の人々がクリスチャンであり、またその中の大半がバプティストという紛れもないキリスト教環境にある中、欧州とは異なる場所にありながらも、本格的なクリスマスを体験できる場所であることを期待した。
ナガランド州最大の街ディマープル発のモコクチュン行きのバスが、アッサム州のジョールハート近郊のマリャーニーを通る(このルートはナガランドの道路事情が良くないためアッサム州を経由して走行している)するはずなのだが、クリスマス直前のため、減便して運行がなされているとのことで、待てどもバスは来なかった。
そんなわけで、同様にバス待ちをしていた人たちとタクシーをシェアしてモコクチュンを目指さざるを得なかった。シェアする人たちはナガランド人ではなく、アッサムを含めた平地のインド人たちで、ナガランドで軍の基地の出入りの業者その他、ナガランドで何がしかの仕事をしている人たちであった。
ナガランド州は、インドにありながらもイギリス領時代からこれまで長きに渡り、他州の人たちの出入りを原則禁じてきた地域である。パーミットを得てのみ入域が可能で、中央政府関係の仕事、軍関係の任務に携わる人たちに加えて、道路建設や建物の建築作業その他の作業に関わる人たちがやってくるとともに、数は決して多くない観光客が訪問する程度であった。
長く続いてきた地元の反政府勢力と政府軍との内戦、同時に同じナガ族の反政府組織やその他周辺民族の武装組織同士の武力抗争等もあり、治安面での印象は決してよくなかったため、それほど多くの人たちがナガランド州を目指してきたわけではない。2011年の元旦から、外国人はナガランド州ならびにミゾラム州とマニプル州への入域が原則自由化され、それに少々遅れてインド人もパーミット無しで入ることができるようになったようである。
現在もナガランド、ミゾラム、マニプルの三州で反政府武装組織は存続しているのだが、政府側との停戦が功を奏して、治安面での改善が見られるようになったことが、内外の観光客によるこの地域への訪問の自由化に繋がったわけである。
まだ先行きの不安は否定できないものの、2011年に「とりあえずは1年限り」として自由化されたものが、すっかり定着しているところを見ると、今後大きなトラブルが生じない限りは、今後もこのままで推移するものと思われる。
入域の自由化の数年前から、インド中央政府が運営するインド政府観光局は、従前より自由に訪問できたアッサム州、メガーラヤ州と合わせて、北東諸州の観光についてキャンペーンを張ってきた。その背景には、石油をはじめとする地下資源に恵まれたアッサム州、石材と石炭を豊富に産出するメガーラヤ州を除けば、北東州でもとりわけアッサムの東側にある四州(ナガランド州、ミゾラム州、マニプル州、トリプラー州)については、開発が遅れており、これといった産業も資源もないだけに、財政的に中央政府が全面的に面倒をみるしかない状態から脱却すべく、唯一可能性がある観光面での発展に期待をかけているという現実がある。
それはさておき、平地との往来が制限されてきた地域であるだけに、州境を越えただけでずいぶんな違いが感じられた。アッサム州らしい茶園が広がる風景の中、しばらく山間の坂道を上った先にはナガランド州境のチェックポストがあり、モンゴロイド系の風貌をしたナガランド警察のポリスたちがクルマの中を覗きこむ。
そこからさらに進んだところにある集落では、平地から来たらしき人の姿はチラホラ見かけるものの、マジョリティは私たちと同じモンゴロイド系の人々となってしまう。あたりに点在するヒンドゥー教のお寺や祠はなく、十字架を掲げた教会の景色となる。州境を挟んでクルマで30分ほど走っただけで、カルカッタから成田の空港まで飛んだくらいの大きな違いがあるといっても過言ではない。
アッサム州から入ると、しばらくは良好な道路であったものの、進むにつれて道幅がとても細くてガタガタした部分が増えてくる。標高がさほどではないことを覗けば、ヒマーチャル・プラデーシュ州やスィッキム州と景色が似ている感じはするものの、路面状況はかなり劣るようだ。
沿道で道路等の工事作業をしている人たちの大半は平地のインドの人たちだが、集落や村に暮らしている住民の大半はナガ族の人々。ミャンマーに住んでいる人たちとも似ている気はするものの、この地には仏法が及ぶことはなかった。仏教的あるいはヒンドゥー教的なバックグラウンドのないモンゴロイドの人々というのは私にはあまり馴染みがないが、インドとミャンマーという、どちらもインド起源の大宗教が広く深く伝播した地域の境目にありながらも、この地域が空白地帯であったことが不思議に感じられる。

スズキのヴァンに運転手含めて8名が乗ると大変窮屈である。マリャーニーから80キロ程度の距離ながらも、くねくねと曲がった山道であること、路面状況もあまり良好ではないため、5時間ほどかかりモコクチュンの市街地が見えるところまでやってきた。


〈続く〉