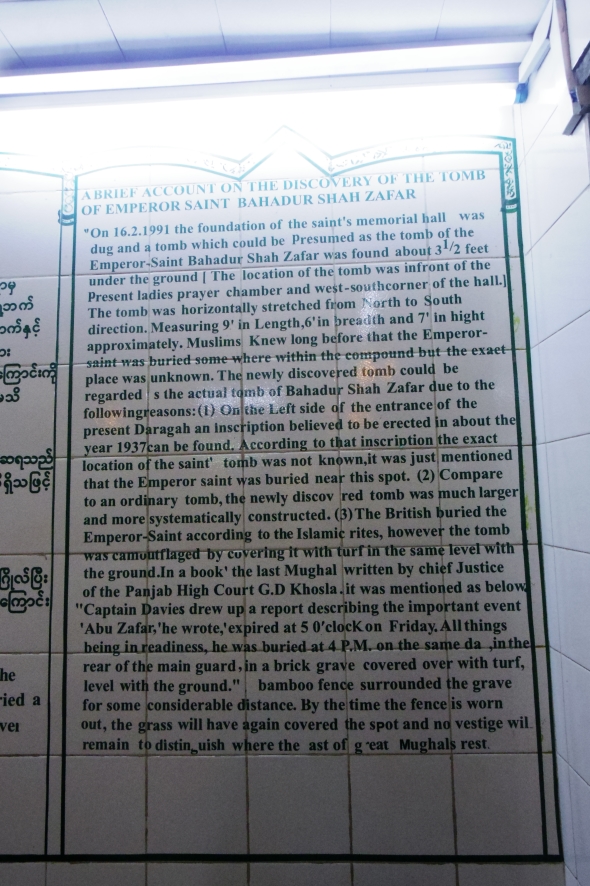ミャンマー・ブームでヤンゴンの宿泊費が高騰しているのはよく知られているところだが、地方の観光地もまた同様の傾向がある。国際的にも有名なバガンやマンダレーはそれでも元々の客室数のキャパがあるので急騰するというほどのことはないのかもしれないが、よりマイナーで訪れるお客が少なかったところでは、存在する宿の数が限られているため、ヤンゴンのようなビジネスや投資関係での需要はほとんどなくても、観光客がこれまでよりも少し多く訪れるようになるだけで、ずいぶん影響が出るようだ。
スィットウェで、エアコンが付いているちょっと小奇麗なシングルルームが40ドル前後もするというのは明らかにおかしい。経営者たちの間でそういう密約があるのかどうかは知らないが、宿の数自体が数えるほどしかないため、そのようなことが可能となってしまう。これについては外国人料金が設定されているため、地元の人たちが同額を支払っているわけではないようだ。
たいていの宿では外国人料金がいくらで、地元料金がいくらであるかは教えてくれなかったりするのだが、ごく新しく出来た比較的安めの一軒ではその料金が前者はドル建て、後者についてはチャット建てで表記されていた。チラリと見ただけだが倍以上の開きがあるようだ。
今後、ミャンマーの経済成長が進み、観光のインフラも整備されていくにつれて、国内の旅客の潜在的な需要も大きい。今後、宿泊費に関する内外格差が解消するのかどうかはよくわからないが、宿泊施設が増えていくことにより、相対的に料金が手頃になっていくことを期待したいものだ。
結局、この町ではストランド・ロードにあるストランド・ホテルという名前のホテルに宿泊することにした。まるでヤンゴンにある東南アジアを代表する名門のひとつであったホテルのようなロケーションと名前だが、これとはまったく無関係の新築ホテルである。シングルルームで60ドルと、この田舎町にしてはずいぶん強気な設定だが、開業してからまだひと月とのことで、ロンリープラネットのようなガイドブックにもまだ取り上げられていないのだが、すっかりくたびれた感じの宿に40ドル、50ドル支払うよりも気持ちがいいので投宿することにした。やはり宿は新しいに限る。非常に清潔で、コテージタイプというのもいい。室内もスタイリッシュだし、スタッフもフレッシュな雰囲気でキビキビと働いている。
水際に政府関係の大きな建物や市場などが並び、水運時代の植民地期に開かれた当時のたたずまいを残しているようだ。ここを軸にして背後に繁華街、そしてさらに裏手には住宅地が広がる。マウラミャインも似たような造りの町である。
この時期、市場で外見はビワのような小型のマンゴーが売られている。上の画像の左側の小さなものがそのタイプである。姿形に似つかわしくなく、味はそのままマンゴーなのだが、水分が多くて酸味も強いジューシーな味わい。果実の量に比して種子の部分が大きいため、あまり食べられる部分は多くはないのだが。ひとくちにマンゴーといっても、実にいろんな種類があるものだ。
河沿いのマーケットには米のマーケットもある。実にいろいろな種類のコメがあるもので、インディカ系のコメにもいろいろ粒が小さかったり、大きかったり、赤みを帯びていたり、もち米であったりといろいろある。もち米はやはりシャンのものであるという。輸入米もインドからの長粒種、タイ産のものもある。世界的な米の大産地であるこの国でも、外国から輸入もしているとは知らなかった。個々の嗜好によりいろいろな米を食べているのだろう。
それはさておき、日中の気温は40℃くらいまで上がるので、夕方のビールが実に旨い!
〈続く〉