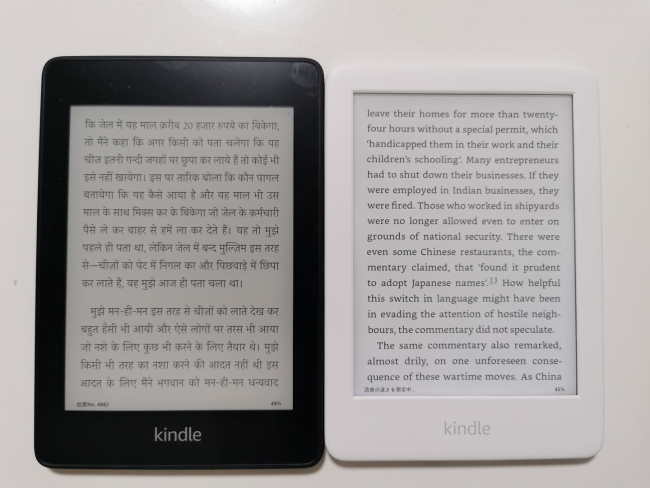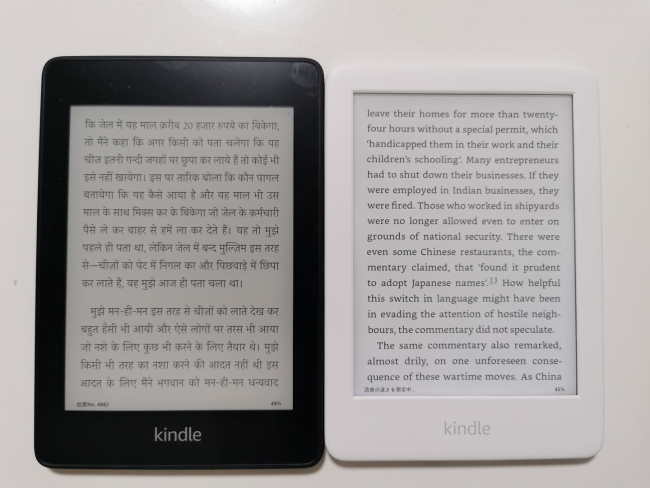常々、前向きで楽しく、人々が元気になるニュースばかり流す「ハッピーニュース・チャンネル」のようなものがあれば良いのにと思っていた。
巨大地震のような災害のときにも、新型コロナウイルスの流行が頂点に達してにっちもさっちもいかないときでも、そういう苦境で人々を救うべく奮闘している人たちや回復して元気になった人たちなどの姿もある。もちろんそうした状況とは関係なく、明るい話題というものは常にそのあたりに転がっているはずだ。ただ、何か大きなことが起きると、そうしたポジティヴな話題にスポットライトが当たらなくなってしまう。悪いことが起きると、畳みかけるように様々なチャンネルで繰り返し報じられて、気が滅入ってしまう思いをした人は多いだろう。繰り返し映像で流れるアメリカのツインタワーの崩壊シーンであったり、日本の東北で起きた津波の様子であったりといったものはその典型であった。
「ハッピーニュース」の需要はインドでも高かったようで、今年9月から、インドのIndia Todayグループのニュースチャンネル「AajTak」に姉妹番組「Good News Today」が加わった。前者はご存じのとおりインドや世界のニュースを人々に伝えるヒンディー語のニュース番組だが、このたび開始された後者は、まさに私が夢想していた「ハッピーニュース・チャンネル」そのものといった構想で開始されたものだ。いずれもインドでオンエアされているものが動画配信されており、もちろん日本での視聴することができる。
放送開始時の映像は以下のリンク先から閲覧できるが、コロナ禍の中でパンデミックに関する陰鬱な報道が非常に多い中で、「気分が沈むのでニュース番組を観たくなくなった」という声を背景に、人々が前向きになることができる、元気の出るニュースを届けるチャンネルとして開始されたとのことだ。「ニュースを変えるのではなく、視点を変える」ことをポリシーにしているのだそうだ。
Good News Today Live TV | GNT TV Live | Watch Live Good News Today Launch (Youtube)
ライヴ放送は、こちらから観ることができるが、「Good News」とは言っても、能天気に愉快なニュースを垂れ流すというものではなく、政治の動向、公害などの社会問題なども取り上げられているなどバランスの取れたものであるようだし、ニュースとニュースの合間にバジャンの演奏なども入ったりして和める。
インドのテレビニュースで多い誘拐、殺人などの事件、視聴者などが投稿したリンチ映像の転用などといった、お茶の間ではあまり目にしたくない凄惨な映像とは無縁のチャンネルは家庭の団欒のひとときなどで流れる、ある意味安心なニュース番組としても支持されるのではないかと思う。