ヒンディー語のわかる者としては、マラーティー語圏にあっても、看板を見て何の店だかわかったり、書かれている内容が把握できるのは助かる。南インドだと3倍の大きさの字で書いてあってもわからない。
同様にメニューなどを見て現地での呼び方などもわかる。またマラーティー語新聞を手にしてみて、何が書かれているのかある程度想像がつくのもありがたい。背景にある語彙に共通性が高いため、文字が共通するだけで非常に便利な部分が多い。これはネパールを訪れても同様だ。



ヒンディー語のわかる者としては、マラーティー語圏にあっても、看板を見て何の店だかわかったり、書かれている内容が把握できるのは助かる。南インドだと3倍の大きさの字で書いてあってもわからない。
同様にメニューなどを見て現地での呼び方などもわかる。またマラーティー語新聞を手にしてみて、何が書かれているのかある程度想像がつくのもありがたい。背景にある語彙に共通性が高いため、文字が共通するだけで非常に便利な部分が多い。これはネパールを訪れても同様だ。


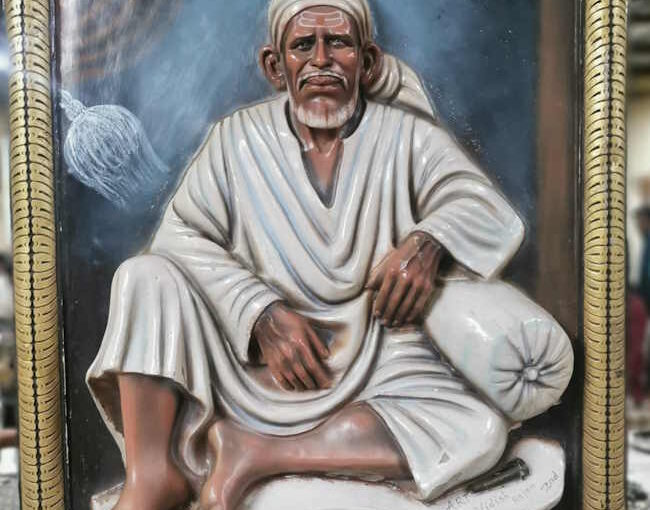
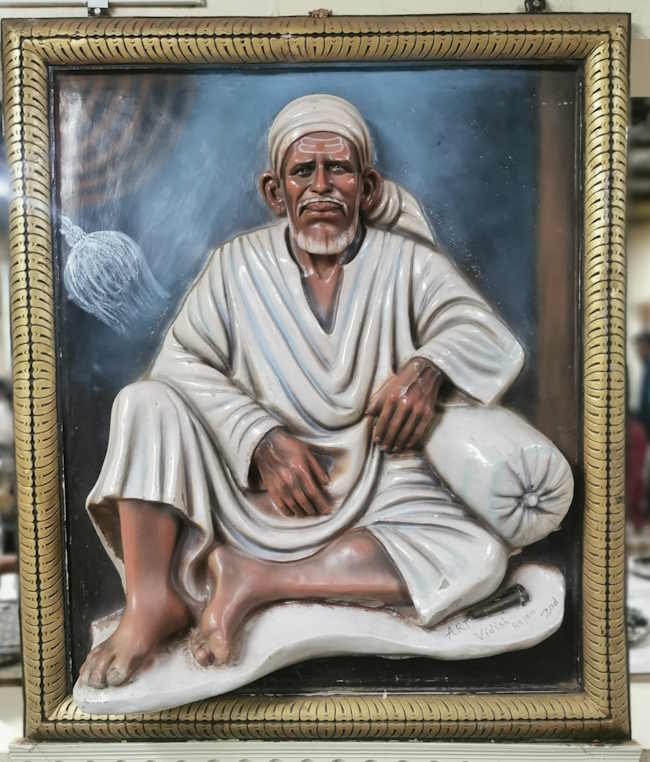
夕飯で入ったレストラン。ボロいし裏手にある小さな食堂に見えるのだが、広い裏庭があり、そこにはたくさんの席がある。


店先の席にはジャンジーラー島で見かけたようなスクールトリップの男の子たちがいて、ただでさえ騒々しいのに、次から次へとやってきては同じような質問を繰り返したり、一緒に写真撮ってとくるのが面倒くさい。「ああ、もう嫌だ」と裏庭の席に行くと、そこは女子席になっていてずいぶん静かだった。


 とても美味なフィッシュターリー
とても美味なフィッシュターリー
あぁ良かったと食事を注文して待っていると、男の子たちに較べると遠慮があるぶん可愛げがあるのだが、やはり入れ代わり立ち代わりやってきては「どこから来ましたか?」「インドは好きですか?」などとお決まりの質問を繰り返したり、一緒にセルフィー撮ってくれというのは変わらない。
それでも男の子たちとは頻度がまったく違う。それにしばらくこちらの様子を窺いながら、思い立ったようにしてやってくるのが女の子たちだ。男の子たちは、こちらに気がついた瞬間にスマホを手にして「セルフィー取らせてや!」とずんずん飛び込んでくるのだ。
いずれにしても、このあたりの「どんどん前に出てくる」感じは日本の子供たちには見習って欲しい。インドの子供たちは、「どこから来ましたか」「インド好きですか?」「インドのどこがいいですか?」「僕らは✕✕から来ました。✕✕を知ってますか?」「インドの食べ物は好きですか?」「スズキ、トヨタ、ソニー!」「カラテ、ジャッキーチェン!」などと質問や質問にもならないようなことをブチまけながら、僕も私も、あいつもこいつもと、次々にセルフィーを取りに来て、あまりに過ぎると引率の先生が「コラぁ〜!」と遮りに来るほどなのだが。
日本に来た外国人旅行者が日本の修学旅行の学生・生徒たちに囲まれて閉口したなんて話は聞いたこともないし、たぶんそんなことも起きないだろう。
それはそうと、日本でもセレブであったら常日頃からどこに行ってもこんな状態なのだろう。こんなのはとても面倒くさいため、やはり私はセレブにならなくて実に良かったと思う。




デーヴァナーガリー文字圏(ヒンディーベルトに加えて、マハーラーシュトラ、ネパール)で興味深いと思うのは、サンスクリット語等古語からの借用語については古語の綴りをきっちり踏襲するのに、外国語からの借用語については大きな揺れがあることだ。
ヒンディーでटिकट (ティカット)がマラーティーではतिकीट(ティキート)となり、最初のTは反転音ですらない。
おそらくグジャラーティーやベンガーリーでも同様に「古語はきっちり正確、外来語はバラてんでバラバラ」という具合ではなかろうかという推測もできる。
DICE+にお試し加入。「ガザの美容室」と「ラッカは静かに虐殺されていく」を観たかったため。無料期間の2週間のみ利用する予定。入会金はなく、月額費用だけなので、今後も興味を引かれる作品があれば、ひと月だけ入るかもしれない。
「ガザの美容室」は、パレスチナ人との結婚によりガザに移住し、アラビア語に堪能なロシア人女性が経営する店とそこに集う女性顧客たちの間でストーリーが展開していく。始めから終わりまで、店内(及び店の前の道路)のみで完結する話なのだが、店内で繰り広げられる女性たちの確執と外で始まる戦闘がシンクロしていき、緊張感とスピード感に溢れる力作。
キリスト教徒の店主、店内の10人の顧客たちのひとり、敬虔な女性を除けば、誰もヒジャーブを着用せずタンクトップやブラウスなどラフな洋装の女性のみの空間。ただ画面の姿のみ眺めていると、スペインやポルトガルなど、南欧のひとコマのようにも見える。パレスチナを含むレバント地方はかつてローマ帝国の領域。後にアラブ世界に飲み込まれたとはいえ、DNA的には南ヨーロッパとあまり変わらないため、造作の似た人たちがいるのは当然のこと。人種よりも文化や言語が世界を区分するのである。
「ラッカは静かに虐殺されていく」は、ISISの「イスラーム国」首都となってしまった故郷ラッカで抑圧される同胞を救おうと国外で反ISIS活動を進めるジャーナリストたちのグループを題材にした作品。重たいテーマだが、事実をベースにしているだけに大変見応えのある作品であった。
両方ともアラビア語による作品だが、mumkin(可能)、umr(年齢)、qabzaa(占有)、maut(死)、mushkil(困難)、bilkul(まったくもって)、galat(過ち)、kharaab(悪い)、jawaab(返事)、tasveer(写真)、hamla(攻撃)、aazaadee(自由)、khauf(恐怖)、qatl(殺人)、yaani(つまるところ)等々、ごく日常的な馴染み深い語彙がたくさん出てくる。ヒンディー語にはアラビア語から入った語が多いからだ。
これがアラビア語ではなく、アフガニスタンを舞台裏にしたダリー語(ペルシャ語)映画だったりすると、ペルシャ語起源のヒンディー語彙もまた膨大なのので、耳で音を追いながら字幕を見ていると、インドにおける西方からの影響はいかに巨大かつ圧倒的なものであったかをヒシヒシと感じる。
もちろん言葉だけではなく、ヒーナー(日本語ではよく「ヘンナ」と表記される)、パルダー(男女隔離)、履物を手にして相手を叩く(最大級の侮辱表現)等々の日常的な習慣などにもごく当たり前に西方から入ったものが生きており、それは食事や建築手法などでも同様。
またアラビア語ではなく、ペルシャ式の表現として、インドのニュースで凶悪犯に対する「Saza-e- Maut(死刑)」判決の報道、道を歩けばダーバーやレストランの名前で「Sher-e-Punjb」をよく目にする。
パキスタンからの越境テロが起きると、その背後に「Jaish-e-Mohammad」や「Lashkar-e-Toiba」といった原理主義武装組織の名前が挙がる。ペルシャ語式に接尾辞「e」を所有決定子として前後の語を繋ぐことは日常ないのだが、「e」で繋いだひとまとまりの語が外来語として用いられているのだろう。
中東方面の映画やドキュメンタリーなどを見ると、様々なものを西から東へと運んだ「偏西風」のようなものを強く感じる。
インドのニュースをつけると、今年の11月に5州(ミゾラム、チャッティースガル、ラージャスターン、マッディャ・プラデーシュ、テーランガーナー)で行われる州議会選挙のニュースと関連のディベートプログラムがたくさん。
私がいつも観るのはヒンディー語ニュースであるため、ミゾラム州政治は地元少数民族政党の争いなのでメインストリームの政治と関連が薄くほとんど報じられないが、ヒンディーベルトのチャッティースガル、ラージャスターン、マッディャ・プラデーシュの3州は、まさにインド政治の主戦場なので火花が出そうな勢いでの報道。ミゾラムよりは扱いの頻度は高いとはいえ、南インドの重要州テーランガーナーについてもヒンディー語放送でフォーカスが当たる度合いはあまり高くはない。
このあたりについては、英語メディアでも拠点となる街の位置する都市やそれが属する州とその近隣州が中心となるため、ごくいくつかのメディアをウォッチングしているだけではインド関連のニュースをまんべんなく吸収しようとすることはできない。政治の潮流も州や地域毎に、まるで別の世界、別の国のようであったりするため、「日本の約8倍」という物理的な面積よりも、さらにインドの政治・社会的な広がりは大きい。
11月の5州における州議会選挙は、来年4月~5月に予定されている中央政府の下院選挙の前哨戦と位置づけられる面が強いため、内外からの注目はとりわけ高い。
インドでは伝統的に「注目されるムスリム政党」は存在しなかった。独立以来、ムスリム票を集めるのは中道左派の国民会議派(及び左派政党)、1980年代以降は特定の地域政党もムスリムからの集票に強いものが出てきたが、「国政で存在感を持つムスリムによるムスリムのためのムスリムの政党」というものはなかった。(独立以降、ムスリムの政党がなかったわけではない)
近年、大きく注目を集めているのがAIMIM。100年近く前にハイデラーバードで発足した政党だが、現在の党首アサードゥッディーン・オーウェースィーが指揮するようになってから各地に活動を広げるようになった。
ただし「ムスリムの政党」といっても急進的な宗教政党ではなく、オーウェースィー自身がそうであるように、リベラルで世俗的なイスラーム教徒による世俗政党。ゆえに国民会議派と支持層が重なるため、国民会議派とは犬猿の仲。
ゆえに「BJPのBチーム」などとも言われる。つまりAIMIMに票が流れた分、国民会議派の得票が減るからである。
5州の選挙結果、うちミゾラムは独自の密室空間のようなものなのでさておき、その他4州の開票結果がどのようなものになるのか、その結果を受けて来年の国政選挙(下院選挙)が極右モーディー政権の続投か、あるいは会議派率いるINDIA ( Indian National Developmental Inclusive Alliance)がこの流れを止めるのか、とても興味のあるところである。


9月9日から10日にかけて、インドのデリーで開催されるG20での夕食会への招待状が同国大統領の名前で送られたが、その書面に「The President of India」ではなく、「The President of Bharat」とあることが明らかとなり、一気にメディアや野党が大騒ぎする事態に。
これまでもBJP議員やその周辺から英語名の「India(インディア)」を廃して「Bharat(バーラト)」にという提案がなされていたこともあり、近々英語国名をそのように変更するのではないかという観測が一気に広まった。
これについては賛否両論ある。大切な国名の変更について正式な動議も議論もなされず、手続きもなしでこのようなことを行うことについて、反対の声が上がるのは当然のことだ。そのいっぽうで、日本が英語で「Japan」であるように、国外からの他称がそのまま英語による国名になっているのと同じように、「India」も欧州からの他称であり、何千年も前からこの地域は「Bharat」であり、ヒンディー語等による国名も昔から「Bharat」だ。英語名が同じ「Bharat」になること自体について反対する理由はないだろう。
奇しくも来年4月~5月に予定されている総選挙で、BJP陣営に対抗する野党連合が「India Gathbandhan〈India連合〉」という名乗りを上げたのに対して、BJPは「Bharat」で対抗する形になる。India vs Bharat。BJP言うところの「イギリスに隷属したIndia」と「威厳と誇りを取り戻したBharat」の戦いとなり、選挙キャンペーンにおいてもわかりやすく、明快な対立軸の構築となる。
街の名前はよく変わるインドだが、さすがに国名を変えるとなると、その限りではないはずだが、案外「選挙キャンペーンも兼ねて」ということでトントン拍子に進んでいくのかもしれない。国名変更には国会で2/3以上の賛成が必要だが、これはほぼ間違いなく確保できることだろう。ちなみにインドはこれまでに幾度も「憲法改正」を重ねている。
ちなみに「Hindustan(ヒンドゥスターン)」もインドという国を表す言葉としてあるではないかと思われるかもしれない。「Hindistan Motors」「Hindustan Times」等々、ヒンドゥスターンを冠した社名、メディア名等もあるが、「Hindustan」はペルシャ方面からのインドに対する他称で、それがインド国内でも定着したもの。よってBharatのような由緒あるものではないということ。

タミルナードゥ州に行くと、あまりにヒンディーが聞こえてこない環境に唖然としたりする。大きな鉄道駅や空港などで北インドからやってきた人たち同士の会話で聞こえてくる以外は、「部屋でテレビをつけないと聞こえてこない」といっても大げさではないのだが、人々に話しかけてみても同様だ。
インドのどこにでもUP州やビハール州などから来た労働者たちは多く、タクシーやオートの運転手にも多い(インドの都市部でこうした運転手はそうしたところからたくさんやってくる。例えばデリーにしてもムンバイにしても、運転手が現地の人というのは稀で、普通はUPやビハールの人たちが多数だ)のだが、タミルナードゥ州はこの限りではなく、北インドその他の州では当然のごとく通じていた言葉が通じず、さりとて彼らが英語をよく理解するわけでもないため、とても不便に感じる。
ヒンディー語、バンジャービー語等、アーリア系の北インドの言語とは系統を異にするドラヴィダ系の言葉のひとつであるタミル語圏なのでヒンディーが通じないと思っている人は少なくないが、そういう単純なものでもない。ドラヴィダ語圏でもカンナダ語、テルグ語圏に行くと、確かにヒンディー語が「誰彼構わず通じる」具合ではないとはいえ、タミルナードゥ州でのような「まったく圏外」みたいに極端なものではないし、その言葉に対する拒否感のようなものもないようだ。また、同様に言語の系統は異なっても、私たちと似た風貌の北東のモンゴロイド地域であるスィッキム州はもちろんのこと、ナガランド州、メガーラヤ州などでもヒンディー語はかなり広く通じるため、インド広く通じる共通語としての役割を持つヒンディーの神通力のようなものを感じる。言語圏が異なっても国内であれば相当程度通じて当たり前なのだ。ついでに言えばネパールでもごく当たり前に通じるため、インドのいわゆる「ヒンディーベルト」(ヒンディー語を母語とする州)を少し外れたところを旅行するのと変わらない。(もっともネパール語とヒンディー語は近い関係にあるがゆえ、そしてテレビや映画などの影響も大きいらしい。)
タミルナードゥでの状況は、同州で長く続いてきた不健康な「アイデンティティー・ポリティクス」の結果、学校教育の場でヒンディー語を教えるカリキュラムすらないというヒンディー語排除の行政があるからだ。インドで学校の試験にヒンディー語はない(西ベンガル州など)というような州はあっても、最初から教えすらしないというのは、ここくらいのものだろう。こんな政治がよく続いているものだ。結果として北インドからの労働者の浸透度合いが低いため、地元の雇用が守られているという側面はあるのかもしれない。反北インドという姿勢があるがゆえのことだが、タミル語のボキャブラリーにはおびただしい量のサンスクリット起源(北インド起源)の語彙が含まれているため、「北インド的なるもの」を否定し切れるものでもない。
タミルナードゥでも例外はある。イスラーム教徒が集住している地域で、そうしたところにはマドラサーがあり、ウルドゥー語が教えられているため、言葉が通じる人たちは多い。実はこれはインド国外でも、ミャンマーのような例があり、都市部に暮らすムスリム(多数派はインド系)であっても、迫害を受けて多数国外に流出しているラカイン州のロヒンギャーの人たちであっても、インド系ムスリムの人たちが当然身につけているべき教養のひとつとして「ウルドゥー語」があるため、書き文字と語彙層の差を除けば事実上の同一言語であるヒンディー語で普通に会話できることが多いのだ。タミルナードゥにおいては、ムスリム集住地区に限っては、州政府が無視しているヒンディー語をマドラサーの教育を通じて、ウルドゥー語という形で習得しているという奇妙な捻じれがある。
ともあれ言葉というものは民族のアイデンティティーに深く結びついているものなので、同じ国にありながらも反発する対象であったり、民族性とは別に信仰から来る受容があったり、国籍は違っても維持すべき文化であったりと、実にいろいろな役割や象徴的なバリューを持ち合わせているものだと思う。
When you speak HINDI in TAMIL NADU | Vikram | Madhuri | Vikkals (Youtube)


INDIA TVの人気プログラム「アープ・キー・アダーラト(あなたの法廷)」。そのときどきの注目されている人たち、俳優、政治家、財界人その他をスタジオに呼び、裁判の尋問と答弁の形で、様々な質問から本人の回答を引き出すというもの。
このところ話題のバゲーシュワル・ダームのディレーンドラ・シャストリーが出演することが予告されていたが、うっかり見逃した。しかしYouTubeで見ることができた。今という時代に感謝である。
まだ26歳の「バーバー」。装いもチェック柄の衣装であったり、このところ気に入っているらしい帽子をよく被って現れるなど、世俗的で、とてもヒンドゥーの「聖者」には見えない。相手を手玉に取るセリフ回し(インド人はこういうのが好きだ)や話もうまい。まだ自分を「大人に見せよう」と苦心している様子もうかがえるが、年齢を重ねるにつれて、それらしくなっていくことだろう。
これまでは田舎で周辺地域から信者を集める新興の「バーバー」だったが、このところメディアで日々取り上げられるようになったため、全国の田舎の人たちから注目する存在になるかもしれない。彼は教えが素晴らしいとか、人格が高潔であるなどといったものではなく、まったく反対に「怪しげな奇跡を演出する」「資金の出処や流れが不明」他、インチキくさいバーバーとして耳目を集めている。
マッディヤ・プラデーシュでとても貧しいブラーフマンの家に生まれ、学校はドロップアウト。リクシャーを引いていた時期もあったとされる。そんな若者が数年間で父母や祖父母世代をも含めた信者層を集める存在となり、一気に有名になったため、彼のアーシュラムにはBJPの代議士たちも信者に顔を売るために表敬訪問するようにさえなってきた。頭のキレは良くて話も上手い彼をプロデュースした黒幕がいるのかどうかは知らないが、少なくともどこかから資金やノウハウの援助は受けてきたはず。
スタートアップ企業の将来性を見込んで投資する人たちがいるように「将来のバーバー」に対して先行投資をする人たちがいるはずなのだ。日本でもそうだが、こうした宗教関係団体というものは、会社組織と同じ。販売しているモノが「信仰」という目に見えないものであることを除けば。
この若い「バーバー」の組織は、田舎からそのまま展開して全国を商圏とするテレビショッピングの「ジャパネットたかた」みたいな感じで将来インド全国へと展開していくことになるのだろうか。若年層人口が分厚いインドでは、彼の若さもプラスに作用し得る。若い人たちにとって同世代で勢いがあり、見た目も悪くない「バーバー」が人気を集めることになっても不思議ではないように思われる。


雑誌や新聞の電子版購読プラットフォーム「Magzter」は米国の企業だが、在米インド人が起業したインドのメディア購読を主目的とするものであるため、米国のメディアの扱いはあまりないという捻じれがあった。
しかしながらこのところNewsweekその他のアメリカの雑誌が次々エントリーされている。
しかしそれでもようやく「今度はTIMEも!」と宣伝しているくらいなので、やはりアメリカのメディアには弱い「アメリカの電子版メディア購読プラットフォーム」。
それにしても「インドメディアほぼ専門」でありながらも米国で操業というのは、おそらく法的その他の環境から、インドでこういうビジネスの操業は容易でなく、米国でのほうがやりやすいというようなことがあるのだろう。
「Magzter」はいろいろなニュース週刊誌に加えて、大手各紙の様々な地方版を読むことができるという点でも素晴らしく、とりわけ読み放題の「GOLD」に加入すると、その真価を発揮する。
来年5月に総選挙を迎えるインドでは、BJPが再び地名変更の動きを見せている。UP州のLUCKNOW(ラクナウ)をLAKHANPUR(ラカンプル)またはLAKSHMANPUR(ラクシュマンプル)にという案が浮上。いずれにしても取って付けたような名称ではなく、それなりにきちんとその土地に由緒あるものであるとはいえ、長らく「LUCKNOW」として知られてきた州都、旧アワド王国の都の名前をそのような形に変更してしまうというのは、ヒンドゥー至上主義右派によるイスラーム文化やイスラーム支配の歴史のあからさまな否定でもある。
Rename Lucknow as Lakshmanpur or Lakhanpur’: BJP MP urges Amit Shah(INDIA TV)
独立以来、インド各地で地名等の変更が行われてきたが、その目的は主に以下のようなものであった。
同様に、各地のストリート名などが、植民地時代の行政官等に因んだ名前からインドの偉人や独立の志士などの名前に変更されている。インドに限らず植民地支配から脱した国々の多くでこのような名称変更は実施されていることはご存知のとおり。
しかしBJPが政権を握るようになってからは、それ以前は見られなかった新たな形での名称変更が続いている。
3.ムスリムの支配や影響を色濃く残す地名を「ヒンドゥー化」する。(ALLAHABAD→PRAYAGRAJ、OSMANABAD→DARASHIV、HOSHANGABAD→NARMADAPURAM等)
この③のタイプの改名については、コミュナルな背景の意思が働いているため①及び②とは異なり、注意が必要となる。
先述のとおり、2024年5月に総選挙が実施されることに先立ち、今後もこのような地名変更の提案が続くものと予想される。州都ラクナウのような伝統ある地名が③の形で改名されてしまうようなことが本当に起きるとは信じ難いものがあるが、グジャラートのAHMEDABAD(アーメダバード)についても、KARNAWATI(カルナワティ)に変更しようという動きもある。ひょっとすると首都DELHI(デリー)についても、INDRAPRASTHA(インドラプラスタ)に改称される未来が来るのではないかと冗談半分に言われているが、数年後にそういう日がやってきたとしても、あまり驚くに値しないのかもしれない。
頻繁に地名変更を提案したり、それを実施したりしているBJP政権だが、報道を注意深く見ていると、そのような方向に本格的に動き出したことが大きく報じられる前に、国会議員なり地方議会議員なりの「個人的な意見」という形で、しばしば観測気球のようなものが上がっていることに気が付く。
以下の記事は昨年末の報道だが、BJPの議員により「インドの国名を改めよう」という意見。
「INDIA」を「BHARAT(バーラト=ヒンドゥーの地)」あるいは「BHARATVARSH(バーラトワルシュ=バーラトの大地)」に変更しよういうものだ。
これについては、例えば英語で「JAPAN」と呼ばれてきたのを「NIHON」あるいは「NIPPON」に変えようというようなもの。外からの呼称を内での呼び方に揃えようというもの違和感は薄い。(インド国外でBHARATという名称をご存知ない方も少なくないかと思うので、もしかすると耳慣れない奇妙な呼称に感じるかもしれないが・・・。)
いっぽうでインド、INDIAの別称として「HINDUSTAN(ヒンドゥスターン)」もある。企業名でも「HINDUSTAN MOTORS」「HINDUSTAN PETROLEUM」等々、「HINDUSTAN」を冠したものは多く、日常会話でも自国のことを「ヒンドゥスターン」と普通に呼ぶので、なぜ「HINDUSTAN」にしないのか?と思う方もあるかもしれないが、BJPのようなサフラン右翼(サフラン色はヒンドゥーの神聖な色)にとって、やはり「BHARAT」あるいは「BHARATVARSH」こそが、あるべき母国の名称ということになる。
なぜならば「HINDUSTAN」という名前は、元々はペルシャ(及びペルシャ語圏)の人々から見たインドに対する呼称であって、インドの人々が自国をそう呼ぶようになったのは、ペルシャ語圏から入ってきたその名称が定着したからに他ならないからということが背景にある。


ヒンディー語映画好きな私ではあるが、そのいっぽうで南インド映画もオーバーアクションな作品もほとんど観ないのだが、ヒューマントラスト渋谷で鑑賞したテルグ語作品「RRR」の重厚感ある造りとともに、作品中で幾度も展開されるどんでん返しにすっかり圧倒された。
息つく暇もないパワフルなストーリーがどんどん進んでいき、派手なアクションシーンとともに体力も消耗した気がする。面白い作品であった。
しかし不思議に思われるのは、なぜ今の時代になって反英ストーリーなのか?
かつても植民地時代を描いた作品はいくつもあったが、民族自立への大義、志士への共感であったり、独立指導者たちと英国当局トップとの駆け引きであったりというものが多かったように思う。
植民地時代を経験した世代には、英国統治への畏敬の念の記憶とともに、分離独立後前後の混乱、独立後長く続いた低成長時代への不満等もあったためか、インドを統治した英国人たちを、とんでもない人でなしと描写するものはあまりなかったように記憶している。
北米内のように英国をはじめとする欧州から入植者たちがどんどん押し寄せて開墾しながら現地の人々を外へ外へと追い出していくような具合ではなく、数少ない英国人たちが多くの現地の人々を雇用したり登用したりして築いていったのが英領インド。この映画で描写されるように現地の人たちをすぐに殴ったり足げにしたり、上層部はすべて英国人でインド人たちはみんな下働きという社会でもなかった。
反対に、舞台として設定されている1920年代には、それまでに英国がインドでの人材育成に力を入れてきた甲斐もあって、多くのインド人たちが高級官僚、裁判官、文化人、起業家などとして社会に台頭していた。
これとは逆に鉄道技師、クルマのエンジニアといった現業部門に従事していた英国人たちが、インド人上司の指示のもとでせっせと働くという場面はごく当たり前のものであったし、英国が間接統治していた藩王国で雇用されていた英国人等の欧州系の人々もあった。安定した生活を送ることが出来るとも限らず、両親がともに病や事故で倒れて孤児となる英国人、欧州人の子供たちも少なくなかった時代でもある。
つまり英国人の圧政に汲々とするインド人というような単純な構図ではなかったのである。英国人だからということだけで社会上層部にいられるはずもなく、インド人であるからといって下働きに甘んじなければならない社会でもなかった。世の中というのはそういうものだ。
あくまでもフィクションの娯楽映画ではあるものの、このような調子で英領時代を描く作品が続くと、総体的に人口構成が若いインド人たちの間で、自分たちの知らない往時のことが、ずいぶん捻じ曲げて解釈・理解されてしまうような気がする。たぶんこのような形でも「歴史の書き換え」がなされてしまうのだと思う。
長年、アーメダバードのことを「エヘムダーバード」と読むものと思っていた。ヒンディーでの綴りと読みはそうなっていて、それはそれで正しいはずなのだが、通常地元では「アムダーバード」と呼ばれているようだ。
「Ahmedabad/ エヘムダーバード」は、グジャラートのスルターン王朝の「Ahmed Shah/エヘマド・シャーハ」に因んで名付けられたもの。BJP支配下の州で相次ぐ地名浄化の中、イスラーム教浸透以前の「カルナーワティー」に改名しようという動きもあったが、幸いまだ実現していない。
「エヘムダーバード」か「アムダーバード」かは、デリーのことをウルドゥーで「デーヘリー」と呼ぶか、ヒンディーで「ディッリー」と呼ぶかの違いのようなものなのだろう。
やはり太古の名前「カルナーワティー」や「インドラプラスタ」がサフラン右派にとっては超復古主義的でインパクトの強い魅力的なオプションとなるのはわかるような気がする。