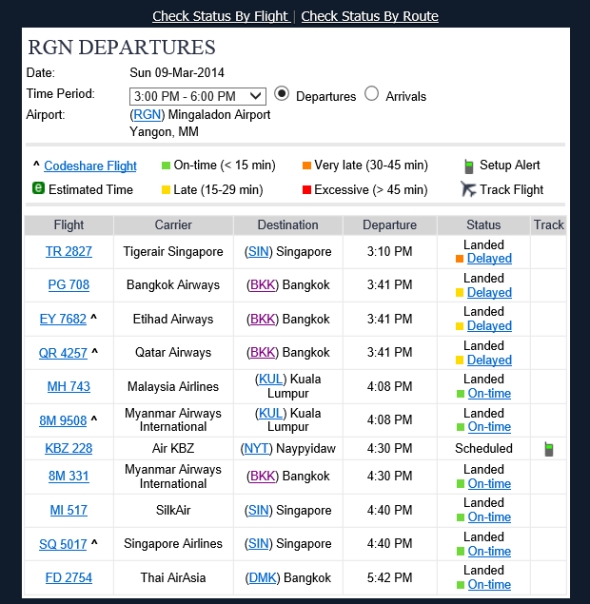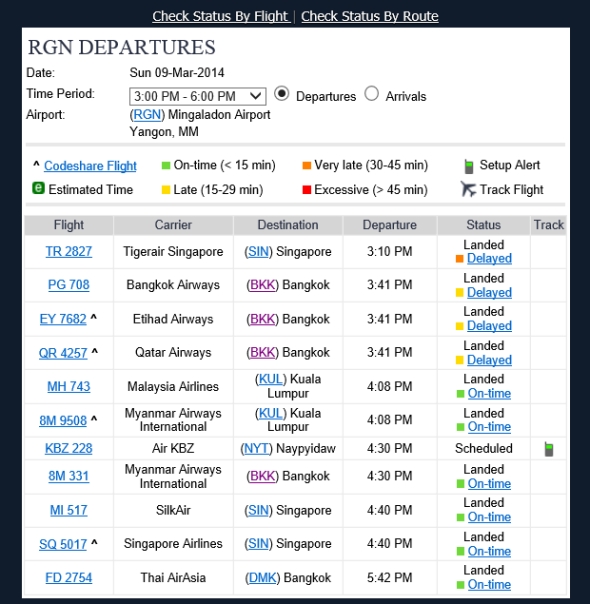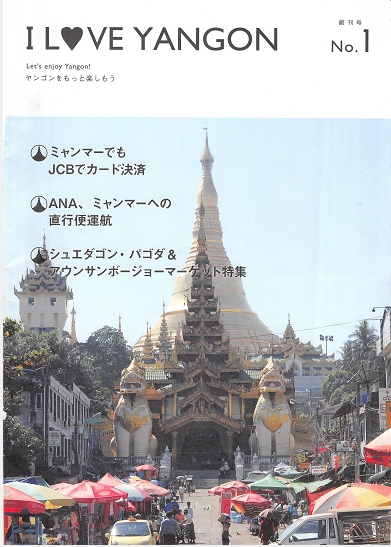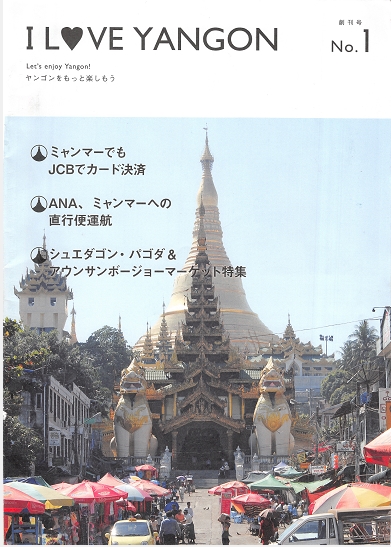ミャンマーのヤカイン州都スィットウェは、かつてアキャブと呼ばれた港町。南アジアから東南アジアへの玄関口でもあり、イギリスによるミャンマー攻略と支配もここに始まった。

1784年、当時のアラカン王国を征服して属国化させて以降、西方へと更なる拡張を模索していたビルマのコンバウン朝が1822年に英領のベンガルへ軍を進めたことがきっかけとなり、1824年に今度はイギリスがビルマへ軍を展開したことにより、第一次英緬戦争が勃発することとなった。その2年後にアラカンとテナセリウムがイギリスに対して割譲されることとなる。
このアラカンを足掛かりとして、1852年に第二次英緬戦争が起き、今度は下ビルマを自国領に組み入れ、さらには1885年の第三次英緬戦争で、マンダレーを王都とするコンバウン朝を滅亡させて、上ビルマをも手に入れることにより、イギリスによるビルマ征服が達成されることとなった。
アラカンの支配的民族であったアラカン族は、現在はバングラデシュとなっているチッタゴン地域にも影響を及ぼしていた時期がある。それがゆえにこの地域も本来はミャンマーの領土であると唱える向きもあるほど、東南アジアと南アジアの境目であり、そのふたつの世界の行き来が盛んな地域でもあった。
だが、現在はヤカイン州と呼ばれているアラカン地方は辺境の地となり、経済的にも政治的にも重要な拠点であったアキャブは、今は州都スィットウェとして知られているものの、パッとしない田舎町に成り果てている。
カラーダーン河口部に位置するこの町の水際に公的機関、市場、それより内側に商業地、その背後には住宅地という、植民地期の水運時代に建設された貿易港らしい造りである。
目下、インドの援助により、スィットウェのひなびた港は深海港に生まれ変わる工事が進行中であり、完成した暁にはスィットウェは物流の重要なハブとしての役割を担うこととなる。長期的には、東南アジア地域から南アジア各国を始めとする、ミャンマーから見て西側に位置する地域との物流ということになるのだろうが、インドにとってはこれとは異なる思惑がある。
インド本土からバングラデシュ国境と中国国境の間で、通称「チキンネック」と呼ばれる、陸路の細い「スィリーグリー回廊」を経て同国の東北部にかろうじて繋がっている物流ルートを補完する役割だ。
更には、インド北東部とミャンマーを繋ぐ陸路については、もっと北回りでの鉄路と道路での構想があるのだが、これについては以下のリンクをご参照願いたい。
インドにとって、物流のハブとしてのミャンマー西部の発展への期待は、そのまま自国北東部の振興に直結するものであることから、このあたりへの援助ならびに投資は当然のごとく相当な力のこもったものになるわけだ。とりわけスィットウェの港湾設備に対するコミットメントがいかに大きなものであるかについては、インドがこの町に領事館を設置することになっているということから、その期待値の大きさがうかがい知れるというものだ。
ちなみにミャンマーにおけるインドの在外公館は、現在までのところヤンゴンの大使館とマンダレーの領事館であり、スィットウェの領事館がオープンすれば、ミャンマーに三つめの在外公館を出す初めての国ということになる。それほどミャンマーはインドにとって大切な国になりつつある。

地味な港町スィットウェだが、今後10年ほどのスパンで眺めれば、これまた地味なインド北東部との繋がりが深まることにより、ともにちょっとした地味ながらも着実な成長と変化を呼び込む結果を生むのではないかと思う。どちらも現状では「この世の行き止まり」であるかのような具合になっているがゆえに、海路・鉄路・陸路の接続が与えるインパクトには測り知れない影響力が秘められているものであると思われる。

〈続く〉