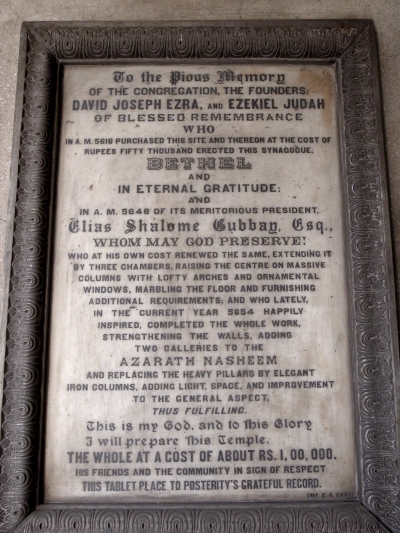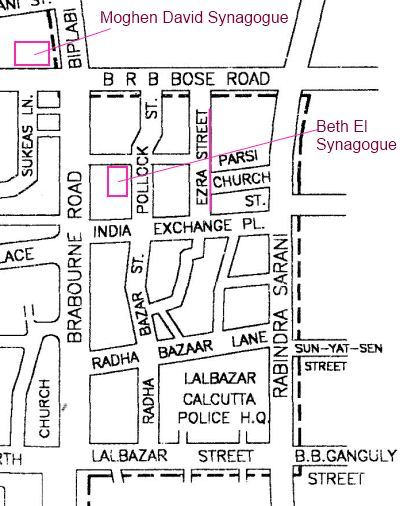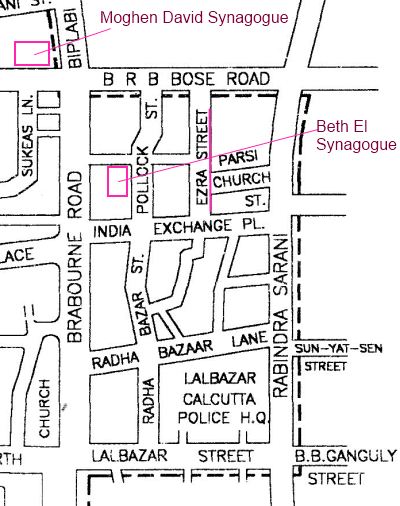オンカデリーという集落で定期市が開かれる日である。
簡単な朝食を済ませて、昨日約束しておいたクルマに乗り込んで出発したのは午前8時。緑と水に恵まれた美しい丘陵地の中を通る州道をひた走る。途中の町で右折すると、そこから先はクルマ1台が通れるくらいの幅で路面もガタガタの田舎道となる。
このあたりからは丘陵地というよりも、山道といった感じになってくる。傾斜はさほどでもないが樹木が多い。そうした中にところどころ耕作された土地が見られる。この地域を含むオリッサ州の内陸部は、インド有数のトライバル・エリアとして知られている。
地形としては「ゆるい山間部」とでも形容しておこうか。他の地域とそれほど隔絶した世界というわけでもなさそうなのに、どうして様々な部族が多く残されているのだろうか。このエリアが発展から取り残された地域であることと、州自体の人口密度が高くないため、人口圧力もあまりないということがあるかもしれない。
ただしオリッサ州は地下資源が有望な地域でもあり、そうした資源開発と先住民の権利との間に生じる摩擦も絶えない。近年話題になっているものとしては、インド系英国資本(ムンバイーで創立され現在本社をロンドンに置いている)の ヴェーダンタ社によるオリッサ州のニヤームギリーでの操業は、元々ここに暮らしてきたドングリヤー・コンド族に対する『迫害』ということになり、深刻な人権侵害として複数の市民団体等から告発されている。
The Story of a Sacred Mountain (Tribal International)
Niyamgiri and Vedanta (Environmental Protection Group, Orissa)
運転手はオンカデリーに行くのは初めてのようで、このあたりからは途中で人に尋ねながら走っている。そうした相手の中には普通のオリッサ人もあれば、見るからに部族らしき人もある。オンカデリーに着いたのは午前11時くらいであった。コーラープトから3時間ほどかかった。
普段は静かなごく小さなマーケットであるが、毎週木曜日だけは近隣地域から部族の人たちが大勢集まって交易する場所として知られている。オリッサ西部の部族地域ではこうした場所がいくつもあり、場所により曜日は様々なのだが、こうした形で市場が開かれているらしい。

オンカデリーの集落の入口あたりでクルマから降りるが、通りにはずいぶん沢山の人々が集まっているのに驚かされる。その中には街中では見かけない格好をした部族の人々の姿がとても多い。ボーンダー、ガダバー、ディダイその他の部族たちである。

弓矢を持って歩くボーンダー族男性の姿が目立つ。この部族の女性たちはカラフルなビーズをあしらった頭飾りと特徴的な衣装を着ている。皆かなり小柄である。女性たちはマーケットで自家醸造の酒を売っている。大根から造ったものと米から造ったものがある。世の中に大根から出来た酒があるとは今日初めて知った。密造酒ということになるが、少数民族の生活習慣なので、定期市ではお目こぼしなのだろう。
ボーンダー族の男性たちにしてみれば、弓矢を身につけているということは、ちょうどスィク教徒にとってのキルパーンのように、男性としての象徴的な意味があるのだろうが、武器を手にしている男たちが酒を飲んで酔うという図には穏やかでないものがある。

ここに来てちょっと驚いたのは、外国人のツアー客らしき人たちの姿がかなりあることだ。最初に見かけたのは5名の西洋人グループ、そして7、8名の日本人グループがいた。オリッサの部族地域についてインターネットで検索してみると、地元オリッサや外国のツアー・オペレーターによる企画ものを紹介するサイトが引っかかったりするが、このようにして訪れる人々は決して少なくないようだ。
そのためだろう、普通に市場の眺めを撮影している分には問題ないが、特定の人物を近くで撮る(もちろん相手の同意が必要)場合、10ルピーを撮影対象の人物に渡すことが習慣になってしまっている。
都市部において、社会の周縁部から出てきた部族の人たちは、バーザールで売られているごくありきたりの衣類を着ているものだ。作るのに手間ヒマのかかる民族衣装よりも、バーザールで購入する大量生産された安価な衣類のほうが経済的に楽だろう。
また民族独自の衣装は、自らのアイデンティティを象徴するものではあるが、そうした『記号』的なものを見に付けることにより、インド人の大海の中では差別ないしは軽視される対象としての目印ともなり得る。
オンカデリーのような集落の外の山々はまるごと部族社会であり、彼らの普段の生活圏内であるためだろう。まだまだ伝統的ないでたちをしている人たちが多い男性たちの間では洋服を着ている人々がかなりあるが、女性は民族衣装を着ている割合がとても高い。部族の人たちにとっては、山あいの村から『町に出る』週に一度のハレの日であるため、こうして着飾りたいということもあるのだろう。

もちろんそういう格好で各部族の人々が集まってくるがゆえに、そうした定期市を見学するツアーが企画されていたりもするわけである。そうしたツアーでは部族の村などにも訪問するようだ。
さらに観光化が進めば、こうした場で民族衣装を纏う動機が『観光客に撮影させて報酬を得る』という具合になっていくことも考えられる。ちょうどタイ北部の山岳少数民族でそういうケースが多いように。少なくとも前述の『撮影=10ルピー』という慣習から、これを臨時収入の手段として認識していることは間違いないだろう。
あるいは各民族の日用品等が『伝統工芸品』として販売されるようになったり、特徴的な衣装(往々にしてオリジナルをかなりアレンジしたもの)が観光客目当てに製造・販売されるようになったりすることもあるかもしれない。
定期市が開かれるのは、オリッサ人が主体の集落の中にあるマーケットである。そのため建物の中や常設のマーケットのスペースで商うのは、主にオリッサ人たちである。それに対して路上や空きスペースなどで、部族ごとに集まって品物を広げているのは集落の周辺地域(・・・といっても山道を数時間もかけて徒歩でやってくる人々もある)からやってきたマイノリティの人々である。
部族の人々は、酒以外には主に村で収穫した野菜や果実といった農作物を販売している。定期市は、彼らが現金収入を上げる手段であり、同時に村では手に入れることのできない工業製品を購入する機会でもある。
ロンリープラネットのガイドブックには『Onkadelli should only be visited with a professional guide』などと書かれていたため、一体どんなところかと思っていたが、案外普通の田舎のマーケットである。
ただ普遍的なマーケットと視覚的に異なるのは、様々な格好をした部族の人々が大勢来ていることだ。加えて密造酒が堂々と販売され、主に部族の人々がこれをおおっぴらに酌み交わしていることだろうか。
ただしここに集まっている部族の人々の姿をいろいろ目にしても、彼らの具体的な文化背景等が皆目わからないのはもったいない。そういう意味でやはりこの地域に精通するガイドを雇って訪れたほうがいいだろう。
少数民族目当てで定期市を訪れる外国人客がチラホラいるため、オンカデリーのマーケットでもガイドを自称する者たちが存在する。だが彼らの知識は非常に限られたものであり、ひどくブロークンな英語(並びにその程度のヒンディー)しか使えない人たちなので、敢えて雇ってみるメリットはあまりないように思う。
ただしこの地域の住民である彼らは、少数民族の村に囲まれたこの小さな町で生まれ育っているため、幼い頃から公立学校でそうしたマイノリティの子供たちと学校で机を並べ、また現在も日常的にそうした人々と接しているという生活環境下にあるため、近隣の民族の専門的な知識はほとんどなくても、彼らの中に知己が多く生活習慣等日常的なトピックにはけっこう詳しかったりするのだが。

<続く>