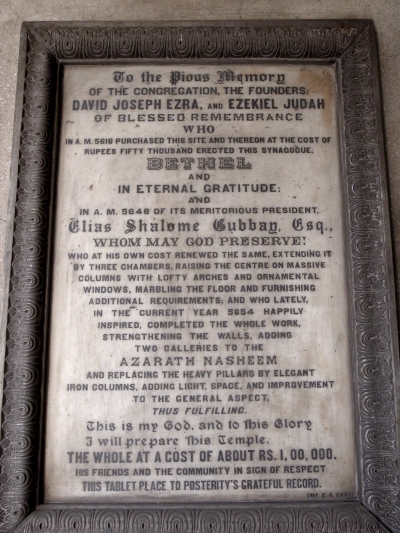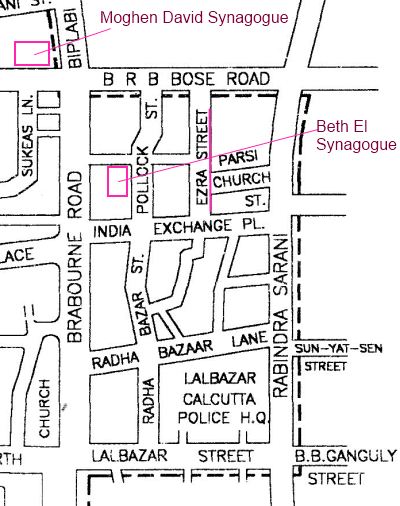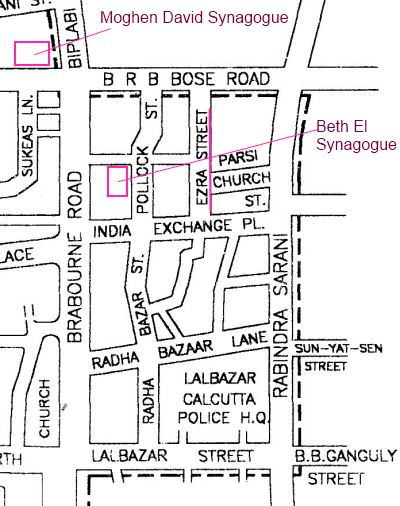その名に惹かれて訪れてみたくなった。
エスプラネードのバスターミナルに行きダイヤモンド・ハーバー行きを探す。幾度か訪れたことがあるというコールカーター在住の知人の話では『1時間半前後だよ』という話であったが、バスに乗り込んでみると乗客たちは『3時間はかかる』と言う。
距離にして45キロほどしかないので、何かの間違いではないかと思ったが、事実きっかり3時間かかった。ずいぶん飛ばしていたのだが、1時間に15キロしか進んでいないことになる。かなり大きく迂回ルートで走るバスであったのかもしれない。市街地の渋滞を抜けて郊外に出てからは、のどかな田園風景を眺めながら走るので心地よかった。
ダイヤモンド・ハーバーに着いた。田舎町ではあるが、コールカーターから日帰りで訪れる人が多く、乗ってきたバスもそうであったが、降りてみるとそういう感じの人々の姿がよく目につく。
カルカッタでもそうだが、このあたりでも舗装道路の表面の大部分はコールタールといった感じで、砂利のザラザラ感に欠ける。滑り止めということだろうか、規則的に小さなレンガ片が埋め込まれている。道路脇にはレンガを砕いた砂利状のものが沢山あるので、道路の基礎はそれらで作っているのだろう。
ダイヤモンド・ハーバーの見所は、海かと思うほど幅の広い河の眺めと英国が残した商館跡。地元の人はキラー(城・城砦)と呼ぶが、コールカーター建設前の東インド会社が拠点としていた場所である。漢字で『商館』と書いてイメージするものとはかなり異なる、物々しい施設であったに違いない。
河の船着き場に出た。空気が霞んでいて対岸が見えない。波がほとんどないことで、ここは海ではなく河であることが実感できる。今、ディガー方面に向かう船が出るとのこと。見た目にはどこに行くとも知れないところに出航していくかのような船の様子は印象的である。私も乗り込んでみたくなったが、まだ商館跡を訪れていないし、今日中にコールカーターに戻らなくてはいけないのでやめておく。
この河の深さは相当あるようで、大洋から航行して来たと思われる巨大な貨物船が悠々と遡上していく。かなりの速度が出ているようだ。少なくとも道路を走るバスのスピードに近いものはあると思われる。
コールカーターから楽に日帰りできる距離ではあるが町中に宿泊施設は多く、簡単な食堂を併設しているところもある。適当に腹ごしらえしてから商館跡に向かうことにする。
幹線道路に貼り付く形で町が続いているが、通りから逸れて河岸の商館跡に至る小道に入るすぐ手前で5ルピーの入場料金が徴収される。岸辺では地元観光客相手にゴザやシートの上で料理を作る人たちがいる。頭上を見上げると、砂糖ヤシに素焼きのツボが取り付けられている。その樹液を集めてから、これを煮詰めて粗糖を作る人たちも何組かある。
商館の建物がきちんとした形で残っているわけではないことは知っていたが、現地を訪れてみてびっくりする。ごく一部の基礎部分は残っているものの、『ここが東インド会社の商館跡である』と感じさせるものはほとんどないからである。
こうなってしまった理由には、もちろん史跡として顧みられることがなかったということもさることながら、元々建物があった部分が大きく河に浸食されたこともあるようだ足元には大量の赤レンガ片があり、どれもすっかり角が丸くなっている。これらはかつてここに存在した建物の名残であろう。想像力を最大限に発揮して、往時の様子を想像してみる。
商館跡の見物後、サイクル・リクシャーで鉄道駅に向かう。コールカーターからのバスを降りたところのすぐ近くである。幸いすぐに次の電車が来るとのことであったし、想像していたほど込んでいるわけではなかった。シアルダー駅まで2時間ほどとのこと。 ダイヤモンド・ハーバー駅はこの支線の終着駅だ。
電車は田園風景の只中を走る。大半は刈り入れが終わった殺風景なものだが、ごく一部では苗代があり、田植えの風景も見られる。時期外れの田植えの際の稲の種類は違うのだろうか、それとも夏に育成するものと同じだろうか?途中駅ではホームに籾を広げて乾燥させていたりする。のんびりしたものである。
カルカッタではいろいろな地域から来ている人たちが多いため、人々の顔立ちには様々なものがある。だがこの車内はほとんどベンガル人ばかりのようで、乗客たちの顔を眺めているとあたかもバーングラーデーシュに来たような気にもなる。
美しい田園風景はホータープルという駅でほぼ終わる。そこから先は田畑と市街地が入り混じり、そしてやがてカルカッタ郊外に出た。ほどなくバリーガンジ駅に着く。界隈で所用があるため、ここで下車する。