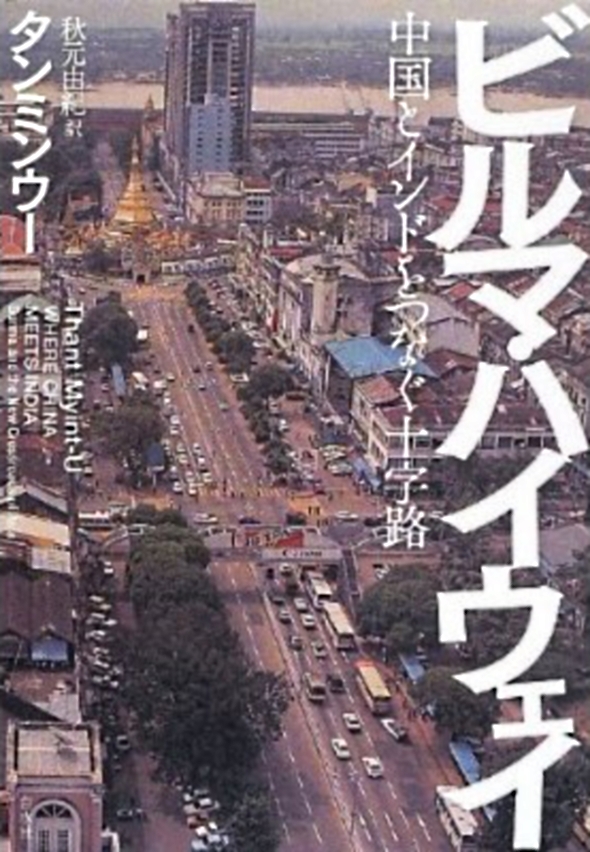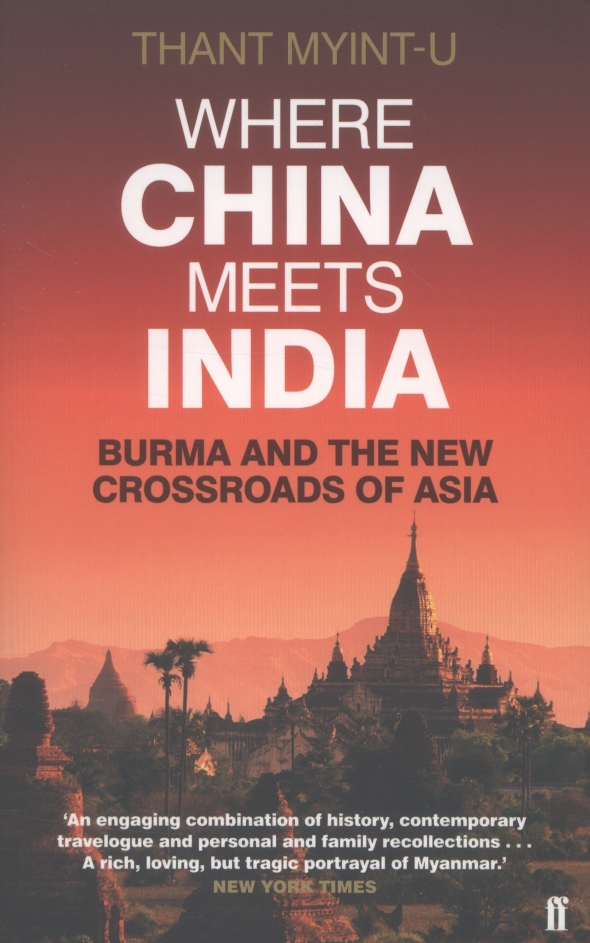教会といえば大半がバプティスト
教会といえば大半がバプティスト
 教会
教会
朝7時に頼んでいた朝食を摂るために階下に降りる。隣席にはアッサムから家族と来ているインド人。この人は釣りが趣味とのことで、北東地域ではとりわけアルナーチャル・プラデーシュがお気に入りとのこと。
「でもどの土地も所有者が決まっていて、釣りしていると、ここではダメだと言われることもよくある。これが平地と違うところだね。平地でも土地の所有者は決まっているけれども、釣りをしていて何か言われることは特にないよ。」
この人は、アッサム州の人で、近隣州に住んでいることもあるかと思うが、アルナーチャル・プラデーシュ州の少数民族事情にもかなり詳しい。最近のインドの人たちは、自国内を広く観光するようになったこともあってか、その地域のマイノリティの習慣や社会についてもかなり知識や関心を持っている人が増えているようだ。
昔はインド人の観光といえば、タージマハルのような超メジャー級の観光地か巡礼地と相場が決まっていたが、今はインド中どこに行っても、それこそ西洋人の姿を見かけないところであっても、インド人観光客はいたりする。バイクで旅行する人たちが多くなってもいる。
90年代から一大ブームとなった国内観光も、さすがにこれだけの年月を経ると、いろんなスタイルの人たちが出てきている。夏にラダックで会った、デリーでの勤めを辞めてバイク旅行していた若者のように、「自分探し」の旅行をしている人たちもいる。自分探しというのは決して悪いことではないと思う。もともとありもしない自分を探すのではなく、「こう成り得る自分」を追求する旅であるからだ。この人は、ライター志望で、そのために旅行していた。ライターとして身を立てる自分と自身が書く題材を見つけるための旅である。
外に出て歩いてみると、昨日はクルマが出入りしていたり、路肩に駐車していた商業地では車両の姿をまったく見かけないようになっているし、どこに行っても商店はすべて閉まっているという徹底した休日モードである。走るクルマもほとんどない。皆が自発的に休みとしているのか、それとも行政や組合が休みとするように強制しているのかはよくわからない。インドの他の地域と大きく異なるのは、どこまでも徹底して休みとなるので外で食事はおろか、軽食さえもみつかならないこと、そして交通機関も姿を消してしまうため、移動もできないことだ。クリスマスだけではなく、ふだんの週末も同様の状況となる。
 どこも店は閉まっている。
どこも店は閉まっている。
 人々は自発的に休んでいるのか、それとも政治的に強要されるのか?
人々は自発的に休んでいるのか、それとも政治的に強要されるのか?
教会には人々が集まり、ミサを行っている。しばしば賛美歌が聞こえてくる。細い路地で行き交う人々と「メリー・クリスマス!」と声かけ合うのが心地よい。ミサの後はクリスマスの食事が教会近くで振舞われている。年に一度の大きな行事なのでみな楽しそうである。精一杯のおしゃれをして教会に集まっているのだ。住宅地あちこちにクリスマスの飾り付けがなされている。万国共通のデザインではあるものの、クリスマスツリーの意匠は日本のそれとずいぶん異なる。
 教会近くの広場で、ミサに集まった人々に振舞われる食事
教会近くの広場で、ミサに集まった人々に振舞われる食事
教会に人が沢山集まっているのとは裏腹に、家の中で家事にいそしむ人たちもある。教会への関心はやはり人それぞれなのだろう。私が受けた印象では、教会に集まるのはどうしても、より知的でどちらかといえば裕福な層が多いように思える。晴れ着を持っていないと、そういう場に出るのは気が引けるということもあるかもしれない。男性は洋装が多いが、ナガのショールを纏って出席する人もいる。女性も洋装が多いが、ナガの伝統的な女性の衣装の人たちの姿もある。どちらもパリッと着こなしていて、いい感じだ。
今日もあちこちで爆竹が鳴り響いている。精一杯着飾った人たちが教会に出入りして、賛美歌が流れてくる雰囲気と、戦争でもしているかのような轟音が響く爆竹とではどうもイメージがオーバーラップしないが、おそらく教会には行かないようなタイプの子が鳴らしているのではないかと思う。
モコクチュンにはカレッジまであるが、卒業後に就業機会はなかなかないらしい。就職先として最も条件が良いのは公務員ということになるようだ。他には、何か家業があればそれを引き継ぐか、さもなければ自分で小さな仕事でも始めるしかないという具合とのことで、日本の過疎の田舎と似たようなところもあるかと思う。世帯にはだいたい三人から四人くらいの子供がいるのが普通であるというから、やはりみんなが将来に渡り食べていくには、就業機会が必要である。
斜面の頂上を中心に広がる町なので、ダージリンやシムラーなどのヒル・ステーションとも遠景は似ている。ただしこれらと大きく違うのは英国時代の遺産と思われる建物は見当たらないこと、旅行産業がまだ端緒についてさえいないので、観光客相手らしきレストラン、みやげもの屋といった類が不在であることだ。
観光産業といえば、オーガナイズツアーがまだまだ中心のようだが、そもそも交通のインフラがとても貧弱であることは、そう簡単に克服できることではないだろう。山奥の部族社会であったため、人が造ったもので歴史的な建造物はないため、多くの人々を集めることができるかどうか期待するのは難しいように思う。景色にしても他のヒマラヤ地域のほうが優れているし、文化的な遺産も比較のしようがないほど多い。今後治安が本当に良くなったとしても、トレッキングの需要が高まるとも思えない。ごく最近、パーミット無しで行き来できるようになったという新鮮さはあるが、果たしてこの地で観光業が今後振興するかといえば、かなり困難を伴うように思える。
ただし、可能性といえば、インドの北東部の治安が安定に向かっていること、ビルマの西側も同様であること、ミャンマーが経済の開放に舵を切ったことにより、最近言われているインドとミャンマーを繋ぐ物流ルートが出来ることになったならば、このあたりの経済は大きく変わることだろう。だがそれは、ここにインド本土から巨大な投資とモノと人が流入してくることであり、これまで独立を求めて闘ってきた地元の意思とは相反するものとなる。やがては大インドにそのまま吸収されていくことになるのではないかと思ったりもする。
ここでは日没は午後4時過ぎだ。太陽は山々の向こうに姿を隠している。まだしばらく明るさは残っているが、太陽が見えなくなると急に寒くなってくる。やれやれ。
坂だらけの斜面の町なので、さほどの距離でなくても、かなりくたびれる。こういう町に暮らしていると、高齢者は外出が億劫になることだろう。また足が悪い人のクルマ椅子も危険で使えるような環境ではない急斜面なので、身体の具合の悪い人は外出の機会も少ないことだろう。
日本では山地の町や集落は谷間に形成されることが多いが、ここでは山の頂上ということが多い。社会習慣や伝統上の違いといえばそれまでだが、やはり水の確保は容易ではないらしい。たまたま知り合った地元の水道局職員としばらく話をしたのだが、ずいぶん下の谷間を流れる水をポンプで汲み上げて供給しているという。
コヒマもそうだが、モコクチュンもここまで町が大きくなったのは、比較的近くにそういた水源があること、加えて現在は電気等を利用した技術があるがゆえに、このような規模で人々が居住できることになったのだろう。
モコクチュン郊外にも小さな茶畑がある。気候条件はダージリンあたりに似ているはずなので茶の栽培は当然できるだろう。だがあまりよく手入れされているようではなく、茶の木がかなり背が高くなってしまっているものもある。自家消費用だろうか?
のどかな山間の町のモコクチュンだが、早朝や夜間などに出歩いていると、向こうからやってくる数人組の男性が機関銃を持つ軍人であることにギョッとしたりする。ライフルを背負った警察官ではなく、プロの戦闘員が警備をしているというのが、停戦により平和を救助していながらも、いまだ不安を払拭しきれないナガランド州にいることを感じさせてくれる。
現在、反政府勢力による大きな騒擾が起きていないのは喜ばしいことだ。しかしながら内戦時代を通じて、中国製の武器が大量に流入していること、中国による戦闘員に対する訓練等がなされてきたといった事柄があるがゆえに、インド独立以来半世紀以上に渡って、彼らが当地に展開しているインド軍と互角に渡り合ってきたということになるのだが、同時に市民の間にも相当量の武器類が出回っているものと考えてよいだろう。
これまで、反政府組織による外国人を狙った誘拐行為などは起きていないようだ。また、一般のナガの人たちは礼儀正してく親切だが、どこの国にも悪い奴はいるものである。政治的な問題はさておき、そういう者が武器を持って強盗を働いたり、山賊行為をしたりということは当然あるはずだ。
インド国内にありながらも、インド文化圏外にあり、南アジア世界と東南アジア世界の境目にあることを感じさせてくれるのがこのエリアだ。ただしこの「世界の境目」もまた、ナガランド、マニプル、ミゾラムなど、州や地域により民族や文化習慣等も様々であることは大変興味深い。
 北東インドらしくサッカーは盛んなようだ。こちらは地元の大会のポスター。
北東インドらしくサッカーは盛んなようだ。こちらは地元の大会のポスター。
〈完〉