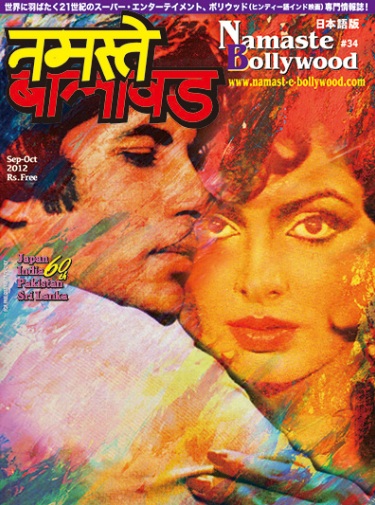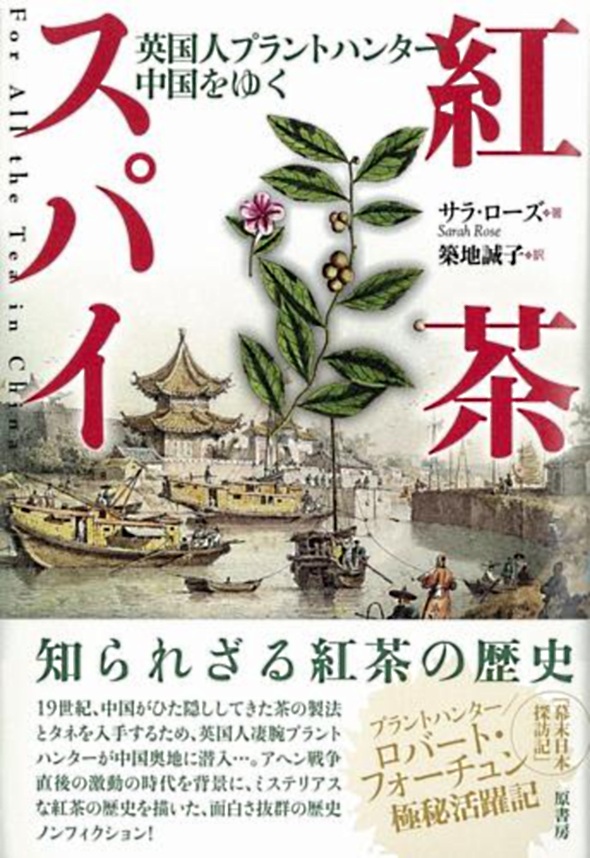夕方のそぞろ歩き
夕方のそぞろ歩き
 Tシャツに描く絵描きさん。なかなか丁寧な仕事をしていらっしゃる。
Tシャツに描く絵描きさん。なかなか丁寧な仕事をしていらっしゃる。
 「死んだ家畜があったらお電話を」とある。そういう仕事もあるようだ。
「死んだ家畜があったらお電話を」とある。そういう仕事もあるようだ。
久しぶりにプシュカルを訪れてみた。ラージャスターン州の他地域同様、ここでもやはり古いハヴェーリー(屋敷)を改築したホテルが人気のようである。多くはカジュアルな宿泊施設で、手頃な料金でこの土地ならではの雰囲気を楽しむことができて楽しい。
宮殿から転用されたホテルは昔からあるが、ラージャスターン州でハヴェーリーを改装した宿泊施設が一般的になったのは、2000年代に入ってからである。それまでは、ほとんど顧みられることもなく荒れ放題であったり、テナントに部屋ごとに細分化して賃貸していたりといった具合で、往時の面影はほとんど残されていないことが多かった。
中世から近世にかけて、商売で成功した人たちが豪奢なハヴェーリーをラージャスターン各地に建築した時代があった。当時とは産業構造が異なり、多くは都市部に居を構えるようになっていたり、一族が肩を寄せ合って暮らすジョイント・ファミリーのような生活形態も過去のものとなっていたりするなど、ライフスタイルも変化している。大家族が暮らしていたハヴェーリーは、往々にして「賃貸物件」として部屋ごとに貸し出され、そこからの収入は大きな街に住むオーナーが受け取り、現地では縁もゆかりもない間借り人たちが住む「アパート」と化している。そこに暮らしているわけではないオーナーも、間借りしているに過ぎない借家人たちも、建物に対する愛着などないので、このコンディションに頓着するはずもない。ゆえにボロボロになってしまうのはやむを得ない。
 こんな建物をよく見かけるが、往時はさぞ立派であったことだろう。
こんな建物をよく見かけるが、往時はさぞ立派であったことだろう。
上の画像は、プシュカルの隣町アジメールのバーザールで撮影したものだが、ラージャスターン各地の商業地域でこのようなハヴェーリーは数多い。もしこれが宿泊施設に転用されたならば、かなり良い収入を見込めるだろう。
だが観光地やその周辺にあるハヴェーリーについては、その資産的価値が見直されているようだ。建物の規模からホテルに充分転用できる可能性があること、一族とはいえ複数の世帯が暮らすように造られていたこともプラスに作用する。商家のハヴェーリーは賑やかで交通の便も良い商業地域にあることが多く、ロケーションの面からも観光客にとって都合が良い。
ラージャスターンらしい意匠や装飾などが外国人客はもとより、インドの他地域から訪れる人々にとってもエキゾチックでアピールするものがある。これらについては、昨年の今ごろ「
旧くて新しいホテル1、
2、
3、
4」でも取り上げてみた。
好立地にある物件ほど、従前より賃借人に部屋ごとに貸し出しているケースが多く、建物の規模が大きいほど、既存のテナントに立ち退いてもらってホテルに転用することが容易ではなかったりするものの、こうした宿泊施設は今後も増加していくものと思われる。
 夕暮れ時の湖
夕暮れ時の湖
 ガートへの入口
ガートへの入口
さて、話はブラフマーの聖地とされるプシュカルに戻る。小さな湖周辺に町並みが広がり、幾つものガートが並ぶ。ガートにも幾つものスピーカーがあり、様々なことがアナウンスされている。「そこの人、サンダルを脱ぎなさい。外国人はちゃんと靴を脱いでいるのに、インド人のあなたは恥ずかしくないのか?」「汚い衣類をガートで洗濯するのはやめなさい」といった具合だ。ガートの様子を逐一監視できるように、監視カメラが設置されているようだ。
ガートに多数出ている看板で、外国人用に英語で書かれているものには、「写真撮影禁止」「禁煙」といった事柄が書かれているのに対して、ヒンディーでインド人用に書いてあるものには、「ここで洗濯するな」とか、「トラストへの寄付は所得税の控除の対象になります。領収書を受領してください」などと書かれている。これら二種類のものは、並んでいるだけに、書いてある内容の相違がさらに際立つ。
こうしたエリアに隣接するラクシュミー・マーケットの裏手に、
Inn Seventh
Heavenという宿がある。かなり建て増しがなされているようではあるものの、入り口の狭いドアをくぐった先にある広々とした中庭を中心に広がる洒落た光景には思わず息を呑む。料金帯の割にはプロフェッショナルなサービスが提供されており、マネジメントもしっかりしていることが窺える。今後長く繁盛するだろう。
 Inn Seventh Heaven
Inn Seventh Heaven

- 最上階のレストランから階下を眺める
 ロビー周辺
ロビー周辺
客室ごとに異なるテーマで装飾等がなされており、それぞれの部屋の前にもソファ、長椅子、ブランコ等々がしつらえてあるのだが、さりとて雑然とした感じにはならずに、上手に統一感を持たせたコーディネートがなされているあたりのセンスの良さからして、経営の主導は在外(インドの都会に暮らす人か、はてまた外国在住者か?)の人の手中にあるのかもしれない。
あまりの人気のため、オフシーズンでも予約は一杯になりがちなので、宿泊の予定が決まれば数日前には電話等で予約しておくべきだ。西洋人の家族連れの利用も多く、子供たちと一緒に快適そうに過ごしている姿が見られる。最上階にしつらえてあるレストランもなかなかいいムードで、気の利いたメニューを提供している。グラウンド・フロアーにあるキッチンから上階に料理を運ぶために、凝った造りの木製の小さなリフトが使用されているのも、見る人の目を楽しませてくれる。
実はすぐ隣にも似たような感じでハヴェーリーを改装してオープンしたホテルがあり、設備等悪くないのだが、同じような料金帯のInn Seventh Heavenかなり見劣りする。やはり内装のセンスの差であり、ランニング姿のオヤジが「いらっしゃい」と出てくるあたりやスタッフというよりも普通の「使用人」然とした従業員など、非プロフェッショナル的で典型的な家族経営のごく普通の宿であるだけに仕方がない。真横にあるホテルが満室でもこちらはガラガラに空いている。
 空いているお隣の宿。正直なところ、ここもなかなかいいのだが、どうしてもInn Seventh Heavenと比較してしまう。
空いているお隣の宿。正直なところ、ここもなかなかいいのだが、どうしてもInn Seventh Heavenと比較してしまう。
それでもプシュカルにはちょっといいホテルが増えた。かつては安旅行者向けの小さなゲストハウスばかりが点在していて、ややアップマーケットな宿泊施設といえば、ラージャスターン州政府観光公社RTDCの
Hotel Sarovarくらいしかなかったのだが、いまやLonely Planetのガイドブックにも掲載されなくなっているほど「無視された」存在となっている。
 RTDCのホテル
RTDCのホテル
ここに限ったことではないが、90年代以降、各地で様々なレベルの宿泊施設に民間資本が参入している。とりわけ宿泊施設については、地域の観光産業振興を牽引する役割は終えているといっていいだろう。事実、インド全土を見渡せば、かつては公営であったホテルが民間に売却された例は少なくない。とりわけ州都規模の街などは、民間大手ホテルグループにとって買収の手を挙げやすいようだ。
さて、今後どのような面白い宿泊施設が出てくることになるのか予想もつかないが、東西南北それぞれの地域で歴史的な資産には事欠かないインドだけに、今後もご当地色豊かなホテルが出現してくるのを待つことにしたい。
 このあたりではホシガメか生息している。
このあたりではホシガメか生息している。