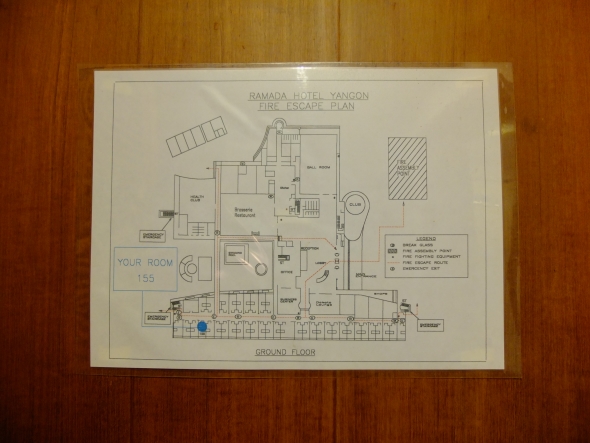点在する村の居住する少数民族がマジョリティとなる山の中では、ビルマ語はあまり通じなくなるらしい。いろいろな言語が散在するこの国らしいことではあるが、村で同じ民族で集住しているため、使う必要がないということもあるだろうし、学校教育の普及程度の関係もあるだろう。
食料品類は基本的に自給自足の生活であるようだ。こうした形で少数民族が村単位で存続できた背景には、それで生活していけるだけの地味の豊かさがあったからに違いない。また周辺地域を統一しようとか、勢力を拡大しようという野望もなく、人々が平和に共存していくことができる状況が続いていたということにもなるのではなかろうか。
もちろん少数民族といっても皆が村に住んでいるわけではなく、町に出て働いている人たちも少なくないはずなので、皆がそういう伝統的な環境で暮らしているということにはならないが。
あれは仏教の寺だとWin氏が指差した先にあるのは、大きいながらも簡素な建物だ。門の上に翻る仏教旗がなければ、これがそうであるとはちょっと気が付かないだろう。規模が大きめな家屋ではないかと思うところだった。

通称、「シャントラック」と呼ばれる、中国製のクルマのシャーシーとエンジンと足回りを流用してトラックに仕上げた、創意工夫の賜物ともいえるトラックが大き目の農家の軒先にあったりする。近くを流れる川の水を有効に活用して、米、野菜、トウモロコシなどが栽培されている。このあたりでは様々な食用になる野草もふんだんにある。



ガイドのウィン氏が指差した先には「マラリアに効く」という野草があった。当然、マラリア原虫を駆除する効力はないはずなので、こうした山間の村で医療施設もないようなところに住んでいる人たちにとって、最大の予防は疲労をためないこと、ひいては睡眠時間をたっぷり取ることしかないだろう。
他にもデングのように同じく蚊が媒介する病気、赤痢やコレラといった他の伝染病も普通にあるはずなので、平和に暮らしていながらも人口があまり増えることがなかったということも、民族ごとの村落社会が長く継続できた理由かもしれない。川から汲んだ水を飲む村人たちの姿を見て、そんなことをふと思う。運不運もあろうが、地域の生活環境に適応できる丈夫な人たちが淘汰されて生き残っているわけである。
山道は、もちろん舗装などされていないダートであるため、雨季の水の流れによって削られていくためであろう、平坦ではなく幾筋もの溝が続いているような具合だ。それでも上のほうから中国製のバイクで駆け下りてくる人たちが少なくない。
ウィン氏によると、そうした人々の多くはパラウン族であるとのこと。元々は馬をよく利用していた人たちであるとのことだが、今の時代になると生身の馬から機械の馬へと乗り換えるようになっているということのようだ。同じような地域に暮らしていても、やはり民族性というのはあるようだ。
シャン族とパラウン族とでは、居住するエリアもかなり違うようで、前者はなるべく平らなところ、そして川の流域に好んで居住するが、後者は山の上のほう、尾根のような見晴の良い場所に村を形成するのだという。また、野生のシカや鳥類などを求めて、よく狩猟をするとのことでもある。集落内の家屋を外から眺めると同じように見えるのだが、生活様式はかなり異なるのではないかと思われる。
さらにどんどん上へと歩いていくと、やがて「ここからパラウン族の地域」とガイド氏は言う。住み分けの境界は少なくともこの地域でははっきりしているようだ。シャンとパラウンが混住する村は、町の近郊ではあるそうだが、それ以外では当混じって住むことはないという。シャンの村はシャン人だけ、パラウンの村はパラウン人だけという具合らしい。
顔立ちは私たちからすると同じに見えるが、言葉や生活習慣も異なるため、また住んでいるエリアが異なるということもあるのだろう。異なる民族間での結婚というのも多くないという。ただそれが不可能というわけではなく、ときにはそういうケースもあるのだそうだ。同じ仏教徒であればそう難しいことではないとも。このあたりの少数民族コミュニティは父系社会なので、異民族と結婚した女性が男性側の村に嫁入りすることになるという。
ただし相手の民族がどうあれ、宗教がクリスチャンであったり、ムスリムであったりということであれば、かなり困難であるそうだ。
「インド出身のムスリムでありながらも、シャン族の仏教徒コミュニティの中に同化していった私の祖父はその中の例外です。」とウィン氏は穏やかに笑う。
山道の上のほうから黒光りする銃器を持って駆け下りてくる男の姿があり、「山賊では?」とちょっと背筋が凍る思いがしたが、ウィン氏と顔見知りのパラウン族で、これから狩りに出かけるとのこと。背後からは彼の子供たちも続いて下りてきた。
チークの木に巻き付くバニヤンの木があった。木は逃げることができない。これから何年か先には、チークの木はバニヤンに絞殺されて、バニヤン自体が大きな木に成長していることだろう。

パラウン族の村の地域に入ると山の斜面に茶の木を見かけるようになってくる。この民族の間では茶の木の栽培が盛んであるとのことだが、ダージリンその他のインドの茶のプランテーションでのたたずまいとかなり違う。通常、木は等間隔で密の植えられるものだが、ここではずいぶん間隔が空いているし、木の背も高くなってしまって伸び放題だ。こんなに背が高くなってしまっている茶の木はインドでは見ない。

収穫された茶葉は、家内工業として粗く製茶されるようだ。「粗く製茶」と言っては失礼かもしれないが、素朴な味わいの中にお茶本来の旨みが感じられて悪くない。
<続く>