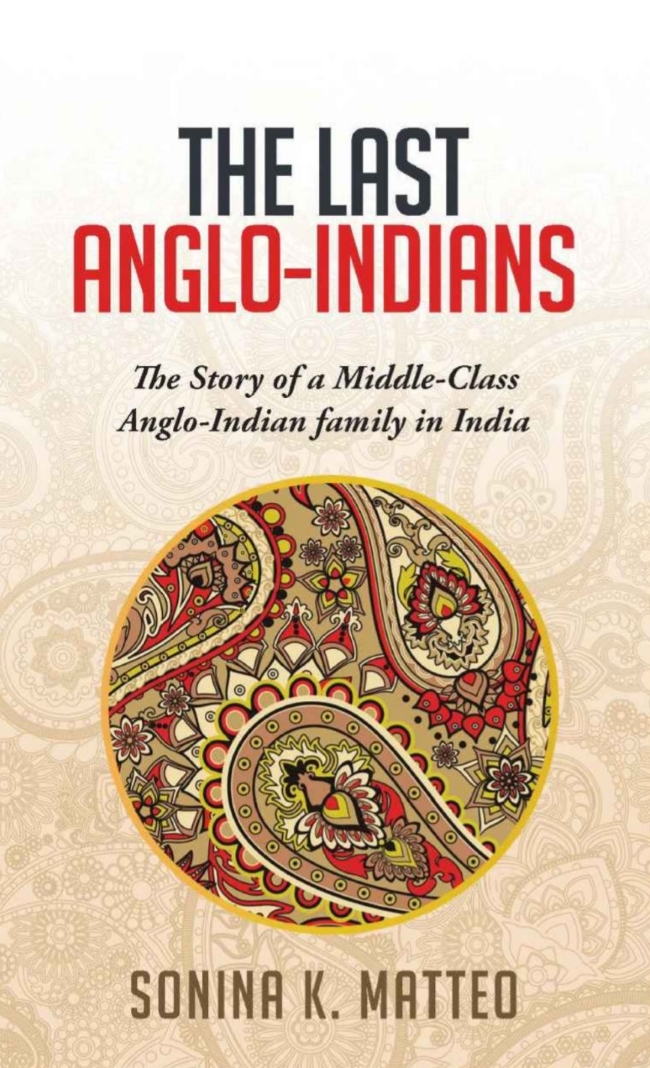アマゾンのKindle版で読んでみた。アングロ・インディアン全般について書かれたものではなく、著者の祖父母、母のインドでの生活の日々から、母親が南米出身の船乗りと結婚して1960年代に米国に移住するまで、19世紀終わりから21世紀に入るまでを淡々と綴った3代に渡る家族史。
インドでは中産階級に位置する家庭だが、一家やその一族は、電報局や鉄道勤務だったり、軍人だったりと、いかにもアングロ・インディアン的な勤め人世帯。
著者が語るに、アングロ・インディアンたちは、土地や家屋を所有せず、多くはアングロ・インディアンたちが多い地域で借家暮らしであったということだが、こうした層の人たちは、多くが転勤族であったことによるのではないかと想像する。アングロ・インディアンの商人層には、これとはまた異なるライフスタイルがあったことだろう。
勤務先での出世といっても、要のポジションに配置されているのは、本国からやってきた英国人。英国系とはいえども、インド生まれの人たちはローカルスタッフの扱いであったようだ。英国もインドも階級社会だが、アングロ・インディアンの中でも、生業や出自、業種や経済状況などにより、いろんなクラスがあったらしい。
1929年から1933年にかけての大恐慌の時代には、インドもひどいとばっちりを受けているが、現地在住のアングロ・インディアンも失業して、文字通り家族で路頭に迷う者も少なくなかったのだそうだ。英国系ということで支配層に比較的近いところにいたとはいえ、やはりそのあたりは、文字通りの勤め人なので、極端な不景気に見舞われると大変である。
家庭料理には、ふんだんにインドらしいメニュー(英国テイストを含んだ)が並び、そのレシピもいくつか紹介されていた。今度、料理してみようかと思う。
一般のインド人家庭よりは、恵まれた環境にあったようだが、それでも10代の反抗期には、グレてしまったり、勉強嫌いで学校からドロップアウトして、家族から離れてしまう者もあったりと、日本で暮らす私たちの家の中で起きることと、同じようなことが書かれている。
ただ、衛生状態や医療水準は今とは違うので、著者の母親は幼い頃、チフスで危うく命を落としかけたようだが、その時代には裕福だったアングロ・インディアンの家庭でも、生まれた子供たちがみんな元気に育つということはなかったらしい。
Kindle読み放題を利用したが、単体で購入しても570円。コスパの高い、英領末期前後のアングロ・インディアンに関する書籍である。